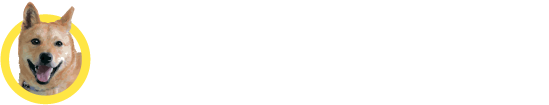保護犬に会いに行く

お散歩中に飼い主とアイコンタクトをとりながら歩いてくる、愛くるしい笑顔のウェルシュ・コーギー。
ふとすれ違いざまにぼくと目が合って、「知ってる、おじさんって犬好きだよね」といった表情で
こちらに視線を向けてくる。ぼくはにっこりしてコーギーを見てから、飼い主さんに会釈をした。
そんなやりとりがあったあとに、考える。
犬と、そのそばにいる飼い主たち。
彼らの人生は、どちらかが先に果てるとしても、幸せにつつまれていることだろう。

そしてぼくはここで、立ちどまることになる。
飼い主のいない犬たち。
保護されたが、一緒に眠る人はいない子たち。
そんな子たちを見にこないか、と誘われていた。
現在の保護犬たちの状況を知ることはとても大切だけれど、まずはなによりも現場を感じてみたい。
その子たちの息づかいをとらえるのは簡単ではないだろうが、
せめて自分の感じたことをスケッチしておきたいし、
その経験をまるで犬みたいに上手に嗅ぎ分けて、その先につなげられればいい。
ここがスタートだ。
保護犬の引き出し現場で

到着したのは「広島県動物愛護センター」。
今日はここでピースワンコ・ジャパンの「引き出し」が行われる。
愛護センターから引き出した保護犬たちをシェルターへ連れていく作業だ。
話を聞くと、ここはもともと野犬の保護が多く、移送にもなかなか骨が折れることが多いという。
「野犬……ですか。なるほど、東京のような都会の愛護センターとはちょっと違う感じですね」
そうなんです、と相づちを打ちながら、ぼくをここまで案内してくれたピースワンコ・ジャパンの塩田さんは話を続ける。
「それでも、犬はみんなちゃんと個性があって、その子なりの魅力がある。
野犬という言い方も、なにか別の呼称はないかなあ、と思っているんですよ」
なるほど、とぼくは返して、野犬の別の呼び名に一瞬思いを馳せてから、口をひらいた。
「名前をつける、という作業はほんとうに大切なことですよね。それはあらためて命を吹き込むようなことで」
「ですよね。考えてみたいです」
そんな会話をしていると、ピースワンコ・ジャパンのプロジェクトリーダーの安倍さんが
年季の入ったハイエースで駐車場にやってきた。
すらりとしたスタイルの安倍さんは、挨拶もそこそこに、颯爽と引き出しの準備にとりかかる。
見学のぼくらもビニール製の防疫服に身をつつみ、愛護センターの内部へ向かった。
長靴に履き替え、靴底の消毒をする。

今回移送される犬たちは、すでにいくつかのケージの中にいた。
そこでぼくがまず感じたことは、絶望や苦痛ではなく、犬たちの生きものとしての普通のたたずまいだ。
そう、犬たちはちゃんと理解している。
そこにいることへの順応さえ見せる。
「怖いから自分の身を守ろうとして、唸ったり歯を剥いたりするだけ」という安倍さんの言葉。
まったくそのとおりだと思う。
犬は人に寄り添い、順応しようとする生きものなのだ。
だとしたら、やはり裏切っているのは人間たち、ということにならないだろうか。
なぜ野犬がうまれる?
どうして犬を捨てる?
そこにいる人たちと、保護犬のやりとり

引き出しは安倍さんが先頭に立ち、愛護センターの職員さんがサポートするかたちで、迅速に行われた。
ケージからケージへ犬たちを誘導し、それをハイエースへ積み込む。
みな慣れている作業だとはいえ、不安を抱える犬たちの移動はそうとう大変そうだ。
ぼくはここでその作業を見学しながら、外に干してあった、
おそらく職員さんたちが洗濯したのであろうタオルたちを思い浮かべていた。
愛護センターの清潔さは、彼らの努力で成り立っている。
清潔にしよう、というのは仕事そのものではない。
職員さんたちの思いが、保護犬たちへの愛情が、そうさせているのだ。
だから、引き出し作業も、なんだかやさしい。
それは安倍さんもそうで、手際はいいが、なんとなくその指先にやさしさが込められているのがわかる。
おかしな言い方かもしれないが、優雅なのだ。
ぺちゃくちゃ話したりはしない。
自信に満ちあふれているが、慢心はない。
犬が人を信頼した「経験」

保護犬たちの引き出しが終わった。
不安に駆られて、思わず噛みつく犬はいなかった。
信頼感という言葉がなんとなく脳裏に浮かび、しばらくそのことを考える。
人が犬を信用し、犬が人を信頼する。
それは飼い主と愛犬の関係に限らない。
刹那の邂逅でわかりあうことも、実際にはあるのではないか。
つまり、ぼくは見逃さなかった。
金属製の丈夫そうな重たいケージを持ち上げるとき、中にいる犬たちは一瞬不安になるが、
すぐにそれを人がしている行為、だと知る。

そうなると、少しだけ犬たちは安心したような表情を浮かべる。
なぜだろう?
それは、犬たちが人を信頼した「経験」があるからだと思う。
暴れたりせず、いまだに人間の行動に応えようとするのだ。
神石高原シェルターへ

「では、シェルターへ参りましょう。そこにもたくさんの、個性的な犬たちがいます」
ピースワンコ・ジャパンの塩田さんにうながされて向かったのは、
愛護センターから1時間ほどクルマで移動した場所にあるシェルター。
ピースワンコ・ジャパンの本拠地でもあり、訊ねてみたかった場所だ。
山あいの高速道路を走り、さらにうっそうとした森を抜け、その先の青空の望めるひらけた場所に、
神石高原シェルターはあった。
整備の行き届いた広いドッグランがいくつかあり、一般客にも開放中。
犬舎にはエアコン、また、床暖房が完備してあるところもあり、
保護犬たちの健康を守るための立派な設備が用意されていた。
あたりをうろうろしていると、お散歩に出た犬たちがめいめいのペースで歩いたり、
走ったり、立ちどまったりしている。
それに付き添うピースワンコ・ジャパンのスタッフはみなさわやかな挨拶を交わしてくれて、
なんとなくこちらが気持ちのよい散歩をしている気分になる。
「まだちょっと怖がりなんですけど……ゆっくり、馴らせていければと思っています」
若いスタッフさんがそう言って、その犬にやさしい視線をおくった。

このシェルターに収容されている犬たちは、200頭ほど。
驚くべき数ではあるが、ピースワンコ・ジャパンのシェルターは広島県に3か所あり、
そこにも収容されていることを考えると、なかなか複雑な気分になる。
だが、どの犬舎の子も、ずいぶんとこの場所に適応し、また人のことを好きになり、
ほかの犬ともうまくつき合えるようになった子たちが目立っていた。
なにかを取り戻した、犬たち。
ドッグランには、発散したい犬たちが集まり、こぞって走り回る姿があった。
その中の一頭がぼくに目を向け、一緒に走ろうぜ、というような誘いをかけてくる。
ぼくはフェンスの外側で、その子に合わせて走り出す。
彼は興奮して、吠えながら走る。
あ、やりすぎちゃったかな、とぼくは反省してクールダウンを促す。
その子は楽しそうだった。
確かにうれしそうな顔をしていた。
臆することは、なにもない。

ピースワンコ・ジャパンの塩田さんが、障がいを持っている子を紹介してくれた。
シェルターにはもちろんそういう子もいるし、老犬も、病気の子もいる。
はたしてそんな子たちに、里親は見つかるのだろうか。
健康ではない、と言えてしまう子に、幸せな未来はやってくるのか。
「ピースワンコ・ジャパンには、『ファミリーサポート制度』 というものがあります。
これは、そういう身体的な理由により生涯シェルターで過ごす可能性が高い犬たちを、
きちんと里親さんへ届ける制度なんです。
ファミリーサポート対象犬を迎えてくださった里親に対し、
年間治療費のうち上限50万円をピースワンコ・ジャパンが負担。
その犬の状態により、『治療費』『投薬費用』『療法食代』における団体の負担内容を決定します。
お世話の大変さや投薬の量など、その都度獣医師の診断内容をもとに検討して、
サポートの内容を変更するという、なかなか手厚いサポートなんです」
塩田さんは、そう解説してくれた。
それはきちんと現実に則している話だとぼくは思った。
そこまでする保護団体はほとんどないだろうし、救われづらい犬たちが「制度」によって救われるというのは、
この先の保護活動へのワンステップにもなるのではないか。
まずはこの子たちに寄り添ってみよう。
彼らがしっぽを振ってくれるのを見て、喜びを感じよう。
生涯の友を引き取って、あなたも幸せになったらいい。
けれども、里親になれなくても犬たちを救うことはできる。
臆することは、なにもない。
彼らはかわいそうな存在ではない

「ねえ、遊ぶ?」
たくさんの犬たちがそう言っていたと感じる、晴れた午後。
彼らはやっぱり、かわいそうな存在ではない。
もっと強くて、生き抜くことを知っている「実体」なのだ。
ぼくはそのひとりの子に、手をのばした。
その子に触れて、ぼく自身のことを、考えること。
その思考を、ちゃんと彼らを救うすべにつなげること。
想像力で経験不足を補い、いくばくかの存在になること。
手をのばして、その子にぺろん、と指先を舐められたとき、ぼくはなにか肯定された気持ちになった。
それだけでぼくは、うれしくなったのだ。
某ペット雑誌の編集長。犬たちのことを考えれば考えるほど、わりと正しく生きられそう…なんて思う、
ペットメディアにかかわってだいぶ経つ犬メロおじさんです。 ようするに犬にメロメロで、
どんな子もかわいいよねーという話をたくさんしたいだけなのかもしれない。