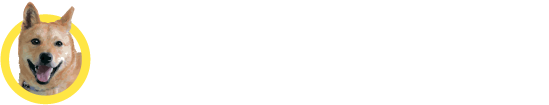子犬と目が合って

前からやってくるあの白い犬、どうやらまだ子犬のようだ。
ころころと丸っこい生きものは、愛嬌をあちこちに振りまきながら、世界中に興味があるような素振りで歩いてくる。
なんとなく目が合って、この人はぼくが好きだろうか、みたいな視線を勝手に感じる。
ぼくはその子犬に小さく手を振った。
飼い主さんは気づいていないようで、ちょっと背徳感。
犬は、霊長類以外では、人間の目を見つめる唯一の動物らしい。
これはオオカミを家畜化する研究において発見された、人間と犬との独特の行為。
人間とのアイコンタクトは求めるが、犬同士ではしないのだから。
ちょっとおもしろいな、と思う。
ころころした子犬が、すでに人間のことを知ろうとしているなんて、犬と人の関係の深さ、その歴史を想像してしまう。
子犬はいずれ成犬になる。
身体的に成長するのは人間でも同じことだが、犬は驚異的なスピードでその成長ぶりをぼくらに見せてくれる。
たくましく、活き活きと、充実した日々を過ごす。
その時間経過とともに、たのしい思い出がぼくらの心に焼き付くようにひろがっていく。
奮発してどこかに旅行したことより、毎日のなんでもない生活が思い出されるのは、どうしてなんだろう。
老犬が気づかせてくれること

成犬はついに老犬になった。
白髪が目立ち、足腰が弱くなり、公園に行く前のあの階段も、ゆっくりゆっくり上ることになる。
若いときはこんな階段なんて走り抜けていたのに。
そしてある日、ぼくは気づく。
この幸福な日々が、かならず終わりを迎えるという事実に。
それは遠くない未来なのだろう。
老犬は、そういうことに気づかせてくれる。
いいことなのかどうかは、まだわからないでいる。
犬たちは人間が好き

保護された犬たちのことを考えてみようか。
子犬のころから野犬になって、命からがら生き延び、ようやく保護されたけれどまったく人間に慣れていない子もいるだろう。
人間と暮らしていたが、ある日突然山の中に置き去りにされた老犬もいるはずだ。
人のやさしさにまったく触れずに生きてきて、この先わかりあえるものだろうか。
あるいは、人のやさしさに触れてきたのに、いきなり裏切られて、恨みを持たないものなのか。
ねえ、どっちがましだと思う?
いや、そういうことを言いたいわけではない。
犬たちはそれでも人のことが好きだ。
子犬も、老犬も、どんな犬もみんな人間のことが大好きなのだった。
じっと見つめてくれるほどに。
文明の最初のきざし

文化人類学者のマーガレット・ミードは、古代文化における文明の最初のきざしは「大腿骨が折れて治った人間の証拠にある」と言った。
動物界では、足の骨が折れてしまったら死ぬほかない。
危険から逃げることも、水場に行くことも、食料を調達することもできないのだから。
足を骨折して、それが治癒するまで生き残れる動物はいない。
だから折れた大腿骨が治った、というのはもちろん自然によくなったわけではない。
倒れた者に寄り添い、安全な場所を確保し、回復するまで面倒をみた誰かがいた、ということである。
その証拠が大腿骨に残されていた、と。
困難に陥った者を助ける。
これが文明の第一歩なのだとしたら、文明人であるはずのぼくらが失ったものとはなんだろう?
それとも、同胞である人のことを愛するのは簡単で、犬のことを大切に思うのは、むずかしいというわけだろうか。
可愛い者たちを愛でる

うちの子は、このあいだまで子犬だった。
そしていつの間にか老犬になっていた。
たのしい日々は続いた。
ある日、その日常は終わり、部屋ががらんとしてしまった。
ベッドも片づけたし、大好きだったおもちゃも、音を立てて舐めまわしていた白いフードボウルも、大量の専用タオルも、なくなった。
ぼくはむしろ、いま凍えているであろう保護犬たちを思った。
彼らとうちの子が決定的に違うのは、こういうことだ。
子犬から老犬になるまで、愛する誰かとずっと一緒にいる経験。
寄り添い、安全な場所を確保し、面倒をみてくれる存在。
それでも、遅くはないんだ、とあらためて思う。
少し欠けてもいい、幸福は量の問題ではない、その質が大事なんだと。
子犬はいずれ老犬になる。
だったらあなたの腕の中では、老犬が子犬になることもあるだろう。
あの可愛い者たちを、どんなふうに愛でていこうか。
老犬を迎え入れる

ピースワンコ・ジャパンには、「ファミリーサポート制度」がある。
老犬・病犬・障害犬など医療ケアがかかせない保護犬を迎えた里親に対し、医療費や療法食代など飼育費用の一部を負担してくれる、というものだ。
里親になる選択肢のひとつとして、大いに検討してほしい。
老犬を迎え入れる、なんて最高にクールだし、命の選別をしない、というコンセプトに乗っかってもいいじゃないか。
あなたの腕の中で子犬みたいに甘える老犬。
写真を撮って、ぼくに送ってくれませんか。
「悪くない」

さて、前から歩いてくるのはどうやら年老いた犬のようだ。
おぼつかない足どりで、それでも一生懸命に歩く。
彼はぼくの視線に気づき、こう言うだろう。
「悪くない」
なるほど、それが老犬たちを代表する言葉なのだとしたら、それこそ悪くない。
そこに一般の犬と保護犬の違いはないからだ。
人生をまっとうする準備ができている証拠。
もちろんこれはぼくの願望であって、意味じゃない。
けれども、そう解釈することで動き出す理由にもなる。
誰かをしあわせにする、と決意すること。
この暗闇が、かがやく星たちのためにあるのだとしたら、きっと救いはある。
あなたがそう思うなら、変えていこう、愛する犬たちと見つめあいながら。
某ペット雑誌の編集長。犬たちのことを考えれば考えるほど、わりと正しく生きられそう…なんて思う、
ペットメディアにかかわってだいぶ経つ犬メロおじさんです。 ようするに犬にメロメロで、
どんな子もかわいいよねーという話をたくさんしたいだけなのかもしれない。