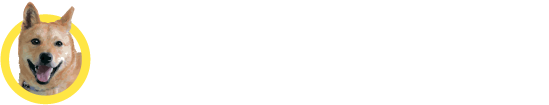その犬種はわからない

斜めの日差しを浴びて、犬らしい犬が歩いている。
その犬種はわからない。
逆光のせいもあるかもしれないが、それだけではない。
名前もなく、ただその個性と美しいシルエットがあるばかり。
山の中をざくざくと歩いていたと思ったら、痩せてはいるがその強靱なばねを持つ後ろ脚を使って、
地面を蹴り飛ばす。
走り出したのだ。
勝手なカテゴライズ

「純血種と呼ばれる犬たちがいますよね。当然のことですが、
彼らももともとは雑種犬から選択交配を繰り返して作られたわけです」
彼女はそう言った。
西日がまぶしい森の中で、キャップを被り直し、歩き出す。
「すべては人間の勝手なカテゴライズというわけですね」
ぼくはいかにもあっさりとした口調で言った。
「でも、それがすべて悪いことばかりともいえません。人間が犬を救っている事実は厳然としてあります。
もちろん逆もあるけれど。つまり、名前をつけるのは、よくも悪くも人間らしい行為なんじゃないかなと」
「…名前をつける」
ぼくはおうむ返しにそうつぶやく。
彼女はこの深い森の中で、思考しつつ散歩をしている。
空気は澄んでいるが、草いきれのにおい、熟したような土の香り、鬱蒼とした森の風景がひろがっていた。
雑種の魅力

「野犬と呼ばれる犬たちは、いわゆる雑種犬が多いわけですよね。
その子たちを保護して、心ある人たちに引き取ってもらう。
正直、雑種じゃなくて純血種だったらもっと引き取り手が多くなるかもしれない…なんて考えたりしませんか」
少し意地の悪い質問かな、とぼくは思いつつ、彼女に問いかける。
「そうかもしれないけど、そこに意味はありません」
森の中の彼女は足を止めずに、はっきりとした口調でそう言った。
間髪入れず少しけわしい表情で話を続ける。
「人間は、生きものをデザインできると思っているのでしょうか。
純血種という概念をつくり出して、新しい動物をクリエイトした、とでも?」
「そんな奢った考えかたではないと思うけれど…純血種というのは犬種ではなく、概念だと思うのですか?」
彼女は少し笑ったように見えたが、その横顔は逆光で滲んでいて、よくわからない。
「ぼくは、雑種犬は魅力的だと思っています」
前置きのようにそう言うと、彼女は足を止めた。
「…どこらへんが?」
「たとえば、唯一無二の個体」
「…なるほど」
「人間の意図に関係なく生まれた個体。目的に応じてつくられたわけではなく、自然そのものの存在。
体格も性格も、その子にしかないオンリーワン」
彼女は耳を立ててその台詞を聞いているように見えたが、視線を合わせようとはしなかった。
「でも、野良犬のイメージがあるじゃないですか、雑種って。あんまり上等じゃないというか」
「そんなことないと思うけど」
「いいえ、だって飼い主にさえ、捨てられちゃうんだから」
大きく一歩を

ぼくは彼女が放ったその言葉を聞いて、喋り過ぎたかな、と思った。
「あんなに大好きだった飼い主なのに、信頼していたのに。夜も明けていない暗い森に、置き去りにされた。
雑種なんて売れないし、価値がないって言ってた。…どうしてなの?
価値がないと思われた犬は、生きていちゃいけないの?」
ぼくは黙っていたが、なにかを絞り出して言おうとして、さらに口ごもる。
「どうせ引き取ってくれる人だって、タダだから、みたいな理由が多いんだと思うんです。
無料なら飼ってやるか、番犬くらいにはなるだろう、って」
そんなことはない、とぼくは一言だけ発した。
そんなことはない、人間にもっと期待してほしい、最初の飼い主がひどい人でも、
次のパートナーはきっとすばらしい人だ、そこにはちゃんと根拠がある、保護犬を迎えるために足を運ぶような人は意識も高いし、
知的だし、なんといっても愛情深い人なんだ——。
でもなぜか、声が出なかった。
それでも彼女には、ぼくの声が届くような気がしていた。
落ちかけた日差しは彼女の全体のシルエットを美しく照らし出し、細いからだが、透き通って見えるようだった。
目が合うと、かすかな笑みを浮かべて、言葉が降りてくるのを待っている。
「わかります。信じることにします」
彼女はそう言って、この森で培った強い筋肉を使うように、踵を返し、大きく一歩を踏み出した。
この森で培ったものがあるのなら、無駄だったことなど、なにひとつない。
ぼくはそう思った。
粗にして野だが卑ではない

そこで目が覚める。
そういう夢オチはありなのか、と自分でも思うが、なにせ雑種であるぼくだから、個性派なのだ。
純血種は純血種なりの、人間とともに生き、寄り添える生きかたを模索していけばよい。
もちろん否定なんてしない。
雑種は、粗にして野だが卑ではない、を地でいけばいい。
これは野犬のままでいろ、という意味ではない。
個体の個性を尊重してくれる飼い主と出会い、媚びずに生きるのだ。
やさしさを知れば、強くなる。
犬も、人間も同じこと。
期せずして、あの森で手に入れたものは、これからの人生に役立つに違いない。
某ペット雑誌の編集長。犬たちのことを考えれば考えるほど、わりと正しく生きられそう…なんて思う、
ペットメディアにかかわってだいぶ経つ犬メロおじさんです。 ようするに犬にメロメロで、
どんな子もかわいいよねーという話をたくさんしたいだけなのかもしれない。