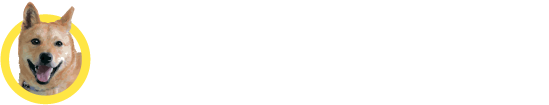テラスの老人

その老人はテラスに座り、誰かを待っているようだった。
ひとりきりで、手はテーブルの上で組まれている。
時折横切る犬の散歩の人たちがいて、うれしそうに歩くその子たちを見てにっこりする。
間違いなく犬好きだろうが、彼の足もとに犬はいなかった。
ぼくは愛犬のエルモを連れて、その老人の横を通ろうとした。
なんとなく彼と目が合って、ぼくは会釈をしてそのまま通りすぎようとしたが、エルモが彼の足もとで立ちどまった。
「こんにちは」
その老人はエルモにやさしい顔で話しかけた。
犬が好き

「かわいいなあ、ミックスの子ですか?」
老人が言った。
「はい、いわゆる雑種です」
「丈夫そうでいいですね。ビーグルの血も少し入ってるみたいだ」
「お詳しいですね。犬は飼ってらっしゃらないんですか?」
ぼくは何気なくきいた。
「ええ。以前は飼っていたんですよ。今までに5頭、見送ってきました」
「へえ、いいですね。これからのご予定は?」
「予定? 今日のですか? デートでもしますか」
そこでその老人とぼくは笑いあった。
自分で終わりを決める

「いやいや失礼。これからまた犬を飼うかってことですよね。結論からいうとNOです」
「そうなんですか。なにか理由が? いや、ごめんなさい、こんなにエルモが懐くのもめずらしいと思って」
エルモはその老人に撫でられてご機嫌だ。
「ふふ、まあ歳も歳ですから、もう犬とは暮らせないかな。ぼくが先に逝って、犬だけ残されちゃうのもね。ぼくには家族がいないし、そうなるとさすがにね」
老人はそういって、すこしだけさみしそうな顔をした。
いや、さみしそう、というのはぼくからの印象にすぎない。
その表情には実はやりきった満足感のようなものもあった気がする。 自分で終わりを決める、もう戻ることはない、というのはどんな気分なのだろう。
運命の再会

「いまでもあの子たちに会いたいなあ、なんて思うんですよ。いい歳をしてね。マヌー、ジャコ、桜丸、ケイト、エルモ」
ぼくはびっくりしてつい声が出てしまった。
「エルモ! この子はエルモっていうんです」
老人も驚いた顔をして、へえ、エルモ!偶然ですね、と言った。
「ひさしぶりだね、エルモ」
彼はとてもうれしそうに、エルモの背中を撫でた。
これは運命の再会というのだろうか。
最後の犬について

ぼくはその老人と犬たちのことについて話をした。
なぜかとても話が合って、たのしい時間だったが、彼の明るい性格が成せるものに違いなかった。
好奇心が強くて、パワフルで、よく笑う。
犬のような人、というと語弊があるかもしれないが、そんな感じだ。
もしかしたらぼくもそう思われているのかもしれないが。
(この前よく行くコンビニで店員がぼくのことを『犬の人』と呼んでいるのを知ってしまった)
「いやあ、犬はいい。どんな子もかわいい」
老人はそう言うと、満足そうにうなずいた。
「よけいなことかもしれないですが、また犬と暮らしてみてもいいんじゃないでしょうか。最後の犬です」
「最後の犬」
老人は何気なくぼくの台詞を繰り返した。
「そうです、まさに最後の犬と暮らすんです。その子の命をまっとうさせるのが飼い主の役目だけれども、それによってぼくらも力強く生きられる。その子がいるから、がんばれる」
ぼくらは犬の人

その老人と再会したのは、ちょうど半年後のことだった。
近くの公園でエルモの散歩をしていたときに、前から見覚えのある姿がやってきて、立ちどまった。
「やあ!」
老人は大きな雑種犬を連れていて、自分がその子に引っ張られているようすをコミカルに演じてみせた。
「もしかして…」
「そう、やっぱり犬と暮らしたくてね。保護犬を迎えたんだ。こんなぼくでも少しは役立ちたいなと思ってさ」
彼はそう言って、とってもチャーミングにウィンクをした。
こんな時代だから、この先だって犬と暮らすことが『推奨』されるとは思えない。
だが、ぼくらは犬の人だ。
犬と出会い、たくさんのことを学び、動物を愛する気持ちを手に入れた。
これだけは譲れない。
人間の子どもたちがぼくらの横を通りすぎていく。
とても楽しそうに、歓声をあげている。
犬だってそれでいい。
保護犬も、そうじゃない子も、区別などなく楽しんでほしい。
いずれぼくも、最後の犬に出会うのだろうか。
文と写真:秋月信彦
某ペット雑誌の編集長。犬たちのことを考えれば考えるほど、わりと正しく生きられそう…なんて思う、
ペットメディアにかかわってだいぶ経つ犬メロおじさんです。 ようするに犬にメロメロで、
どんな子もかわいいよねーという話をたくさんしたいだけなのかもしれない。
▽ ワンコを幸せにするために「ワンだふるサポーター」でご支援お願いします。▽
[no_toc]