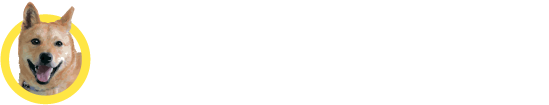家庭という小さな宇宙に宿る自然

犬は、家の中で暮らしながらも「外」の世界を持ち込む存在だ。
散歩から帰るたびに、風の匂いや草の種をまとってやってくる犬は、家庭に自然の断片を運んでくる。
外で拾った小さな枯葉や、鼻に残る土の香り。
犬の体についたそれらは、家という人工的な空間に自然の息吹をもたらし、それがどれほど新鮮で豊かなものかを気づかせてくれるわけだ。
一方、子どもは犬という「動く自然」に触れることで、自分の身近な環境を新しい目で見るようになる。
犬と一緒に草むらを探検したり、季節ごとの変化を感じたりすることで、子どもたちは「自然の一部としての自分」に気づき始める。現代の家庭がテクノロジーと効率性に彩られる中で、このような自然との触れ合いは、子どもの感受性を豊かにしてくれるはずだし、なんといっても生きものへの思い、みたいなものが芽生えてくるんじゃないか。
(つまり家庭円満はなによりも大事、ということなのかも)
自然のピュアさと、それに救われる人間

犬と子どもが家庭に呼び込む「自然」とは、単に外の世界から持ち込まれる風景や匂いだけではないだろう。
それはもっと本質的な、生きものとしての「ありのまま」の姿だ。
犬が無心に水を飲む姿、うとうとと眠りに落ちる瞬間、耳をぴんと立てて音に反応する動き。
その一つひとつには、自然のリズムに従う生き物としての美しさがある。
そしてその美しさは、人間が無意識のうちに抱える疲れや焦燥感を溶かしてくれるようだ。
そこに貴賎はない。
保護犬も野犬も、ペットショップでうずくまる子犬も。
現代の人間はしばしば、自分を取り巻く環境を管理し、制御しようとする。
しかし、犬や子どもと触れ合う中で、人間は自然の流れに身を委ねることの心地よさを思い出す。
たとえば、犬の散歩に出かけるとき。
最短距離を目指して早足で進もうとする人間をよそに、犬は立ち止まり、地面を嗅ぎ、気になるものをじっと見つめる。その様子を見ていると、「急がなくてもいい」「今この瞬間を楽しむことに価値がある」と気づかされるのだ。
「ただ存在すること」に喜びを見出す感覚

子どももまた、犬のその姿に感化される。
何かを「するために生きる」のではなく、「ただ存在すること」に喜びを見いだす感覚は、犬から子どもへ、そして子どもから大人へと伝播していく。
自然のピュアさは、言葉ではなく、こうした小さな行動や感覚の中で静かに広がるものなのだろう。
家庭という場所における「自然」の存在が、なぜこれほど人を癒すのか。
それは、自然が人間に「何者でもなくていい」という安らぎを与えてくれるからなのかもしれない、とぼくは思っている。
犬や子どもと過ごしているとき、誰も完璧を求めたりはしない。
犬は吠えるし、子どもは転ぶし、大人だってその不完全さに思わず笑ってしまう。
まったく、眩しくて、頼りない。
そこには、ありのままの姿を肯定し合う静かな共鳴が生まれる。自然のピュアさとは、まさにその「不完全さの美しさ」を指しているのではないだろうか。
犬がソファで丸くなり、子どもがその横で寝転び、穏やかな息遣いだけが響く夜の風景。
その空間には、人工的なものや効率性とは無縁の、静かで純粋なリズムが流れている。
家庭という小さな宇宙の中に生まれるその瞬間は、外の世界でどれだけ疲れていても、どこか救いを感じさせる特別な時間だ。
家庭に自然を取り戻すことの意味

犬と子どもがいる家庭は、人工的で便利なだけの場所にはならない。
それは、自然の持つ豊かさと不思議を感じることができる「小さな楽園」とでもいうべきもの。
家庭が楽園なのであれば、もはや怖いものはないのではないか、なんてことすら考える。
犬は外の自然を運び込み、子どもはその中で感性を育み、大人はその光景に癒される。
この循環の中で、家庭は単なる「生活の場」ではなく、命が息づき、互いに響き合う「生命の場」へと変わるだろう。
言い過ぎだろうか。
ここでもう一考したいところだが、本来はそうだったはずなのだ。
そもそも論をかざすまでもなく、生きていくために家庭は造られ、そこに犬がいた。
人間は、犬や子どもを通じて、自然そのものだけではなく、自然と調和する自分自身をも再発見する。
その過程で、急ぎすぎる歩みを緩め、失いかけていた感受性を取り戻していく。
自然のピュアさが持つ力は、ただ外界の一部を家庭に呼び込むだけではなく、人間の内面を深く癒し、救うものでもある。
子どもと犬がともにいる家庭――そこには、家庭という宇宙の中心で輝く、純粋な自然のエネルギーが宿る。
そしてそのエネルギーは、人間にとって失われがちな「自然とのつながり」をそっと思い出させ、穏やかな希望を灯す。
赤い首輪のトナカイ

クリスマスが近づくと、家の中が少しずつ忙しくなる。
ツリーを飾ったり、クッキーを焼いたり、プレゼントをこっそり用意したり。
けれど、うちの家族がいちばん楽しみにしているのは、毎年恒例の「サンタクロースの話」だ。
息子のカズキは、毎晩のようにサンタクロースについての話をせがんでくる。
愛犬リオもそばにやってきて、まるでお話をきかせて、というように寝そべる。
リオはカズキが4歳のクリスマスに「サンタさんからのプレゼント」としてやってきた、元保護犬のミックスだ。
その年、サンタクロースへのお手紙に「弟か妹をください」と書いたカズキに、リオは「特別なきょうだい」としてわが家にやってきたのだ。

カズキはリオを最初から「弟」と呼び、今でもそうしている。
リオが靴をかじって怒られると、「僕がちゃんと教えるから、ママは怒らないで」と本気で叱る。
逆に、カズキが風邪をひいて寝込むと、リオはずっとそのそばに寄り添っている。
見ていると、本当に兄弟のようで、わたしは毎日その光景に胸があたたかくなる。
そんなカズキには、小さな秘密がある。
彼はリオのことを「サンタさんの相棒、トナカイ」だと思っているのだ。
「だってリオ、赤い首輪してるでしょ? あれ、ルドルフみたいだもん!」
そう言って目を輝かせるカズキ。赤鼻のトナカイの歌詞を何度も歌いながら、リオの鼻先をじっと見つめ、「ほら、ちょっと赤い気がする!」なんて言い出す始末だ。

♪ 真っ赤なお鼻のトナカイさんは いつもみんなの笑いもの~ ♪
リオが得意げにカズキの顔を舐めるたびに、「ほらね、絶対ルドルフだ!」と笑う。
わたしはそのたびに「じゃあ、サンタさんがカズキの家に来たとき、どうしてリオを置いていったのかな?」と聞くけれど、カズキはにやっと笑うだけだ。
「それはね、リオがぼくの弟になるって決めたからだよ。きっとね、サンタさんの仕事を引き継ぐのを手伝ってくれるんだよ」
カズキは真剣な顔でそう話す。そして、ある日こんなことを言った。
「ぼく、大きくなったらサンタさんみたいになる。たくさんの子どもたちにプレゼントを届けて、みんなを笑顔にしてやる」
最後のデーモン閣下みたいな言いかたが気になったけれど、カズキの夢はとても純粋で、美しくて、あたたかい。
「…カズキなら、きっとみんなを笑顔にする素敵なサンタさんになれるよ」
そう答えると、彼は満足そうに頷いた。そして、「ぼくがサンタさんになるときは、リオも絶対一緒だからね」と言って、リオの首をやさしく抱きしめた。リオもまるで「もちろんさ」と言うように、しっぽをぶんぶん振って答えている。

その年のクリスマス・イブ、カズキはリオと一緒にサンタさんへのクッキーをテーブルに置いた。そして、「リオがトナカイに戻らないように、この首輪を絶対外しちゃだめだよ」と私に真剣に言い残し、眠りについた。
深夜、プレゼントをこっそり置きに行ったとき、私はリオの寝顔を見てふと思った。
もしもリオが本当にサンタクロースのトナカイだったら、どんなに素敵だろう。
いや、もしかすると、彼の正体は誰にもわからないし、この世界の秘密の一部分かもしれないのだ。
だって、リオがこの家に来てから、私たち家族がどれだけ笑顔になれたかを考えると、彼は間違いなく私たちにとっての「奇跡」なのだから。
次の朝、カズキは目を輝かせながらプレゼントを抱きしめた。そして、リオの耳元でささやく。
「ありがとう、リオ。やっぱりきみはトナカイだよね」
リオはしっぽを振りながら、カズキに寄り添う。
彼らがまとう、あたたかい空気は、私たちの小さな家をまるで魔法のように包み込んでいる。
じゃあ、やっぱり…。
クリスマスに奇跡は起きる。
リオの赤い首輪は、革が擦れてぴかぴか光っていた。
文と写真:秋月信彦
某ペット雑誌の編集長。犬たちのことを考えれば考えるほど、わりと正しく生きられそう…なんて思う、
ペットメディアにかかわってだいぶ経つ犬メロおじさんです。 ようするに犬にメロメロで、
どんな子もかわいいよねーという話をたくさんしたいだけなのかもしれない。