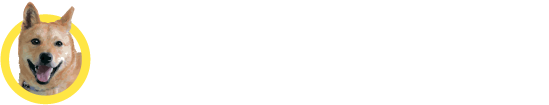クッシング症候群は、内分泌系疾患(ホルモンに関連した病気)の中で発生する割合が高い病気です。中高齢の犬に多く、原因が下垂体にあるか副腎にあるかで、治療法は異なります。
クッシング症候群の治療はいくつかの選択肢がありますが、ご自宅での投薬がメインになることが多く、飼い主が病気のことをしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、クッシング症候群の原因や症状、治療法、おうちでの投薬、食事などの管理のポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。
クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)とは
クッシング症候群は、副腎皮質からホルモンが過剰に分泌されることにより異常が現れる病気です。
副腎の位置と働き

副腎は、左右の腎臓の内側に1つずつ位置しています。副腎の構造は、中央部分の副腎髄質と周囲の副腎皮質の2つの部位に分かれていて、副腎皮質からは3種類、副腎髄質からは2種類のホルモンが生成されます。
副腎皮質から分泌される3つのホルモン
- コルチゾール
- アルドステロン
- 性ホルモン
のなかで、クッシング症候群に関わるのはコルチゾールです。
コルチゾールは、体にストレスがかかると分泌され、全身のさまざまな器官に働きかけ代謝を調節します。また、体に細菌やウイルスが入ったときや、ケガをしたときなどに起こる炎症を抑える働きもあり、この働きを使った薬がステロイド薬です。
クッシング症候群の原因

副腎皮質からのコルチゾールの分泌は、脳にある下垂体から分泌される副腎皮質刺激ホルモンで調節されています。そのため、クッシング症候群でコルチゾールが異常に分泌される原因には、
- 下垂体が原因の場合(下垂体性クッシング症候群)
- 副腎が原因の場合(副腎性クッシング症候群)
の2パターンがあります。
下垂体性クッシング症候群
下垂体から副腎皮質刺激ホルモンがずっと大量に出続けて、命令を受けた副腎皮質がコルチゾールを作り続けてしまいます。この場合、下垂体の腫瘍や、コルチゾールが過剰に分泌されることにより、下垂体自体が腫れたように大きくなります。
下垂体が1cmを超えるほど大きくなると、腫瘍が脳の別の部位を圧迫することで、ふらつきや発作などの神経症状を示すこともあります。犬のクッシング症候群では、約9割がこの下垂体性クッシング症候群に当てはまります。
副腎性クッシング症候群
副腎の腫瘍により副腎の細胞が増え、コルチゾールがどんどん作られている状態です。腫瘍が良性の場合、外科的に切除することで完治する可能性が高いです。
医原性クッシング症候群もある
アトピー性皮膚炎など別の病気の治療で長期間大量にステロイド薬を使っていると、クッシング症候群を引き起こすことがあります。このケースでは、獣医師と相談しながら薬の使い方や量を見直していきます。
クッシング症候群の症状

クッシング症候群になると、主に以下のような症状が現れます。
- 多飲多尿
- 食欲亢進
- 筋肉量の低下
- 腹部膨満
- 肝臓の腫大
- 皮膚症状(両側性脱毛、石灰沈着、色素沈着、皮膚炎、菲薄化など)
- パンティング(あえぎ呼吸)
このなかでも、飼い主が見極めやすい3つの症状について詳しくみていきましょう。
外見:おなかだけがぽっこりする
クッシング症候群の犬は食欲が増すので、体重が増加します。しかし、筋肉が落ちていくため、お腹周りだけが垂れ下がったり、肝臓の腫大でおなかだけがぽっこりと目立つような外見になったりします。
皮膚症状:脱毛、変色など
クッシング症候群の皮膚症状を解説します。
両側性脱毛
左右対称に同じ部位が脱毛します。一般的にかゆみはありません。クッシング症候群以外にも、甲状腺機能低下症などホルモンの病気で出ることの多い症状です。
石灰沈着
皮膚の表面にカルシウム塩などが沈着し、ゴツゴツした触り心地になります。石灰沈着は、糖尿病や腎臓病、ケガ、皮膚病など、さまざまな原因で起こります。
色素沈着
皮膚の一部が黒っぽく変色する症状です。甲状腺の病気、アトピー性皮膚炎、細菌や真菌などの感染、腫瘍などさまざまな病気でみられることがあります。
菲薄化(ひはくか)
皮膚の表皮や真皮が薄くなります。皮膚は乾燥してバリア機能も弱くなるので、表面がシワシワして血管が見えやすくなり、炎症も起こしやすくなります。
パンティング
犬が運動した後などに舌を出してハッハッハと荒い呼吸をすることをパンティングといいますが、クッシング症候群の犬は普段からパンティングをすることがあります。
クッシング症候群の検査法
クッシング症候群の診断には、以下の検査を行います。
- 身体検査
- 血液検査
- 画像検査
身体検査

外見やパンティングの有無、皮膚病変の有無を獣医師が確認します。
血液検査

クッシング症候群では、肝臓の異常でみられる数値(ALP)の上昇や、コレステロールの上昇がみられます。
確定診断では、ACTH刺激試験をおこない、下垂体から分泌される副腎皮質刺激ホルモンを注射し、副腎がどのように反応するかを採血して調べます。次に、下垂体性か、副腎性かを検査で調べます。
画像検査

健康な犬の副腎は小型犬で3〜5mm、中型犬や大型犬でも5〜8mmと、とても小さいサイズのためエコーで見つけられないこともあります。クッシング症候群になると、下垂体性では両側の副腎が腫大し、副腎性では片側だけ腫大していることが多いです。また、多くのケースで肝臓の腫大も確認されます。
下垂体性クッシング症候群では、頭部のCT検査で下垂体の腫大が観察されます。
クッシング症候群の治療法
クッシング症候群の治療は、下垂体性か、副腎性かによって治療方法が異なりますが、大きくは以下の3つの治療方法があります。
- 内科療法
- 放射線療法
- 外科手術
内科療法
大きさが1cmに満たない下垂体腫瘍や、犬の年齢、腫瘍の悪性度から放射線治療や手術などの選択ができないケースで適用になります。コルチゾールの働きを抑える薬を、生涯飲み続けることになります。
放射線療法
下垂体腫瘍の大きさが1cmを超えるケースで適用され、放射線治療で下垂体腫瘍を小さくする方法です。この治療ができる設備を持つ病院は限られているので、二次診療施設への転院が必要です。
外科手術
巨大な下垂体腫瘍は手術で摘出する方法もありますが、難易度は高いです。また、下垂体を取り除いてしまうので一生涯、薬でホルモンを補充していく必要があります。
副腎腫瘍の場合は、外科手術で腫瘍を摘出する方法が第1の選択肢です。こちらも、残ったもう一方の副腎の働きが悪ければ一生涯薬でホルモンを補充していきます。
クッシング症候群の自宅管理・注意点

クッシング症候群は、投薬を正しく続けていれば寿命を全うできる病気です。ご自宅での管理で気をつけることをまとめました。
投薬を自己判断でやめたりしない
クッシング症候群で使用する薬は、ホルモンの分泌を抑える薬です。クッシング症候群自体を治すための薬ではないので、症状が落ち着いていても薬を勝手にやめたり、量を変更したりしないようにしてください。
薬の副作用に注意
薬の量は、各種の検査結果によって獣医師が判断していますが、あまりに薬が効きすぎてしまうと副腎の働きが悪くなり、クッシング症候群とは逆の病態であるアジソン病(副腎皮質機能低下症)になる可能性もあります。
元気がなかったり、食欲の減退や嘔吐・下痢などの消化器症状などの症状がみられたりする場合は、速やかに獣医師に相談しましょう。
体調管理
コルチゾールの働きを抑える薬を服用すると、免疫力が弱くなり、膀胱炎(ぼうこうえん)や皮膚病などの病気にかかりやすくなります。犬の全身、皮膚、健康状態を毎日よくチェックしましょう。
栄養管理
多飲・多食の症状が出るので、新鮮な水はいつでも飲めるようにし、肥満には気をつけましょう。クッシング症候群では、肝臓に異常が出ることも多く、胆汁がドロドロになる胆泥症(たんでいしょう)を引き起こすことも多いので、低脂肪のフードに変更するのもおすすめです。
まとめ
クッシング症候群の原因、症状、検査法、治療法、自宅管理について解説しました。
- クッシング症候群は副腎皮質からのコルチゾール分泌が過剰になることで起こる
- 多飲多尿、両側性脱毛などの皮膚症状、パンティングがみられる
- 原因が下垂体か、副腎かにより、治療法が異なるが、薬は生涯必要になることが多い
クッシング症候群は、正しく投薬や健康管理をおこなえば、寿命を全うできる病気です。この記事を通じてみなさんの病気への理解が深まっていただければ幸いです。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。