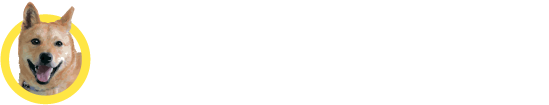骨折の可能性を感じたらやるべきこと

骨折は軽度の場合もあれば、場所によっては命に関わることもあります。骨折を疑ったら、愛犬を無理に動かしたりするのは非常に危険です。まずは冷静になり、以下の応急処置をしてみましょう。
応急処置の手順
①ケガの状態を確認する
まずは落ち着いて、出血部位やケガをしているところがないか、大きく腫れている箇所がないかを確認しましょう。いつもは穏やかな子でも、鋭い痛みを感じ攻撃的になることが少なくありません。過度に興奮させたり強く触わらず、様子を伺いながら確認してください。攻撃的になってしまう場合は、応急処置をおこなう必要はありません。
②骨折箇所を固定して痛みを和らげる
手足の骨折であれば、プラプラと動いているのがわかる場合もあります。そんなときは骨折箇所が動かないように優しく固定してあげましょう。
割り箸や木の枝を足の長さに合わせてカットして添木とし、骨折したところに添えてタオルやハンカチで優しく巻いてください。ただし嫌がったり、骨折が体に近い肩や太ももなど固定が不可能の場合などは、無理をする必要はありません。
③犬を動かさないようにする
キャリーケースの中に愛犬を入れて、隙間ができないように毛布やタオルなど柔らかい布を敷き詰めることでなるべく動かないようにします。
④起き上がれない子や大型犬は担架にのせる
抱きかかえられないほど重症な場合や、大型犬は移動が困難になります。大きなタオルの上に寝かし、端を数名で持ち上げるなど担架を作り、移動するのがおすすめです。
すぐに病院に連れていくべきケース
次の場合は、緊急を要する場合があります。急いで動物病院へ連れて行きましょう。
- 骨が皮膚を突き破っている場合
- 痛みが強く鳴いたり噛みつこうとする場合
- 出血が止まらない場合
- ぐったりしている場合
骨折を放置するとどうなる?
激しく痛がる様子がないからといって、骨折を疑う症状を放置してはいけません。万が一骨折していた場合は、骨が変形して歩けなくなってしまったり、長期間痛みが続いてしまうこともあります。また、骨折箇所から菌が感染したり臓器を損傷してしまうと、命に関わるため油断は禁物です。
骨折の主な症状と見分け方

骨折の症状は、損傷の部位や程度によってさまざまな形で現れます。
行動の異常
最も顕著な症状としては、急な行動の変化が挙げられます。普段は活発な愛犬が突然動きたがらなくなり、足をあげる場合は骨折の可能性があります。特に足の骨折の場合、患部を地面につけることを極端に避けて三本足で歩行したり、触ろうとすると激しく痛がる場合が多いです。また、骨折した部位周辺が腫れ上がり、熱を持つこともあります。
食欲や元気の低下
食欲や活力の低下も、骨折を示唆する重要な症状です。痛みによるストレスで、普段の食事量が激減したり、水も飲まなくなったりすることも多いです。
呼吸の変化
肋骨の骨折の場合は、息がしづらくなるため呼吸が早くなったり、不規則になったりすることがあります。また、肋骨を骨折した場合は、肺を損傷している可能性もあるため、異変に気づいたらすぐに動物病院を受診しましょう。
犬が骨折する主な原因

外傷によるもの
一般的な原因としては、室内での転倒やドアへの巻き込み、落下や交通事故が多く報告されています。たとえば、フローリングの床で滑って転倒したり、ソファやベッド、階段等から飛び降りる際に骨折したりするケースが多いようです。特に1歳未満や高齢犬は骨が細く脆弱なため、わずかな衝撃でも骨折につながりやすく、注意が必要です。
病気が関連する場合も
高齢犬は、基礎疾患による骨折リスクが高いです。カルシウム代謝異常や、骨のがんなどの疾患は、骨の強度を低下させ、わずかな衝撃でも骨折を引き起こす可能性があります。また、重度の歯周病では顎の骨が溶けて骨折してしまうこともあります。そのため普段の健康状態を日頃から把握し、早めに治療しておきましょう。
骨折しやすい犬種や年齢
トイプードルやポメラニアン、チワワなどの小型犬種は足の骨が細いため、手足を骨折しやすい傾向があります。ただ、四肢が細長い場合はどんな犬種でも足への衝撃が負担となりやすいため、注意が必要です。また成長期で骨が柔らかい子犬や、骨密度が低下して弱くなっている老犬も骨折のリスクが上がります。
骨折の診断方法

骨折の診断は、視診と触診で腫れや痛みの有無を確認するほか、レントゲン撮影をおこない骨折の状態を把握することで診断します。骨折の箇所によっては、専門病院でCTやMRI検査をおこなう場合もあります。
骨折の治療方法
骨折の治療は、部位や症状の程度、そして愛犬の年齢や全体的な健康状態によって、適切な方法が選択されます。内科治療から外科治療まで方法はさまざまで、その子の状態に合わせて組み合わせておこないます。
薬物療法
抗生物質を使用して菌の繁殖を抑えたり、消炎鎮痛剤により痛みを緩和します。場合によってはカルシウム剤や、脂肪酸製剤などのサプリメントも併用することもあります。
保存療法
比較的軽度の骨折や、手術リスクの高い高齢犬などに適用されます。この方法では、ギプスや副木による外部固定と、痛みのコントロールが主な治療となります。完全な治癒は期待しづらい場合もありますが、体に大きな負担をかけずに痛みを緩和することができます。
外科療法(手術)
より複雑な骨折の場合は、全身麻酔を用いた手術治療が必要となります。一般的な方法は、金属製のプレートやスクリュー(ネジ)という器具を用いて骨を内部で固定する方法です。また、開放骨折や粉砕骨折などより複雑な骨折の場合に選択される「創外固定術」という治療法や、細いピンやワイヤーを使用して骨を繋ぎ合わせる方法もあります。
手術を用いる方法では骨折部位を正確にもとの状態に戻すことができるので、より確実な治癒が期待できます。
ただし手術後は入院が必要で、体に入れた金属を取り出すために、複数回手術をおこなうこともあります。骨折箇所や状況に応じて、家族と相談しながらやり方を使い分けていきます。
骨折の治療期間
治療期間は手術を伴う場合、一般的に2〜3ヵ月を要します。ただ、完全に回復する期間は、年齢や症状によって変わるほか、個体差もあるため獣医師に確認しましょう。
骨折の治療にかかる費用
犬の骨折治療にかかる費用は、骨折の部位や程度、選択する治療法によって大きく異なります。ギプスや副木による外固定での治療は、特殊な器具や手術を必要としないため、数万〜10万円程度の場合が一般的です。
一方、手術治療をおこなう場合は、より高額な費用が必要となります。一般的な固定術の場合、手術費用だけでも20〜40万円ほどかかります。この費用には、麻酔料、手術材料費、入院費などが含まれます。特に金属プレートやスクリューなどの医療材料は高価で、使用する数や種類によっても費用が大きく変動します。
そのほか通院中の検査や診察費用、術後のリハビリの費用も必要となります。
手術せずに直す方法はある?

軽度の骨折やヒビ割れであれば、ギプス固定のみで治療が可能な場合もあります。ただし、一部の骨折に対してだけの適応で、場合によっては治癒期間が長引いたり完治が期待できないこともあります。
しかし近年では、前足の骨折に対して「3Dギブス治療」という新しい骨折治療も登場しています。これらは従来の治療と比べて犬にかかる負担が比較的軽い上に、完治が期待できる点が利点です。まずはかかりつけ医に相談してみましょう。
骨折を防ぐために飼い主ができること
愛犬の骨折を防ぐためには、日常生活での適切な予防対策が不可欠です。日頃のちょっとした意識で、愛犬を危険から守ることができます。
室内環境を整える
フローリングは犬にとって非常に滑りやすく、転倒してしまうと危険です。そのため愛犬の過ごす床には滑り止めマットを敷くことが効果的です。また、ソファや階段などの高い場所から犬が飛び降りないようにゲートや専用のスロープ、ステップを設置することも重要です。

適切な食事を心がける
栄養管理も骨折予防には欠かせません。特にカルシウムとビタミンDは、骨の健康維持に重要な栄養素です。総合栄養食のドッグフードを食べている場合は、栄養素は十分に含まれているため過剰に与える必要はありません。年齢や健康状態に応じた適切な栄養バランスを考えてあげましょう。

健康診断へ行こう
定期的な健康診断も大事な予防になります。骨や関節の問題は、健康診断で早期発見することが可能です。特に高齢犬の場合は、年に2回程度は健康診断を受けましょう。

日常的に運動する
適度な運動も骨を丈夫にする上で重要です。ただし、過度な運動は逆効果となる可能性があるため、子犬や高齢犬の場合は、その日の体調や気温に応じて運動量を調整することが大切です。散歩は1日2回程度、小型犬であれば15-30分程度を目安とし、徐々に運動量を増やしていくことをおすすめします。

愛犬の骨折を防ぎ安全な毎日を
骨折は確かに怖いものですが、日頃の小さな工夫や意識で事故を防ぐことができます。一度自宅を見渡してみて、愛犬がケガしやすい場所がないか探してみてください。些細な改善が愛犬の幸せな生活につながるはずです。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。