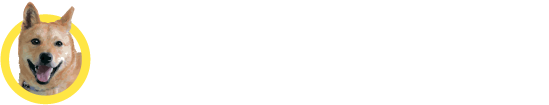『犬から見た世界 その目で耳で鼻で感じていること』

犬という動物を理解するために
さて、犬は人間の最も身近な動物の一つだが、ぼくらは本当に犬のことを理解しているのだろうか。
そんなことを思いながら、本棚に手を延ばしてみる。
『犬から見た世界 その目で耳で鼻で感じていること』(アレクサンドラ・ホロウィッツ・著 竹内和世・訳/白揚社)を手に取り、ぱらぱらと読み進める。
本書は、ソニーのAIBO製作にも協力した動物行動学者が、犬の知覚や行動を科学的に分析した研究書だ。
一般的な「犬のしつけ本」や「犬との暮らしを楽しくする本」とは異なり、犬を擬人化せず、徹底して「犬の目線」で世界を見ようとするアプローチが取られている。そのため、読みにくさを感じる部分もあったが、新しい発見にも満ちている。
視覚の人間、嗅覚の犬

本書の前半では、犬がどのように世界を認識しているのかについて、感覚器官ごとに詳しく解説されている。
人間は視覚を中心に世界を理解するが、犬は嗅覚を頼りに外界を把握しているということ。
たとえば、ぼくらは「目で」道の先に何があるかを確認するが、犬は「鼻で」そこに誰がいたのか、どのような匂いが残っているのかを読み取る。
この違いは非常に大きく、犬にとっての「散歩」とは単なる運動ではなく、「匂いを通じて世界を探索する行為」なのだという。
この話を読んで、ぼくは首を縦に振りまくる。
「早く歩かせなきゃ」と思っていたお散歩はナンセンス、犬にとっては道端の匂いを嗅ぐことこそが大切な時間なのだ。
もっと自由に匂いを嗅がせてあげればいい。
それだけのことなのに、犬の散歩となるといかに不自由な飼い主の多いことか。
「今」を生きる犬と、過去や未来を考える人間

本書で特に印象に残ったのは、「犬は人間よりも〝今〟を生きている」という点だった。
犬は閃光融合頻度が高いらしい。
閃光融合頻度とは、光の明滅や遮断を一定の頻度で反復したときに、ちらつきから融合して持続光のように見える境界値の頻度なのだそうだが、つまりは犬たちは人間よりも瞬間瞬間をより細かく感じ取っているのだ、と。
さらに、時間の流れを嗅覚で感じることができるため、人間とは異なる「時間の感覚」を持っている。
ぼくらが「今、目に見えるもの」を頼りに世界を理解するのに対し、犬は匂いの強弱から「ここに何があったのか」「どれくらい前の出来事なのか」を感じ取るという。
なるほど、これはおもしろい。
犬は単に「今」を生きているのではなく、ぼくらとは異なる方法で時間を感じ取っているのだ。
また、犬は過去の経験に縛られたり、未来を想像して不安になることが少ない。
人間はどうしても「過去の失敗を引きずる」「未来の不安に悩む」といった思考にとらわれがちだが、犬はそうではない。
彼らは「今この瞬間」に集中して生きている。
これはぼくらにとって学ぶべき点だろうし、誰だって日々の生活の中で「未来のことを考えて不安になる」ことが多いわけだが、犬のように「今を楽しむ」ことができたら、もっとシンプルに生きられるはずだ。
人間の「善意」は本当に犬のためか?

本書を読んで、ぼくらが犬に対して「良かれ」と思ってすることが、必ずしも犬にとって心地よいことではないのだとあらためて気づかされたことも。
特に印象に残ったのは、雨の日のレインコートの話だ。
ぼくらは「濡れるとかわいそう」と思い、犬にレインコートを着せることがあるが、犬にとっては背面から体を覆われることが「支配・被支配」の関係を想起させるため、むしろストレスになるという。
まあそれは極端な例かもしれないが、ぼくが興味深いと思ったのは、ものは使いよう、ということだ。
つまり、レインコートはそのまま使ったらストレスになるかもしれないが、逆に安心感を与えるようになにか工夫はできないか。
そんなふうに考えることが、犬との暮らしに役立つのは間違いない。
また、犬が「人間に頼ることを学ぶ」点についての話もおもしろかった。
著者は「犬と人間の関係は有史以前から続いており、犬は人間が自分を助けてくれることを知っている」と述べている。
飼い主なら誰もが覚えがあるはずだ。
愛犬がちらりとこちらを見て、なにかを求めている。
それは「人間に助けを求めれば反応してくれる」と学習した結果なのだろう。
ちなみに犬と幼児の行動が似ていることについても述べられており、犬も幼児も、自分でできることが限られるため、周囲の反応を見ながら「どうすれば助けてもらえるか」を学習していく、と。
このテーマも興味深いので、いずれ深堀りしてみたい。
読みにくさと翻訳の問題

本書はとても興味深い内容だったが、正直なところ、読みにくい部類の文章かもしれない。
論理的に書かれているが、翻訳の影響か文章が硬く、専門用語も多いため、すらすらと読み進めることが難しかった。
また、著者は「結論を決めつけない」姿勢で書いているため、「こういう結論です」とはっきり断言されるわけではなく、曖昧な部分も多い。
そのため、考えながら読む必要があり、単純に楽しむというよりも「学ぶ」感覚で読む本だった。
特に前半は犬の生態について細かく説明されているため、専門的な話が続き、退屈に感じる部分もあった。
しかし、後半では「犬の心」に関する話が増え、より身近なエピソードも出てくるため、個人的には後半のほうがおもしろく感じた。
特に「朝の大事な時間」という章では、犬と飼い主の日常的な関係性について述べられており、犬と暮らす人なら共感できる部分が多いと思う。
「犬の環世界を心に留めて擬人化する」というフレーズは、なかなかいい。
シンプルに犬のように考えることがあってもいい

本書は科学的に「犬の世界」を探求した一冊であり、犬をより深く理解したい人にとっては価値のある本だろう。
愛犬との散歩の時間を「ただの運動」と考えるのではなく、「犬にとっての大切な探索の時間」として大事にすること。
それは愛犬のためだけでなく、飼い主にとってもすばらしい人生の時間になり得る。
人間の価値観はそれぞれだというけれど、シンプルに犬のように考えることがあってもいい。
悩み抜いて未来を悲観することが人間らしさであるのなら、四つんばいになって愛犬にちょっかいをかけてみよう。
……また違った人生が開けるかもしれませんよ。
文と写真:秋月信彦
某ペット雑誌の編集長。犬たちのことを考えれば考えるほど、わりと正しく生きられそう…なんて思う、
ペットメディアにかかわってだいぶ経つ犬メロおじさんです。 ようするに犬にメロメロで、
どんな子もかわいいよねーという話をたくさんしたいだけなのかもしれない。
▽ ワンコを幸せにするために「ワンだふるサポーター」でご支援お願いします。▽