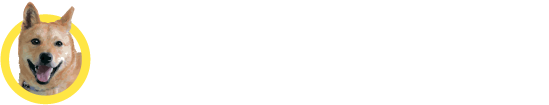「食後に愛犬の散歩に行くのは良くない?」そんな疑問を持ったことはありませんか?胃捻転は、食後の運動などがきっかけで起こりやすく、突然命を落とすこともある危険な病気です。この記事では、胃捻転の症状・原因から予防策に加えて、安全な運動の工夫についても紹介します。愛犬の命を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
食後の散歩は危険?胃捻転と運動の関係性

胃捻転は動物病院でも「緊急手術が必要な疾患」として知られており、数時間のうちに命を落とす可能性もある致命的な病気です。発症する原因や経緯に関していまだ完全には解明されていませんが、大量のフードの一気食いや過食、食後の運動およびストレスなどが危険因子であると報告されています。
食後すぐの散歩が危ない理由
食事の直後は、胃の中に大量のフードや空気、ガスが存在します。この状態で激しい運動をすると、ガスが大量に発生して胃が膨張し「胃拡張」という状態に陥りやすくなります。さらに胃がねじれる「捻転」が起きると胃壁の血流が止まり、内臓壊死やショック症状、最悪の場合には数時間以内の死亡という事態もありえます。そのため、食後すぐの激しい運動は高いリスクがあるため推奨されません。
室内でも過食や遊びすぎに要注意
室内でのジャンプや追いかけっこなどの激しい運動も、胃に大きな刺激を与えます。特にフードを勢いよく食べた後に急激に動くと、胃に入った空気や内容物が胃拡張を引き起こし、その後胃捻転へと進行するリスクが高くなるため、室内でも注意が必要です。
命に関わる危険な病気「胃捻転・胃拡張症候群」

胃捻転は、正式には「胃拡張・胃捻転症候群(GDV:Gastric Dilataion andVovulus)」と呼ばれます。胃が膨らみ(胃拡張)そのままねじれて(胃捻転)、血流が遮断されてしまう病態です。胃拡張だけであれば致死率は極端に低いとされていますが、胃捻転が起こると血管や胃壁が締めつけられて臓器への血流が止まり、内臓の壊死やショック状態に陥る危険性があります。
「胃拡張」と「胃捻転」の違い
「胃拡張」とは、胃の中に空気やガス、食物などが大量に溜まり、胃が膨らんでしまう状態です。胃拡張のみであれば、軽度なら自然に改善することもあります。「胃捻転」はその膨らんだ胃がねじれて元の位置に戻らなくなる状態です。放置すれば胃壁の壊死や血流遮断によるショック症状が起こる可能性があり、迅速な診断と処置が生死を分けるカギとなります。
発症から数時間で急死する場合も
胃捻転は進行が非常に早い病気ですが、運悪く夜間や診療時間外に発症し、来院が遅れてしまうケースもよくあります。病状が進行してからだと、緊急手術を行っても救命できなかったり、手術を行う前に亡くなってしまうこともあります。お腹が急激に張って苦しそうな様子を見せた場合は、迷わずすぐに病院へ連絡しましょう。
発症しやすい犬の特徴と生活習慣

胃捻転はどの犬にも起こる可能性がありますが、特に犬種や生活習慣によってリスクが高まります。ここでは発症リスクが高い犬の特徴と、日常の過ごし方で注意すべきポイントを紹介します。
大型犬以外に小型犬の発症も
大型犬に多いとされている胃捻転ですが、最近では小型犬でも発症が報告されています。特にミニチュアダックスやシーズーなどで報告があり、小型犬でも十分に注意が必要です。犬種に関係なく予防意識を持つ必要があります。
食後の運動や興奮は危険
胃捻転は食後の運動だけでなく、食後の興奮によっても発症リスクが高まります。食後に走り回ったりするだけでも、胃が急激に動き、内部にガスや空気が溜まって胃拡張が起こる可能性があります。食後はなるべく興奮させず、安静に過ごすことが重要です。
高齢犬・神経質・早食いは要注意
高齢犬は胃の運動機能が低下しやすく、胃捻転のリスクが高まりやすくなります。神経質でストレスを受けやすい状態や、食べ過ぎ、一気食い、さらに食後の大量の飲水も要注意です。毎日の散歩の時間が食後の場合や、1日1回の食事などの生活習慣はリスクを高めるため、改善しましょう。
胃捻転を疑うべき症状

胃捻転は何よりも家族の早期発見が命を救います。見逃してはいけない代表的な症状をおさえましょう。
発症は食後すぐとは限らない
胃捻転は「食後すぐに起こる」と思われがちですが、実際には食後数時間たってから発症するケースも多いです。食後に蓄積されたガスやフードが胃内で発酵・膨張し、何らかの刺激で突然ねじれ、胃捻転を引き起こす可能性があるためです。特に午後や夜間、静かにしていたはずの時間帯に突然苦しみだすこともあるため、食後数時間は注意深く観察しましょう。
よだれ、空嘔吐、腹部膨満は危険サイン
胃捻転の初期症状で多く見られるのが大量のよだれ、吐こうとして吐けない仕草、お腹の膨らみや腹部を痛がるといった症状が見られます。これらはいずれも胃に空気やガスが溜まり、出口が塞がれているサインで、すぐに動物病院で受診する必要があります。一刻を争うため、迷わず救急動物病院へご連絡のうえ、速やかに受診してください。
失神やぐったりしたらすぐに救急へ
胃捻転が進行すると、血流障害により胃や脾臓が壊死し始め、ショック症状を引き起こします。ぐったりして動かない、目がうつろ、倒れて意識を失う(失神)などが見られます。これは体内の血圧が急激に低下し、臓器に酸素が届かなくなっている状態で、命に関わる緊急事態です。数時間以内に死亡する可能性があるため、速やかに救急動物病院へ連絡・受診してください。
緊急時の対処法

万が一愛犬が胃捻転を起こしたかもしれないと思ったときに大切なのは、「ためらわない判断」と「迅速な行動」です。いざという時に備えて知っておきたいポイントを紹介します。
いざという時の応急処置
結論から言うと、胃捻転は自宅での応急処置では救命できません。放っておくと100%亡くなってしまいます。応急処置の基本は「移動中に安静を保ちつつ、最短時間で病院へ搬送すること」です。そのため車内ではできるだけ横向きで優しく寝かせ、激しい揺れを避けるようにしてブランケット等で体温低下を防ぎましょう。
胃拡張・胃捻転の治療

胃拡張のみの場合、胃内のガスを抜く減圧処置や点滴などで回復するケースもあります。しかし胃捻転を併発すると、ねじれた胃を元に戻し胃を腹壁に固定する緊急手術が必要です。症状の進行により脾臓の摘出が必要な場合もあります。
緊急時の動物病院の選び方
夜間や休日に発症する可能性もある胃捻転は、救急対応可能な動物病院の把握が重要です。事前にかかりつけ病院の夜間対応の有無や、夜間救急病院を確認し、行く病院を決めておきましょう。慌てないように連絡先と場所を控えておくことも忘れずに。
また、初診での受け入れ可否、レントゲンや血液検査から手術の即日対応が可能かどうかも選ぶ基準になります。普段から診療時間や緊急時の方針についてかかりつけの動物病院に確認しておくことが重要です。
胃捻転を予防するには

胃捻転は完全に防ぐことは難しい病気ですが、日常の食事・運動・生活習慣の見直しによって、リスクを大きく減らすことは可能です。今日から始められる行動ばかりですので、ぜひ習慣化を意識してみてください。
散歩は食前か食後3時間後が安心
食後すぐの散歩は胃捻転のリスクを高めます。そのため胃内にフードやガスがある状態での運動は推奨されません。理想的なのは「食前」に軽く散歩を済ませること、あるいは「食後3時間以上空けてから」運動をさせることです。特に大型犬や興奮しやすい子は、散歩のタイミングを意識的にずらすことで、危険性を大幅に下げられます。
食事は1日2〜3回に分ける
1回の食事量が多いと、胃に一気に負担がかかり、ガスの発生や胃の急激な膨張を招きやすくなります。そのため食事は1日2~3回に分けて与えることが好ましいでしょう。また、日々のフードも急激な発酵やガスの発生を起こしにくい消化に配慮したものを選ぶのがおすすめです。また、食後の大量の飲水はせずに、少しずつ飲ませるようにしてください。
早食い防止などグッズの活用

早食いは胃に空気を大量に取り込む原因となり、胃拡張を引き起こしやすくなります。そんなときは早食い防止用の器(ボウル)やフードディスペンサーなどのアイテムの活用が有効です。食事のスピードを自然に落とすことで、胃の急激な膨張を防ぎ、胃捻転の予防につながります。いろんな形状があるため、調べてみましょう。
大型犬は予防的な手術の選択肢も
再発を繰り返す場合や、胃捻転の家族歴がある場合には、「予防的な胃固定手術(胃腹壁固定術)」という選択肢もあります。これは胃がねじれないよう腹壁に部分的に胃を固定する外科処置で、特に大型犬や深い胸の犬種に対し検討される場合があります。すべての犬に必要というわけではありませんが、リスクが高いと判断された場合には、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。
日々の備えで愛犬を守ろう
胃捻転は発症すれば短時間で命に関わる病気ですが、日常の食事管理・運動習慣・家族の観察力を磨くことで、リスクを確実に下げることができます。大切なのは「うちの子は大丈夫」と思い込まずに、今できる備えを習慣にすることです。愛犬の命を守れるのは、飼い主であるあなたしかいません。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。