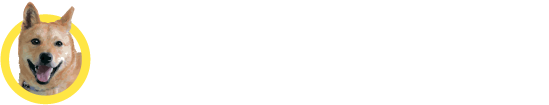フィラリア症は、犬の心臓や肺動脈に寄生虫が住みつくことで起こる病気です。突然死などの命に関わる症状を起こすこともありますが、正しく予防薬を使うことでほぼ100%の確率でフィラリア症の発症を防ぐことができます。
この記事では、初めて犬を飼う人にも分かりやすいように、フィラリア症とはどのような病気なのか、予防薬の種類や使い方、もしフィラリア症にかかってしまったときの症状や治療法を解説します。
フィラリア症は怖い病気ですが、飼い主が正しい知識を得て対策をとれば心配することはありません。一緒に学んでいきましょう。

犬のフィラリア症とはどんな病気?

犬フィラリア症は、フィラリア(犬糸状虫)という寄生虫が犬の心臓や肺動脈に住みつくことで血流を妨げたり、血管に障害を与えることによって起こります。フィラリアは、犬の体内で5〜7年生きると言われ、重症例では何十匹も成虫が寄生することもあります。
感染のサイクル
フィラリア症は、犬から犬へはうつりません。フィラリア症に感染している犬を吸血した蚊の体内にフィラリアの幼虫が入り、その蚊が別の犬を吸血したときに、幼虫が犬の体に入ることでフィラリア症に感染します。
犬の体に入った幼虫は移動しながら成長し、4~6ヵ月で成虫になり、大きいもので30cm以上になります。成虫になると繁殖し、またたくさんの子虫(ミクロフィラリア)を生みます。この犬が蚊に吸血されると、ほかの犬に感染がうつっていきます。
フィラリア症の症状
フィラリア症に感染したときの症状は、寄生数や寄生場所によって様々で、突然死するケースもあれば、フィラリア症にかかっていても無症状で長生きする犬もいます。
ここでは、一般的な初期症状と、進行したときに見られる症状を説明します。
初期症状
感染初期は、寄生数が少ないため、はっきりとした症状は出ません。症状が出る頃には感染から数年経っていることも多いです。
・乾いた咳
・痩せてくる
・食欲低下
・運動不耐性(散歩や運動を嫌がる)
・呼吸が速く、浅くなる
進行したときの症状
成虫が血管に住みつき血液の循環障害が起こると、肝臓や腎臓などの内臓にも影響が出はじめて、以下のような症状が出ます。
・腹水がたまり、お腹が膨らんでくる
・運動後の失神
・咳に血が混じる
・血色素尿(真っ赤~コーヒー色のおしっこ)
大静脈症候群を起こすと早急な治療が必要
成虫が本来の寄生部位である肺動脈から何らかの拍子に右心房や右心室に移動すると、大静脈症候群という危険な症状を引き起こします。心不全や貧血を起こしたり、血圧が低下して急激に体調が悪化することもあり、緊急手術で虫体を取り出すといった処置を行わないと多臓器不全で死んでしまうため、注意してください。
フィラリア症の予防薬の種類や使い方

フィラリア症は、蚊に刺されることでうつっていきますが、完全に蚊に刺されないようにするのは難しいことです。そのため、毎年、一定期間薬を服用するのが最も確実な予防方法です。
動物病院で取り扱っているフィラリア症の薬には大きく3つの種類があります。
・内服薬(錠剤、チュアブル錠)
・滴下薬
・注射薬
それぞれの薬の与え方と、その薬を使うメリットとデメリット、どの薬を選べばよいかを解説します。
内服薬(毎月1回)
錠剤は薬のバリエーションが豊富で、体に合わない成分の薬があっても別のものに変更することができます。月1回の投薬が必要です。
錠剤
昔からあるタイプの薬で、最も安価です。そのまま与えても気にせず食べてしまう犬もいれば、フードやおやつに混ぜ込まないと食べない犬もいます。
チュアブル錠タイプ

チュアブル錠とは、錠剤のひとつで、口のなかでかみ砕いて服用する薬のこと。肉などの原材料に薬を練りこみ、犬が好んで食べるように加工したおやつタイプの薬です。
注意点としては、原材料にアレルギーのある犬には使えないこと。また、犬が好きな味がついているため、犬の届くところにチュアブル錠を置いておくと盗み食いしてしまう可能性があるので、保管には気をつけましょう。
滴下薬(毎月1回)

「スポットタイプ」とも言われます。月1回、首の後ろの毛をかき分けて滴下します。飲み薬が苦手で、ほかの食べ物に混ぜても薬だけ吐き出してしまうような犬にもおすすめです。肌が弱い犬には、合わないこともあります。
注射薬(年1回)
上の2つと違って、動物病院での年1回の注射ですみます。注射液には、いろいろな成分が含まれているため、アレルギーの発生率が少し高いといわれているため、よく獣医師と相談してください。
フィラリア予防とほかの寄生虫駆除が同時にできる薬が人気
最近、フィラリアの予防と、ノミ・ダニなどの外部寄生虫、線虫や回虫など犬の消化管に住む内部寄生虫の駆除が同時にできるチュアブル錠も販売され、動物病院でも人気になっています。
ただし、8週未満の子犬や、1.8キロ未満の犬には用いない、妊娠授乳中の犬には避ける、などといった注意事項があります。どの予防薬がよいか、獣医と相談して選んでみるとよいでしょう。
いつからいつまで?フィラリア予防を投与する期間
内服薬や滴下薬を使うのは、基本的には蚊が出始めた1ヵ月後から、蚊を見かけなくなった1ヵ月後までです。
しかし、近年、蚊が出始める時期が早くなっていることから、薬を飲み始める時期を早めている病院や、通年の服薬を推奨している病院もあります。かかりつけの獣医師とよく相談してください。
予防薬を与えるときの注意点

フィラリア症の予防薬を飲ませるには、いくつかの注意点があります。
・春ごろに動物病院を受診し、事前検査を受ける
・毎月確実に飲ませる
・もらった薬は最後まで飲み切る
フィラリア症の予防薬は市販されておらず、動物病院で獣医師に処方してもらいます。春は狂犬病ワクチンの予防接種の時期と重なり、動物病院がとても混むため、余裕をもって動物病院に行きましょう。
①事前検査を受ける
薬をもらう前には、血液検査をして現段階でフィラリアに感染していないかを調べなければいけません。もしすでに犬の体内に幼虫がいた場合、薬を投与することで幼虫が一気に死んで血管に詰まったり、アレルギーによるショックを起こしたりする可能性があるためです。
②毎月確実に与える
フィラリア症の予防薬は、犬の体内にいる幼虫を殺し、成虫になるのを防ぎます。ある程度大きくなった幼虫や、肺動脈や心臓に住んでいる成虫にはあまり効きがよくありません。そのため、毎月薬を飲み、その都度幼虫を駆除していくことが必要です。
③もらった薬は最後まで使う
涼しくなって蚊を見かけなくなったからと服用を中断してしまうと、遅い時期に感染した幼虫が成虫にまで成長し、フィラリア症を発症する可能性があります。処方された薬は、最後の1錠まで確実に投薬してください。
フィラリア症の検査と治療

もしも、犬がフィラリア症を発症したら、どのような検査や治療をするのか説明します。
フィラリアの検査
動物病院では、以下のような検査を行い、寄生数と寄生場所を確認します。
・血液検査
・心エコー検査
・エックス線検査
血液検査では、少量の血液を顕微鏡で観察し幼虫を探す直接法と、検査キットで成虫が体内にいるかを判定する抗原検査があります。どちらも10分程度で判定ができます。
心エコー検査では、心臓や血管内に寄生する虫体を確認するほか、異常な血液の流れを判定することができます。検査は無麻酔で15分くらいで行います。
エックス線検査では、虫体は見えません。心臓や肺にどのくらい負担がかかっているかを判断します。検査は無麻酔で15分くらいで行います。
フィラリア症の治療法
フィラリア症にかかっていることが確認できたからといって強い駆虫薬を使うと、死んだ虫が血管や内臓に詰まり、とても危険です。そのため、安全性が高く、成虫をゆっくり殺す作用のある駆虫薬を使って、年単位で段々と虫を減らしていきます。
フィラリア症に関するQ&A
最後に、動物病院でもよく聞かれる、フィラリア症に関する疑問点についてお答えします。
Q.室内飼いでもフィラリア予防は必要ですか?
A.室内飼いの犬でも予防は必要です!
屋内飼いの犬が蚊に刺される確率は屋外飼育の犬に比べると低いですが、散歩中に刺されたり、家の中に完全に蚊の侵入を防ぐことは難しいことです。薬での確実な予防をしてください。
Q.フィラリア症は犬同士でうつりますか?
A.犬から犬へは移りません。
フィラリア症は、蚊の吸血でうつる病気です。もしフィラリア症にかかっている犬と遊んだり触れ合ったりしても、犬から犬に移ることはありません。

Q.猫はフィラリア症にかかりますか?
A.猫もフィラリア症にかかります。
犬の病気と思われがちなフィラリア症ですが、猫もかかることがあります。ただし、猫の体内はフィラリアにとって住みやすい環境ではないため、感染しても大量に虫体数が増えることはないといわれています。

とはいえ、消化器症状や呼吸困難を起こすこともあるので心配でしたら獣医師に相談してください。猫用のフィラリア予防薬も販売されています。
Q.蚊取り線香、超音波など防虫グッズの効果は?
A.完全な予防は不可能です。
防虫グッズでフィラリア症を完全に予防するのは難しいです。また、火の付いた蚊取り線香や、コンセント式の防虫グッズのコードが犬の近くにあるのは思わぬ事故の可能性があり心配です。薬での予防を行いましょう。
Q.飲み忘れに気づいたらどうしたらいいですか?
A.気づいた時点で薬を与えてください。
気づいたらすぐ薬を与えてください。薬に持続効果はないので、次の薬は元々の予定どおり与えて大丈夫です。
Q.生後何ヵ月から予防薬の投与が必要ですか?
A.2ヵ月ごろから予防を始めましょう。
子犬でも蚊に刺されればフィラリア症を発症する可能性があります。目安は生後2ヵ月を過ぎたら予防薬の投与を始めましょう。
まとめ
犬の肺動脈や心臓にフィラリア幼虫と成虫が寄生し、血流障害を起こすフィラリア症について、症状、検査法、治療法を解説しました。
フィラリア症は、蚊の吸血によりうつっていきます。蚊に刺されないようにするのは難しいため、予防薬の確実な投与によりフィラリア症を発症させないことが大事です。
春から秋にかけて、蚊が増える季節。もし予防していないようでしたら、今回の記事を参考に、すぐに病院で受診し、フィラリア症予防をしましょう。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。