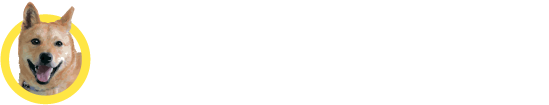犬のパルボウイルス感染症とは

犬パルボウイルス感染症は、ウイルスが犬の鼻や口から侵入し、小腸粘膜の細胞に感染することで、激しい消化器症状を引き起こす病気です。特に子犬では、ワクチン未接種もしくはワクチンによる免疫が弱い段階で感染するとかなりの確率で死亡してしまいます。
犬パルボウイルス感染症の伝染力の強さは、犬の病気のなかでもトップレベルのため、周りの犬へ感染が広がらないよう細心の注意が必要です。
パルボウイルスは熱や消毒に強いウイルス
パルボウイルスは熱や消毒薬に抵抗力が高く、60℃でも1時間は死滅しません。また、アルコール、クレゾール、逆性石鹸などの消毒液では効果がなく、消毒液として強い作用を持つ次亜塩素酸ナトリウムやホルマリンなどを使用してようやく死滅します。
自然環境のなかでも、条件が合えば数カ月以上感染能力を持ったまま生存できるといわれています。
感染経路は経口・経鼻
犬パルボウイルス感染症は、感染している犬の嘔吐物や唾液、下痢などに含まれるウイルスが周りの犬の口や鼻から侵入することで感染します。ウイルスに直接触れたときだけでなく、お世話をした人の手や靴の裏にウイルスが付くと、その人の手や触った食器を介してほかの犬に間接的に感染が広がることもあります。
発症する確率は減っている
現在では、後に解説するワクチン接種などの対策が子犬のうちからしっかり取られており、多くの犬がパルボウイルス感染症の免疫を持っています。そのため、以前のように次々と子犬がパルボウイルス感染症にかかって死んでしまうような事例はあまり見られなくなりました。一般の飼い主では、あまり目にすることのない感染症といえるでしょう。
主に犬パルボウイルス感染症の流行が心配なのは、ペットショップ、ブリーダーなどのワクチン未接種の子犬を集団飼育しているところです。また、災害時の避難所やペットホテルなど不特定多数の犬が集まるところでもし発生すると、ワクチン未接種の犬などにうつる可能性も高く、危険です。
犬パルボウイルス感染症の症状

犬パルボウイルス感染症に感染後約2日で、以下のような症状が現れます。
- 元気がなくなる
- 発熱(発熱しないケースもある)
- 嘔吐
- 下痢や血便(特に「イチゴジャム状」の下痢が特徴)
- 食欲不振、食欲廃絶
- 衰弱
感染後1週間すると、体内でパルボウイルスに対する免疫がつくられるため、軽度〜中度の症状の犬であれば回復の兆しが現れてきます。
体力のない子犬は急死することもあるので要注意
生まれて間もない子犬は、下痢や吐き気が続くと脱水やショック症状を引き起こし、発症後1日程度で死亡することもあります。子犬が発症すると1週間生存率はとても低く、重症例では大抵が残念な結果になってしまいます。
8週齢未満の感染では心筋炎を起こすこともありますが、最近ではあまり心筋型は見かけません。
混合感染にも注意
子犬の時期はほかのウイルスや細菌との混合感染にも注意が必要です。同時に複数の病原体にかかり体力や免疫力が弱ると、重症化しやすくなるためです。
気をつけなければいけない感染症として、ジステンパー、アデノウイルスによる犬伝染性肝炎と犬伝染性咽頭気管炎、コロナウイルス感染症、パラインフルエンザ、大腸菌症などがあります。
犬パルボウイルス感染症の検査法と治療法

動物病院では、便を使った簡易検査キットで判定します。臨床症状や同居犬がいれば状況の聞き取りも重要です。血液検査では、白血球数の減少が見られます。
また、パルボウイルス自体をやっつける薬はないので、いま出ている症状を楽にするための対症療法を行います。嘔吐や下痢などで失った水分と電解質を輸液で補ったり、腸内環境をよくするために抗生剤や整腸剤を投与したりします。
家の犬がパルボウイルス感染症になったら

もし飼っている犬がパルボウイルス感染症と診断されたら、自宅でとるべき対策は以下の3点です。
- 同居犬と隔離
- 消毒の徹底
- お世話のあとは飼い主の手も消毒
それぞれ詳しくみていきましょう。
同居犬と隔離
パルボウイルスの感染力はとても高いため、特に飼い始めたばかりの子犬が体調不良を示したら隔離しましょう。パルボウイルス感染症の予防に関わらず、新しい子犬を迎えたら2週間程度は先住犬とは接触しないように別室で飼育することをおすすめします。
消毒の徹底

パルボウイルスには、次亜塩素酸ナトリウムが有効です。市販の塩素系漂白剤の有効塩素濃度は5〜6%のため、水1Lに漂白剤の原液20mLを混ぜてスプレーボトルなどに入れて使用します。
次亜塩素酸ナトリウムは、有機物に触れると効果が弱まってしまうため、まずは排泄物を消毒液で濡らしたキッチンペーパーなどで覆い、固形物や液体をできるだけ取り除きます。次にその場所にスプレーをしてしばらく放置します。
食器は、消毒液に1時間程度浸したあと洗って乾かします。ケージやトイレの周りも消毒液を浸した雑巾で拭き掃除をしましょう。
お世話のあとは飼い主の手も消毒
まず、飼い主がパルボウイルスに触れてもうつることはありません。同居犬への間接的な感染を防ぐため、感染した犬の世話をするときは、使い捨てエプロンと手袋、マスクなどで防備をして、使い捨てのものは毎回廃棄しましょう。最後に飼い主の手も消毒しましょう。
成犬ではどのくらい注意すべき?
成犬で注意が必要なのは、老犬、持病がある犬、アレルギーなどの理由でワクチン未接種の犬です。ただし、成犬が感染しても発症せずに終わったり、重症化しないことが多いです。
犬パルボウイルス感染症の予防

犬パルボウイルス感染症の予防で最も効果が高いのは、0歳のうちから毎年混合ワクチン接種を受けることです。特にドックランなど不特定多数の犬が出入りする施設へ行くときは注意が必要です。
混合ワクチン接種は必ず受ける
犬の混合ワクチンは、多くの病院で5種のワクチンを基本として、必要であれば住んでいる地域やライフスタイルに合わせて6種や8種のワクチンを接種します。ワクチンを接種することで、パルボウイルス感染症や、同時にかかると危険なアデノウイルス感染症、ジステンパーなどを合わせて予防することができます。
犬の混合ワクチン接種プログラムは、生後2カ月頃から始まり、0歳のうちに2〜3回、1歳以降は年に1回の追加が推奨されます。初回のワクチンはペットショップやブリーダーの元にいるうちに接種することが多いので、多くの飼い主は0歳の2回目もしくは3回目から接種を受けさせることになります。
ワクチンの接種証明書は必ず保管しておく
ワクチン接種をしたあとにもらう「接種証明書」は廃棄せず、少なくとも次回同じワクチンを打つまでは保管しておきましょう。トリミングサロンやドッグランなど、不特定多数の犬が利用する施設では、証明書の提出を求められることがあるためです。
災害時に避難所でペットを預けるときも、伝染病の流行を防ぐためワクチンの接種証明が必要です。
まとめ
犬パルボウイルス感染症について、症状や予防方法、発生したときの対応を解説しました。
- パルボウイルスは感染力が強く、感染した犬の排泄物に直接触れたり、看護をした人の手や食器などを介して間接的にも感染が広がる。
- ワクチン未接種、または接種回数が少ない子犬が発症すると、生存率は大幅に低下する。
- 嘔吐、下痢などの消化管症状を起こし、血液の混ざったイチゴジャムのような水様性の下痢が特徴的。
- パルボウイルスは熱や消毒液に強いため、塩素系漂白剤を薄めた消毒液で徹底的に消毒を行う。
- 混合ワクチンの接種で予防可能なので、0歳のとき2〜3回、1歳以降は毎年の追加接種が推奨される。
- ワクチン接種許可証は保管する。
現代では一般のお宅での発症は少ない感染症ですが、自分の犬や周りの犬を守るためにもワクチン接種は重要な予防手段です。忘れずに接種するようにしてください。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。