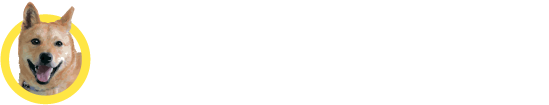愛犬が震えていると、寒い?それとも体調が悪い?と不安に思う方は多いのではないでしょうか。犬の震えは、寒さや興奮、ストレスなどの原因から、緊急度の高い病気までさまざまな原因があります。なかには命に関わるケースもあるため、震えのサインを正しく見極め、適切に対処することが重要です。本記事では、犬の震えが起こる原因から対処法、自宅でできる予防策まで詳しく解説します。万が一に備えて、愛犬が健康に長生きできるよう理解しておきましょう。
犬の震えとは

震えは、医学的には「振戦(しんせん)」と呼ばれ、犬が小刻みに体を揺らす動きを指します。これは、人間が寒いときに体を震わせるのと同じく、自然な生理現象でもありますが、病気のサインや体調不良を示す場合もあるため注意が必要です。
犬が震える主な原因

犬が震える理由は「生理的な震え」「精神的な震え」「病的な震え」の3つのタイプ に分類できます。震えのパターンを理解することで、病院へ行くべきか、それとも自宅で様子を見るべきかの判断がしやすくなります。愛犬にはどちらが当てはまるか、確認してみましょう。
生理的な震え(寒さ・興奮・筋力低下など)

健康な犬でも、寒さや興奮、筋力の衰えなど生理的な原因によって震える場合があります。 このタイプの震えは自然な体の反応で、一時的なものであれば特に心配する必要はありません。
たとえば、飼い主が帰宅したときに興奮して震えたり、冬の寒い日に縮こまって震える場合は、生理的なものの可能性が高いです。
また、筋力低下による震えは、高齢犬や運動不足の犬で起こりやすく、立ち上がるときに後ろ脚の筋肉が震えることがあります。軽度であれば生活に支障はありませんが、重度の場合は介助や治療が必要のため、一度専門機関に相談してみるのがおすすめです。
精神的な震え(恐怖・ストレス・不安など)
恐怖やストレスを感じると、精神的な影響で震えることがあります。これは自律神経の影響によるもので、犬が「怖い」「不安」と感じると、体が無意識に震えてしまうのです。
たとえば、雷や花火などの大きな音に驚いて震えることはよくあるケースです。精神的な震えは、環境や状況を整えることで改善できることが多いです。そのため愛犬が落ち着けるように、常に安心できる環境を整えてあげましょう。
病的な震え(痛み・悪心・不快感など)
愛犬が長時間震えている場合や震え以外の症状を伴う場合は、何らかの病気が原因の可能性があります。病的な震えは、神経系の異常から内臓疾患、外傷や中毒などさまざまな不調で生じます。放置すると悪化したり、ときには命に関わる可能性があるため注意が必要です。
症状が長引く場合や、食欲低下・嘔吐・ふらつきなど震え以外の症状がある場合は、すぐに病院を受診してください。
すぐ病院へ行くべき震えのサイン

病院に連れて行ったほうがよいかどうかは、判断がとても難しいものです。犬の震えが病気によるものかどうかを見極めるポイントとして、以下の症状がある場合は早めに動物病院を受診しましょう。
元気がなく、食欲が落ちている
健康な犬なら、少しの震えがあっても元気に動き回ることが多いですが、元気がなく、食欲が落ちている場合、体調不良や病気が原因の可能性があります。
たとえば、感染症から、胃腸や肝臓、腎臓などの内臓疾患、ホルモン異常などの内分泌疾患など、さまざまな病気で食欲低下などの症状が同時に起こる場合があります。なかでも「震え+元気がない+食欲低下」の場合は要注意です。 動物病院での診察が必要になるケースが多いため、見過ごさずに受診しましょう。
震えが長時間、頻繁に続く場合
犬の震えが長時間続いたり頻繁に繰り返す場合、病的な原因の可能性が高く、早めの対応が必要です。 一時的な震えであれば問題ありませんが、何時間も続いたり数日にわたって頻繁に震える場合は、体に何らかの異常が起きている可能性があります。てんかんなどの神経疾患では、短期間に何度も震えに似た発作が起こることがあります。
また低血糖による震えの場合、放置すると次第に震えが悪化し、重篤な状態になる危険性があります。「震えが長時間続く」「1日に何度も震える」 という場合は、すぐに動物病院へ連れていきましょう。
震え以外にも症状がある場合
下痢や嘔吐・呼吸が速い・歩き方が変などほかの症状が伴う場合は、病気のサインの可能性が高いです。下痢や嘔吐を伴う場合は、胃腸炎など内臓の病気の可能性、咳が止まらない場合や呼吸が速い場合は、肺炎や心臓病などが原因の可能性があります。
また痛がる様子があれば、椎間板ヘルニアなどの神経痛や胃腸炎からくる腹痛かもしれません。熱が出ていれば、細菌感染症などの強い炎症が起こっているサインです。震えと同時にほかの異常が出ていないか、必ずチェックしてください。
気をつけるべき高齢犬や子犬の震え

高齢犬や子犬は若い成犬よりも病気のリスクが高く、注意が必要です。 高齢犬は筋力や神経の衰えによって震えやすくなるうえ、病気が発症すると、症状が深刻化しやすい傾向があります。
一方、子犬は体温調節機能や免疫機能が未熟なため体調を崩しやすく、さまざまな不調から震えが起こりやすい傾向があります。歳だから仕方ないと放置せず、日々の体調をチェックすることが重要です。
震えと似た症状の痙攣には要注意

「震え」と「痙攣(けいれん)」は似ているようで異なります。 痙攣は神経の異常によって起こるため、放置すると危険な場合があり要注意です。
震えは意識がはっきりしており、体の不調も見た目では分かりにくい場合が多いです。一方で痙攣は意識がなく、激しく体が動いて硬直したり、口から泡を吹いたり失禁する場合もあります。ふらふらするなど、痙攣の前兆がみられることもあります。
震えか痙攣か判断がつかない場合は、動画を撮影し、病院で確認してもらうのがおすすめです。 痙攣の可能性がある場合はすぐに受診しましょう。
愛犬が震えを起こしたらすべきこと

もしも愛犬が震えていたら、どうすればよいでしょうか。不安になってしまう方が多いかと思いますが、ここでは落ち着いて対処するポイントをご紹介します。
震えの原因から遠ざける
まずは震えの原因となっている環境や状況を取り除くことが大切です。寒さ・ストレス・痛み・興奮など、震えを引き起こす原因が明らかであれば、それを取り除くことで症状が落ち着くことが多いです。寒さが原因なら暖房をつけ、ストレスが原因なら安心できる場所へ移動させましょう。
過度な興奮が原因なら、静かな空間をつくって落ち着かせてあげるとよいでしょう。すぐに病院へ行くべきケースかどうか判断するためにも、まずは原因を取り除いて様子を観察しましょう。
慣れた毛布やクッションを利用する

寒さや緊張が原因の震えであれば、飼い主の匂いがついた毛布や、いつも使っているクッションで体を覆って温めると、震えが治まることがあります。
ペット用のヒーターや湯たんぽを活用してもよいでしょう。散歩時に震えが出る場合は防寒着を着せたり、帰ってすぐに温めることで改善できるケースもあります。飼い主の匂いや自分の匂いのものに包まれると安心する子も多いので、特に慣れない環境に行く場合は、わざと匂いのついたものを側においてあげるのが効果的です。
いつもと様子が違うなら早めの受診を
震え以外の症状がある場合や、普段と様子が違うと感じたら迷わず病院を受診しましょう。震えが病気の初期症状のこともあるため、油断は禁物です。元気がない、食欲低下、下痢や嘔吐、呼吸が速い、ぐったりしている……なんだかいつもと違うと感じたら、早めの受診が大切です。
震えを予防するためにできること

異常な震えを予防するため、普段の生活の中でできることから始めてみましょう。愛犬の震えに早期に気づいてあげるためにも、普段から意識することが重要です。
生活環境を見直す
日々の生活環境を整えることで、震えの発生リスクを減らせます。室内の温度やストレスになりやすい原因を減らし安心できる環境をつくることが、愛犬の健康維持の第一歩になります。
室温は20℃前後に保ち、雷や花火など大きな音が鳴る場合は、聞こえにくい場所へ移動させてあげましょう。動物病院やペットサロンなど、不安になりやすい環境に連れていくときは、飼い主や自分の匂いがついている使い慣れた毛布で包んであげるのも有効です。
また、獣医師と相談のうえ、不安を軽減させるサプリメントなどを利用するのもよいでしょう。犬が快適に過ごせる環境を整えることで、震えを予防することができます。
普段から体温を把握する

日頃から愛犬の体の状態をチェックし、異変に気づきやすくしておきましょう。 特に愛犬の正常な体温を知っておくことで、震えが出たときに異常かどうかを判断する材料になります。
愛犬のお腹や耳の裏は体温を感じやすい部位です。日頃からスキンシップを通じて、体温の変化を確認する習慣をつけましょう。
ペットショップに犬用の柔らかい体温計が販売されているため、時々お尻から優しく測ってみるのもおすすめです。犬の平熱はリラックスしているときで38度台です。震えを感じた際に測ってみて、低い場合や高い場合は要注意です。普段から体温をチェックすることで、震えの原因を素早く判断できます。
定期的な健康診断を
震えの原因となる病気を早期発見するために、定期的な健康診断はとても大切です。病気の初期は見た目では分からないことが多いため、見落とさないためにもしっかり検査を行いましょう。成犬なら最低でも年に1回、高齢犬なら半年に1回の健康診断がおすすめです。
愛犬の震えを見逃さず守ってあげよう
愛犬の震えは自然なことだと軽視せず、原因を見極めることが大切です。 適切な対応をすることで、不必要な震えを予防して健康を守ることができます。日々のケアを心がけて、愛犬と健やかな日々を過ごしましょう。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。