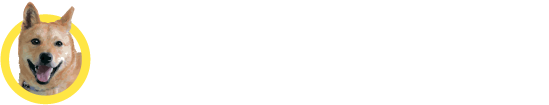「おしっこの回数が増えた」「おしっこの色が赤い」などの変化は、膀胱炎の疑いがあります。膀胱炎は中高齢の犬に多く発症し、主に細菌感染が原因になりますが、尿路結石や腫瘍、オス犬では前立腺のトラブルが関係していることもあります。
この記事では、犬の膀胱炎の原因や症状、治療法、おうちでできる予防法や再発防止策を獣医師がわかりやすく解説します。膀胱炎は何度も繰り返すことも多い病気のため、食事管理や変化に気づいたときの早めの対処が大切です。病気のことをよく知って、膀胱炎になるのを防ぎましょう。
犬の膀胱炎の原因

膀胱炎は、尿の貯蔵タンクである膀胱の内側に炎症が起きる病気です。膀胱炎になる原因には、以下のようなものがあります。
- 細菌感染
- 尿路結石
- 腫瘍
- 前立腺炎
1つずつ解説していきましょう。
細菌感染
犬の膀胱炎は、細菌感染が原因のことが最も多いです。尿道口付近にいる大腸菌や腸球菌、ブドウ球菌などの細菌が尿道を通って膀胱に侵入し炎症が起こります。
細菌感染を起こしやすい要因
以下のような犬は細菌性膀胱炎を起こしやすい傾向にあります。
- メス犬:オス犬と比べて尿道が短くまっすぐなため。
- 中高齢の犬:年をとって免疫力が低下するため。
- 糖尿病の持病がある:尿に糖が含まれており、細菌が増殖しやすいため。
尿路結石

尿路結石と膀胱炎はとても関連深く、尿路結石に続発して膀胱炎を起こすことも多いです。
膀胱や尿道に結石があると、結石が膀胱や尿道の壁に擦れて粘膜が傷つき炎症を起こしたり、そこから細菌が侵入して細菌性膀胱炎を起こしたりします。また、尿道が結石で詰まって尿が排泄できないと、尿の中で細菌が繁殖しやすくなり、炎症を悪化させます。
腫瘍
腫瘍の種類に関係なく、膀胱や尿道にできる腫瘍が膀胱炎の原因になることもあります。腫瘍は中高齢になるとできやすくなるため高齢の犬に多くみられる要因です。
腫瘍が膀胱や尿道の壁にできると、粘膜表面が傷ついて出血したり感染が起こりやすくなったりすること、腫瘍が大きくなると尿の排出を妨げることから、膀胱炎を引き起こします。
前立腺炎からの波及
前立腺炎は、中高齢の未去勢のオス犬で多くみられる病気です。
前立腺炎も、腸内細菌などが尿道を通って前立腺に侵入して炎症が起こります。前立腺は膀胱のすぐ下の位置に尿道を囲むように存在しているので、前立腺に炎症があると、すぐ近くにある尿道や膀胱にも感染が広がりやすいです。
膀胱炎の症状

犬の膀胱炎では、以下のような症状が見られます。
- 頻尿(おしっこの回数が増えるが、量は少ない)
- 血尿(ピンク色〜赤っぽい尿)
- 排尿時の痛み(排尿中に鳴く、震える、排尿を嫌がる)
- トイレ以外の場所で漏らしてしまう
- おしっこの姿勢を何度も取るが出ない
- お腹を触ると痛がる
これらの症状の中でも、頻尿、血尿、排尿の痛みは、尿路結石や腎臓の病気など膀胱炎以外の尿路系疾患の可能性もあるため、早めに受診しましょう。
動物病院での診察・検査

泌尿器系の病気が疑われる場合、尿検査、エコー検査、レントゲン検査、血液検査などを行います。
- 尿検査:尿蛋白、pH、比重、潜血など尿の成分を調べる
- 超音波検査:腎臓や膀胱などに結石や腫瘍がないかを確認する
- 血液検査:炎症の有無や腎臓機能を調べる
Q、尿は自宅で取って持って行ったほうがいいですか?
A、自宅で採れると検査がスムーズですが、難しければ無理せず動物病院に任せてOKです。
基本的な尿検査や健康チェックが目的の時や、犬が採尿に協力的な場合、高齢や持病などの理由で動物病院で採尿をするのが難しい時は自宅で取ってくるよう頼まれることもあります。
この場合は、朝一番のおしっこを清潔な容器にとり、数時間以内に動物病院に持って行くようにしましょう。
膀胱炎の治療方法

細菌感染が原因の膀胱炎には、抗生物質で菌をやっつけ、消炎鎮痛剤で排尿時の痛みや炎症を和らげます。
腫瘍が見つかった場合は、手術や放射線、抗がん剤などで対応します。
尿路結石が原因の膀胱炎では、水をしっかり飲ませておしっこの回数を増やし、自然に結石や細菌を排出するように促します。ただし、石が大きすぎる時や、尿道や尿管に詰まっている時は手術やカテーテルでの処置が必要になることもあります。
予防・再発防止のために自宅での生活で気をつけたいこと

膀胱炎は、犬の体質や食事内容などの生活習慣によっては繰り返しやすい病気です。膀胱炎にならない、または再発させないため、日常生活で気をつけたいポイントをまとめました。
水分量を増やす工夫をする
膀胱炎は水分をしっかり取らせ、おしっこをさせることが一番の予防・再発防止策です。
飲み水のお皿を置く場所を増やしたり、ウェットフードやスープ状のおやつに変更したりして、水分を摂らせる工夫をしましょう。寒い時期や高齢になると水分の要求量も自然と減ってしまいがちなので、少しぬるめのお湯にしたりと積極的に水を取らせることが大切です。
排尿の我慢をさせない
室内のトイレの数、トイレの位置、清潔さを見直し、気持ちよく排尿ができる環境づくりをしましょう。屋外でないと排泄ができない犬は、朝晩以外にも短時間で家の外に出すなど、排尿を促しましょう。
お尻周りを清潔に

膀胱炎になりやすい犬は、お尻周りの毛をトリミングで短くしてもらったり、排泄の後は拭き取るようにし、清潔に保ちましょう。
また、高齢になると体の免疫機能が下がって膀胱炎にかかりやすくなります。特に寝たきりやおむつをしている犬では、お尻周りは不衛生になりやすいので気をつけましょう。
尿路結石では食事管理が重要

尿路結石から膀胱炎を起こすケースでは、食事内容にも気を配りましょう。一方、細菌感染、腫瘍、前立腺炎に関係した膀胱炎では、食べない方がいいものは特にありません。
食事管理で自然と溶ける種類の結石もある
結石の成分は、主に2つに分けられます。
- ストルバイト結石
- シュウ酸カルシウム結石
ストルバイト結石は、主に細菌感染が原因であり、尿を酸性に傾けると自然と溶けていく性質があります。そのため、動物病院で処方される療法食で尿の性状をコントロールし、食事に含まれるリンやマグネシウムの量を制限することで数週間〜数ヶ月かけて結石を溶かしていきます。
一方、シュウ酸カルシウム結石は細菌感染とは関係なくできる結石で、溶かすことができません。結石は自然と排泄されるのを待つか、手術や処置で取り除きます。そのあとは、療法食でカルシウムやシュウ酸などを過剰に摂取しないように管理をします。
手づくりのご飯は、食事中のミネラルバランスや尿の性質の管理が難しいので、尿路結石が関係する膀胱炎と診断された場合は、動物病院で処方される療法食に切り替えることをお勧めします。
まとめ
この記事では、犬の膀胱炎について、原因や症状、治療法、自宅でできるケアや食事管理などの予防・再発防止方法を解説しました。
犬の膀胱炎は、細菌が原因になることが多いですが、尿路結石や腫瘍、前立腺の病気が関係していることもあります。おしっこの回数が増えたり、血が混じったり、排尿時に痛がったりするなどのサインが見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。治療は、原因に合わせてお薬や手術、食事の見直しなどが行われます。
予防や再発を防ぐには、しっかり水を飲ませることやおしっこを我慢させない環境づくり、お尻まわりの清潔さを保つことが大切です。おしっこの悩みはつらいものなので、普段の健康づくりから気をつけていきましょう。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。