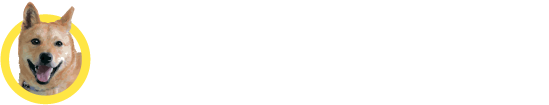犬の歯周病とは?原因と発症リスク

歯周病は、口の中で歯垢(しこう:食べかす)や歯石(しせき)が増えることによって細菌が繁殖し、口や周りの組織に炎症を引き起こす病気です。進行すると全身にさまざまな悪影響を及ぼすため、飼い主による早期発見と毎日の予防が非常に重要です。
歯周病の主な原因
歯周病の主な原因としては、歯磨き不足が挙げられます。歯磨きをせず放置しておくと、歯ぐきに歯垢が付着します。歯垢は食べかすや細菌が混ざり合った物質で、数日かけて歯石に変わり歯周病菌が増殖する温床となり、より歯周病が悪化する原因となります。
そのほか、生まれつき顎が小さく歯並びが悪い不正咬合(ふせいこうごう)や、乳歯と永久歯が同時に生える乳歯遺残(にゅうし遺残)がある場合は、より歯周病のリスクが高い傾向にあります。
放置するとどうなる?歯周病が全身に与える影響
歯周病は口の中だけではなく、全身にも悪影響を及ぼすことがあるため、油断は禁物です。口の中の菌が血流に乗って全身に広がると、心臓や肝臓、腎臓などいろいろな臓器に影響を与えることが報告されています。
また、歯周病による口の痛みからご飯が食べられなくなると、体重が減り、さまざまな病気にかかりやすくなってしまいます。愛犬の歯周病は決して軽い病気ではなく、飼い主が日頃から意識して気をつける必要があります。
歯周病の主な症状

歯周病は、初期のうちは日常生活に影響が出ることはほとんどありません。しかし、進行すると見た目の変化に加え、全身に影響を与えるようになります。日常生活にも支障が出てくるため、進行する前に早めに対処してあげることが大切です。
初期は口臭や歯肉の腫れに注意
初期の歯周病の症状では、歯ぐきが汚れたり歯肉がわずかに赤くなるなど、些細な見た目の変化が出てきます。ほとんど日常生活に変化が見られないため、見過ごしてしまうことも多いので、定期的に確認するとよいでしょう。
中期〜重度では食欲が無くなることも
進行した歯周病では、日常生活ではっきりと症状が現れるようになります。何度もクシャミをしたり、鼻水や強い口臭、歯がぐらついたり抜け落ちるなどの症状のほか、時には顎の骨が骨折したり、歯根に膿(うみ)が溜まり皮膚が裂けることもあります。このような辛い症状が出る前に、異常を感じたらすぐに動物病院へ連れていきましょう。
飼い主ができるセルフチェック方法

愛犬の歯周病の有無は、ご家族でも簡単にチェックすることが可能です。以下のような症状が複数見られる場合は歯周病の可能性が高いため、要注意です。
- 愛犬の口臭が強い
- 歯ぐきが腫れて出血しやすい
- 歯垢や歯石が溜まっている
- クシャミや鼻水が増えた
- 歯がぐらぐらしている
- 両方の目の下や頬が腫れている
- 痛がって硬いフードを食べられない
犬の歯周病の診断方法

犬の歯周病を診断するためには、いくつかの方法があります。初期段階では症状が目立たないことが多いため、症状を見逃さないように定期的な動物病院での健診が不可欠です。
視診と触診
まずは診察時に愛犬の口の中を直接確認し、歯肉や歯石の状態をチェックします。しかし、口の中を触られるのが嫌いな子が多く、全体像を把握するのが難しい場合もあります。
画像検査
歯周病の検査では、隠れている歯根部分を確認することが非常に重要です。見た目は綺麗でも、実は歯の根元が溶けている場合も少なくありません。そのため全身麻酔下で歯科用の特殊なレントゲン検査を行い、歯周ポケットの深さや歯槽骨(歯を支える骨)の状態を確認します。
犬の歯周病の治療方法
歯周病の治療は、軽度の場合と重度の場合とで治療法が異なります。
軽度の歯周病の場合
わずかな歯石や歯垢がついているだけで症状がない場合は、毎日の歯磨きなどデンタルケアで経過観察を行う場合が多いです。歯磨き以外にも、サプリメントや飲み水に混ぜる薬液を活用することもあります。
また、1度できた歯石は歯磨きで落とすことができないため、歯周病の進行を予防するため早期に歯石除去の手術を行う場合もあります。
重度の歯周病の場合
歯周病が進行している場合は、抗生剤や止血剤、痛み止めなどの薬を使って内科的に治療する場合と、根治のために外科治療を行う場合があります。外科治療では、全身麻酔下で歯石の除去と抜歯を行います。その際に歯周ポケットを洗浄したり、抜歯後に歯肉の縫合を行う場合もあります。
治療にかかる費用の目安
軽度の治療では、薬の処方のみで一般的に数千円〜数万円程度ですみますが、外科的な処置が必要となる場合は、手術だけで10万円前後の費用がかかることもあります。そのほか血液検査やレントゲン検査などの各種検査費用がかかります。治療費用は病院によって異なるため、かかりつけの病院に相談してみるのがおすすめです。
自宅でできる歯周病の予防・対策

歯周病は、毎日の予防で未然に防ぐことが可能です。日頃からご家族でデンタルケアを実施し、愛犬の健康を守ってあげましょう。どれも今日から実践できる内容なので、始めやすいものから試してしてみてください。
日々の歯磨きを習慣に
毎日の歯磨きは、最も効果的な歯周病の予防策です。最近ではさまざまな形状の歯ブラシがあるので、愛犬に合ったものを選んであげましょう。歯垢は、約2〜3日で歯石になるとされています。そのため毎日の歯磨きが難しい場合は、最低でも週に3回以上は実施してあげるのが大切です。
デンタルケア製品を上手に活用
毎日のデンタルケアには、歯ブラシ以外にも多様なデンタルケア製品が販売されています。歯磨きが苦手な子には、歯ブラシよりも簡単で取り組みやすい玩具やおやつから始めるのもおすすめです。

歯に良い食事とおやつの選び方
手づくり食やウェットフードは水分が多く含まれているため、ドライフードよりも歯垢が付着しやすいとされています。そのため、歯石の形成を防ぐためには、歯にやさしい低糖質のドライフードを選ぶのが好ましいです。ただし、日頃から多く水分を摂取する必要のある子は、必ず獣医師に相談してからご飯を変えるようにしましょう。
歯磨きが嫌いな子のケア方法
口の中に歯ブラシが入るのを怖がる犬は少なくありません。子犬のうちから少しずつ、遊びのなかでトレーニングしていくことが重要です。歯ブラシはブラシタイプだけでなく、指サック型や指に包んで使うシートタイプなど、さまざまな形状のものがあります。愛犬が一番嫌がらずにできるものを選んであげましょう。
ケアに慣れるまでは、少しずつ短時間から始めることがポイントです。歯磨き粉もいろんな味を試して、愛犬の好みのフレーバーを見つけてあげてください。

歯周病を防ぐため飼い主が知っておくべきこと
歯周病は、多くの病気のなかでも飼い主のケア次第で予防できる数少ない病気のひとつです。ここでは、歯周病を防ぐために事前に知っておきたい大切なポイントを紹介します。
自己判断は禁物!専門家に相談しよう
歯周病は、放っておくと徐々に進行します。特に高齢犬は歯周病が進行してしまうと、持病や年齢のために麻酔が難しくなり治療が難航することも多いです。元気だから大丈夫だと安易に考えず、まずは獣医師に相談しましょう。
食べ物やおもちゃの硬さに要注意
一見歯に良さそうに見える硬い玩具やおやつは、実は歯が欠けてしまう原因になることもあります。馬や牛のヒヅメのおやつや、硬い木の枝などの玩具は、小型犬の歯にとって硬すぎる場合があるので注意が必要です。
万が一歯が欠けて神経が露出した場合は、細菌感染のリスクが高まるため、詰め物や抜歯が必要になる場合もあります。日頃から愛犬の歯の大きさに合ったものを用意してあげるのはもちろん、歯が欠けていないか日頃からチェックしてあげましょう。

若齢犬や高齢犬のケアは特に慎重に
子犬は、成長の過程で乳歯が永久歯に生え変わります。生まれつき不正咬合(噛み合わせが悪い)や乳歯遺残(乳歯が抜けず残っている状態)がある場合は、歯周病のリスクが高いため、子犬のうちから対策する必要があります。また、高齢犬は若齢犬よりも歯周病のリスクが高いため、定期的な診察が重要です。
歯科専門の動物病院も確認してみる
全国には、歯科治療を専門的に行う動物病院も存在します。一般の動物病院だけでなく、歯科専門の診療を行っている施設を検討することで、より専門的な治療を受けることができます。ぜひ近くの動物病院をチェックしてみてください。
歯周病を予防して愛犬と笑顔あふれる毎日を
犬の歯周病は、正しい予防と早期治療で進行を防げます。毎日の歯磨きや口腔ケア製品の活用、動物病院での定期検診を習慣化して、大切な愛犬の健康寿命を伸ばしましょう。愛犬と健康的で楽しい毎日を過ごすために、今日からデンタルケアを始めてみてはいかがでしょうか。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。