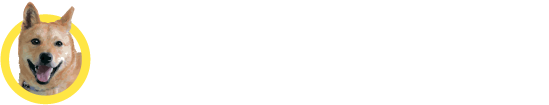犬の予防接種とは

犬の予防接種とは、特定の感染症に対しての免疫力を高め、感染症の発症を予防するための処置のことです。犬の感染症のなかには発症すると重い症状を引き起こすものがたくさんあります。そうした感染を予防するため、ワクチンを適切に接種することが重要です。
犬の予防接種には、大きく分けて「狂犬病ワクチン」 と 「混合ワクチン」 の2種類があります。それぞれ詳しくみていきましょう。
狂犬病予防接種とは
狂犬病は「発症すると致死率ほぼ100%」という非常に危険なウイルス感染症です。犬だけでなく、人間を含む哺乳類全般に感染する「人獣共通感染症(ズーノーシス)」の一種で、世界的に大きな問題となっています。狂犬病ワクチンは、このウイルスに対する免疫をつくり、感染を予防します。
病気が人と犬に及ぼす影響
日本では、1957年以降国内での狂犬病の発生はありません。しかし、2006年には海外で感染した日本人の死亡例が報告されており、2024年にも海外で感染した外国籍の男性が日本で発症し死亡しています。海外から人や動物の出入りが活発になっている現在、狂犬病ウイルスが日本に再び侵入してくるリスクは高まりつつあります。
狂犬病予防接種が義務化されている理由
国内での狂犬病の侵入・拡散を防ぎ、安全な社会を維持するために、日本では「狂犬病予防法」によりワクチン接種が義務化されています。生後91日以上の犬には毎年1回の狂犬病ワクチン接種が義務付けられており、未接種の犬を飼育していると、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
狂犬病予防接種の接種時期

生後91日以上の犬は、1回目の接種が義務化されています。その後は毎年1回の追加接種が必要です。市町村に愛犬を登録すると、毎年3〜4月上旬に各市町村から狂犬病予防接種の案内ハガキが届くので確認してみましょう。
狂犬病予防接種の接種場所
狂犬病予防接種は、自治体が主催する「集合注射」と、動物病院での「個別接種」のどちらでも実施可能です。集合接種は、地区によって接種会場と日程が決められており、費用が安く時間がかからないのが利点です。
一方、動物病院での接種は、1年中問わず接種が可能で、獣医師の診察を受けた上でおこなえます。愛犬の健康面が気になる方は、動物病院での接種がおすすめです。
狂犬病予防接種の手続き

狂犬病予防接種の手続きは、動物病院が代わりにおこなうか、飼い主自身が「狂犬病予防接種注射済証明書」を持参して市役所等で手続きをする場合の2通りがあります。接種後に交付される注射済票と鑑札は、忘れずに愛犬の首輪や胴輪に装着してあげましょう。
もしも狂犬病予防接種を受けていない犬が人を噛んだ場合

犬が人を噛んでしまった場合、狂犬病ワクチンを接種しているかどうかで対応が大きく異なります。
狂犬病予防法では、犬が人を噛んだ場合、飼い主は24時間以内に自治体に届け出なければいけません。また、動物病院で狂犬病でないことを証明する鑑定を受け、「狂犬病鑑定書」や「証明書」を保健所に提出します。その際に監視や隔離措置を受けることも。飼い主に過失が問われ、損害賠償を受けるリスクもあります。
愛犬の咬傷事故は、どんなに愛犬に悪気が無くても大問題になりかねません。必要な知識を押さえ、万が一の際は落ち着いて対処しましょう。
犬の混合ワクチンとは

混合ワクチンとは、複数の感染症を一度に予防できるワクチンです。狂犬病予防接種とは異なり、法律で義務付けられているわけではありませんが、感染症予防のために接種が推奨されています。
コアワクチン4種、ノンコアワクチン4種の組み合わせにより2〜11種類の混合ワクチンがあります。多くの動物病院では、犬の生活環境や健康状態に応じて、5種から10種のどれかを取り扱っていることが一般的です。
混合ワクチンで予防できる病気
混合ワクチンで予防できる病気は「コアワクチン」と「ノンコアワクチン」に分けられます。「コアワクチン」とは、生活環境によらずどんな犬にも接種を推奨するワクチンです。一方「ノンコアワクチン」は、生活環境に応じて接種をおこなうものをいいます。
- コアワクチン(すべての犬に推奨)
- 犬ジステンパーウイルス感染症
- 犬アデノウイルス1型感染症(犬伝染性肝炎)
- 犬アデノウイルス2型感染症(犬伝染性喉頭気管炎)
- 犬パルボウイルス感染症
- ノンコアワクチン(生活環境によっては推奨)
- 犬レプトスピラ感染症
- 犬コロナウイルス感染症
- 犬パラインフルエンザウイルス感染症
- 犬ボルデテラ・ブロンキセプチカ感染症
混合ワクチン接種しないとどうなる?
狂犬病予防接種と違い、混合ワクチンの接種は飼い主の自由意思によります。ここでは、ワクチンを接種しなかった際に気をつけるべきポイントを解説します。
感染症の発症リスク
ワクチンを接種しない場合、致死率の高い感染症を発症するリスクが増加します。特に子犬や老犬は免疫力が弱いため、感染すると重篤化し命の危険を伴いやすく、注意が必要です。
サロン・ホテルなどへの制限
ペットホテルやトリミングサロン・ドッグランなど多数の犬が利用する施設では、事前に狂犬病予防接種と混合ワクチン両方の証明書の提示が必要な場合が多いです。接種をしていないと利用できないことがあります。
混合ワクチンの種類と接種時期

多くの動物病院では、5種と10種や6種と10種など、2種類ずつの組み合わせで取り扱っている場合が一般的です。何種を選ぶべきかは、愛犬の生活環境と体調面から総合的に判断して決めます。
何種を選ぶべき?
7種以上の混合ワクチンには、ノンコアワクチンのなかでも特に「レプトスピラ感染症」の予防を含んでいます。レプトスピラ感染症は細菌による人獣共通細菌感染症で、野生動物の尿で汚染された土壌や水辺から感染することが多いとされています。そのため野外に行く機会が多い犬は感染リスクが高く、7種以上のワクチンを摂取したほうが安心です。
一方で、室内で生活し、ほかの犬との接触が少ない場合や、アレルギー体質でワクチン接種後に体調を崩しやすい場合は無理をせずに、6種以下のワクチンを選ぶのがおすすめです。
混合ワクチンの接種時期
混合ワクチンは、子犬と成犬で接種間隔が異なります。子犬は生後6〜8週齢で初回のワクチン接種をおこない、その後は16週齢またはそれ以降まで、2〜4週間間隔で接種を行うことが推奨されています。1歳になるまでは、接種する時期と接種間隔によって2〜4回のワクチンを接種、それ以降は動物病院によって差はありますが、1〜3年に1回の接種が一般的です。
予防接種の副反応と注意点

なかにはワクチン接種後に副反応が出る子もいます。一般的に混合ワクチンよりも狂犬病ワクチンのほうが副反応は少なく、食欲不振や注射部位の軽度の腫れなどは、一般的に数時間~数日で回復することが多いですが、急激な顔の腫れや呼吸困難、嘔吐下痢など症状が重度の場合はすぐに動物病院へいきましょう。
こうした副反応のリスクもあるため、ワクチン接種はなるべく午前中に受け、午後は様子を見れるよう余裕を持ったスケジュールでの接種をおすすめします。
予防接種を打てない場合
ワクチンは、ほとんどの犬にとって有効な感染症予防策ですが、体質や健康状態によっては接種が難しい場合もあります。そんなときは自己判断で予防接種を避けるのではなく、必ず獣医師に相談しましょう。
軽度のワクチンアレルギーの場合は、アレルギー反応を抑える注射を事前に打つことで安全にワクチン接種ができます。重度の場合、ワクチンの効果がどの程度体内に残っているかを調べる「ワクチン抗体価検査」をおこない、接種回数を安全に減らすことも可能です。
また、高齢犬や持病持ちでどうしても狂犬病予防接種ができない場合、市町村によっては「猶予証明書」の届出を行うことで狂犬病予防接種が免除できる場合もあります。
犬の予防接種にかかる費用
狂犬病予防接種は、自治体や動物病院で多少の差がありますが、一般的に集合注射で3,000円程度、動物病院だと3,000〜4,000円程度かかります。
一方、混合ワクチンは、動物病院の診察料と取り扱っているワクチンの種類により差があります。平均的にワクチン費用と診察代込みで7,000円〜9,000円前後のことが多いです。
ペット保険で予防接種費用はカバーできる?
一般的にペット保険は病気やケガの治療費が対象で、ワクチン接種費用は補償対象外です。しかし、一部の保険会社では「予防医療特約」を付けることで補償を受けられる場合があります。混合ワクチン接種を含めた予防医療がお得に受けられるものもあるため、ぜひ探してみてください。
愛犬と長く健康に暮らすために
愛犬のワクチン接種は、感染症から愛犬を守る重要な手段です。しかしすべての犬に一律のワクチン接種が適しているわけではなく、年齢や体質を考慮することが大切です。 ワクチン選びに迷ったら、かかりつけの獣医師に相談しましょう。怖い病気を予防して、愛犬と安心して春を迎えられると良いですね。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。