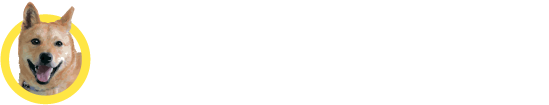今年も風邪や感染症がはやる季節になってきました。私たちは咳や鼻水が2〜3日続くと「風邪をひいたかな?」と薬を飲んで早く寝るなどの対応をとりますが、犬も風邪をひくのでしょうか。
結論からいうと、犬には風邪をひくという概念がありません。注意してほしいのは、犬に咳や鼻水、発熱など人間の風邪のような症状が出たときに疑われる病気です。今回は、人間でいう犬の風邪の症状について解説します。
犬には風邪に該当する病名はない
人間には、鼻やのどの炎症を主な症状とするウイルス性感染症に「風邪症候群」という正式な病名がありますが、犬には人間でいう風邪に該当する病名や病気の定義はなく、「風邪」という診断名はつきません。
しかし、犬も、鼻水やくしゃみ、発熱、咳といった鼻やのどに症状が現れる病気はあります。犬でこれらの症状が出たときにはどのような状態になるのか、みていきましょう。

犬の咳
犬の咳の音は「コン、コン」とか「ゴホン、ゴホン」というよりは、のどにつかえたものを吐き出すような「カハッ、カハッ」という音に近いです。実際、動物病院に犬の咳を「犬ののどに何かつかえているようだ」といって来院する方もいます。
犬の鼻水
犬の鼻は湿っていることが多く、時々、犬の鼻が乾燥していると心配する飼い主がいます。しかし、犬の鼻は興奮や緊張によっても乾燥しますし、普段から乾燥気味な犬もいるなど個体差もあるので、乾いていてもそれほど心配はいりません。
鼻水にも、透明で水のような鼻水と、何か細菌感染が起きているときの黄色っぽい鼻水があります。
犬のくしゃみ
犬のくしゃみは、人間と同じく生理反応です。強い匂いを嗅いだり、鼻の中にホコリや草の種などの異物が入ったときに反射的にでます。多くのケースで、すぐに収まります。

犬の発熱
犬が発熱すると、元気がなくてぐったりしている、呼吸があらい、動きたがらない、食欲がないといった症状がみられます。
犬の平熱は38.5度前後で、人と比べるとやや高めです。興奮しているときや運動の後はやや高くなります。動物病院では、お尻に体温計を入れて直腸温を測定しますが、普段から自宅で犬の体温を測っている方はあまりいないでしょう。犬が発熱していても分からないのではと心配になるかもしれませんが、普段から犬をよく触って犬の体温に慣れていると異変に気づきやすくなります。耳や足先など、被毛が少ない部分は体温の変化を感じやすいので、ぜひ試してみてください。
犬に風邪のような症状を示す病気
これまでご紹介した犬に風邪のような症状を示す病気で、注意しなければいけない病気を紹介します。
- ケンネルコフ(犬伝染性気管支炎)
- 気管虚脱
- 鼻炎
- 鼻腔内腫瘍
- 犬フィラリア症
- 心臓病
それぞれの病気について次章で詳しくみていきましょう。
「ケンネルコフ」は感染力の強い病気
ケンネルコフ(犬伝染性気管支炎)は、ウイルスや細菌への感染により、咳、鼻水、発熱などの呼吸器症状がみられる病気です。1歳以下の子犬に多く発生しますが、病中・病後やストレスなどで免疫が低下している成犬や、シニア犬でも発症することがあります。
混合感染で重症化する
ケンネルコフの原因となるのは、「犬アデノウイルス2型」や「犬パラインフルエンザウイルス」「ボルデテラ菌」「マイコプラズマ」などの病原体です。これらの病原体のうち複数が混合感染すると症状が悪化しやすくなります。
重症化すると、以下のような症状がみられるようになります。
- 乾いた咳
- 発熱
- ネバネバした黄色い鼻水
- 元気消失
- 食欲不振
- 目やに
- くしゃみや咳などで感染が広がる
ケンネルコフの原因となるウイルスや細菌は、感染している犬のくしゃみや咳などの飛沫で感染するほか、鼻水や唾液などに直接触れることでもうつっていきます。
ケンネルコフは伝染力がとても強く、犬を多数飼育しているブリーダーや、ペットホテル、ドッグランなど不特定多数の犬が集まる場所で広がりやすい傾向にあります。特に、ワクチン接種前の子犬は、1匹症状が出るとすぐに広まりやすいため、注意が必要です。
家に新しく連れてきたばかりの子犬は特に注意
ウイルスや細菌は、体の中に入ってから症状が出るまでに3〜10日の潜伏期間があります。そのため、子犬を家に連れてきたときは元気だったのに、1週間程度経ってから咳や鼻水が出るようになり、調べてみたらケンネルコフにかかっていたというケースもよくあります。
子犬に咳や鼻水のような症状がみられるときは動物病院を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。特に、ペットショップやブリーダーからご自宅に迎えたばかりのワクチン未接種の子犬、またはワクチンの回数が少ない子犬は免疫力も弱いため、早めに対処しましょう。

子犬、シニア犬は肺炎に移行しやすいので注意
ケンネルコフの原因となる病原体のうち、特に注意が必要なのは「犬アデノウイルス2型」と「犬パラインフルエンザウイルス」です。どちらのウイルスも、単独感染の場合は鼻水、咳などの軽い症状がでて徐々に回復していくことが多いですが、感染が長引いてほかのウイルスや細菌と混合感染すると重症化しやすい傾向にあります。
特に、免疫力の低い子犬(目安としては体重1kg以下)、シニア犬、呼吸器や心臓に持病のある犬は、炎症が肺にまで広がって肺炎を起こすこともあるので注意が必要です。
ケンネルコフの治療
動物病院では、抗生剤や咳止めの内服薬や、点滴などの治療をおこないます。軽度なら2、3日で快方に向かっていきますが、重症化し肺炎を起こしているようなケースでは、入院して酸素室での酸素吸入、持続的な点滴などの治療が必要になることもあります。
低温や乾燥は、咳の原因にもなります。自宅では、部屋の温度や湿度を適正に保ち、食欲がないときは無理に食べさせず、安静に過ごしましょう。
なお、犬にとって快適な環境は、室温22〜25℃、湿度50〜60%といわれています。

予防は定期的なワクチン接種
ケンネルコフの原因となる病原体のなかで、「犬アデノウイルス2型」と「犬パラインフルエンザウイルス」は、犬の混合ワクチンを接種することで予防できます。
犬のワクチンのうち、狂犬病は狂犬病予防法という法律で接種が義務づけられていますが、混合ワクチンの接種は飼い主の任意となっています。
しかし、最近ではドッグランやペットホテルの利用にワクチンの接種証明書が必要な施設が増えてきています。また、災害時にペットシェルターや一時預かり施設に犬を預けたいときにも接種証明書が必要になることが多いため、ワクチンは毎年受けるようにしましょう。
以下のふたつのポイントに注意して、愛犬をケンネルコフから守りましょう。
- ワクチンは初年度2〜3回、1歳以降は年1回接種する。
- ドッグランやペットホテルを使用するときは、利用条件に接種証明書の提出を求めるなど管理がしっかりしているところを選ぶ。

「気管虚脱」は咳や呼吸困難に注意
気管虚脱(きかんきょだつ)は、ポメラニアンやヨークシャーテリア、チワワなどの小型犬、パグなどの短頭種に多いといわれていますが、すべての犬種に起こりうる病気です。
気管が押しつぶされて空気が通りにくくなることで咳が出たり、アヒルの鳴き声のような呼吸音がするようになります。
治療は、気管支拡張剤や咳止めなどの薬を飲む内科療法と、気管の内側にコイルを入れたりして気管の形を整える手術もあります。
「鼻炎」は原因が幅広く、くしゃみ、鼻水がみられる
犬の鼻炎は、原因がさまざまです。
主なものには、
- ウイルス、細菌、真菌(カビ)の感染
- 異物(植物の種など)が鼻に入った
- 歯周病、口腔内腫瘍など口の中の病気が鼻に波及した
などがあります。
また、重度の歯周病では、歯を支えていた骨が溶けて穴が空き、口腔と鼻腔がつながってしまいます。その結果、炎症が鼻のほうにまで広がり、鼻水やくしゃみといった症状が出ることがあります。
「鼻腔内腫瘍」は早めに受診すべき
犬の鼻腔や副鼻腔に腫瘍(しゅよう)ができた場合、進行の早い癌であるケースが考えられます。最初はくしゃみや鼻水程度だったものが、鼻血を出したり、マズルの形が変わってきたなどの症状がみられたら、早めに動物病院を受診してください。
「犬フィラリア症」は初期に咳がみられる
犬の肺動脈や心臓に、犬糸状虫(フィラリア)という線状の寄生虫が住みつくことで血流障害が起こる病気で、一般的には初期に乾いた咳が出ます。多数のフィラリアが寄生すると突然死することもあります。また、蚊の吸血によりうつっていくため、毎年予防薬を使うことがとても重要です。
【関連記事】犬のフィラリア症は予防薬で確実に防げる!症状や正しい薬の使い方を解説【獣医師監修】
「心臓病」でも咳が出る
僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜん)など心臓病が原因で咳が出ることもあります。心臓に病気があると、拍動のしにくさを補うため心臓が肥大します。大きくなった心臓が肺や気道を圧迫したり、肺に水が溜まることで咳が出ると考えられています。
犬の「アレルギー」は皮膚症状が多い
花粉やハウスダストが原因となるアレルギーでは、人の場合はくしゃみや鼻水のような呼吸器症状が現れます。しかし、犬の場合、かゆみや脱毛、赤みなどの皮膚症状が出ることが多く、くしゃみや鼻水などの呼吸器症状はあまり出ません。

まとめ
この記事では、犬に咳、鼻水などの風邪のような症状が出たときに疑われる病気について解説しました。犬には、人間でいう風邪に該当する病気はなく、ちょっとした咳や鼻水でも大きな病気が隠れていることがあります。
特に注意してほしいのが、ケンネルコフです。
- ケンネルコフは子犬で特に注意が必要な感染力の強い病気。
- ケンネルコフはワクチンで予防できる。
- 咳で注意が必要な病気には、気管虚脱や鼻炎、鼻腔内腫瘍、心臓病、犬フィラリア症などがある。
このほかにも、今回ご紹介した気になる症状がみられたら、動物病院を受診して適切な処置を受けましょう。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。