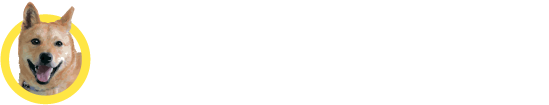お昼寝が気持ち良い季節となりました。しかし、愛犬が長時間寝ていると心配に感じたことはありませんか?睡眠には、犬の健康状態や心のサインが表れることがあります。 眠りの変化は、実は病気やストレスの兆候かもしれません。この記事では、年齢別の睡眠時間から病気に関わる危険な寝方、快適な睡眠環境の整え方まで、睡眠を通した愛犬の健康管理に役立つヒントをお届けします。愛犬の眠りを見直すことで、家族みんなで心地の良い毎日を過ごしましょう。
犬の睡眠サイクルとは

犬の睡眠は、人とは大きく異なります。 人の睡眠サイクルは、1日1回まとまった長い睡眠をとる「単相性睡眠(たんそうせいすいみん)」に当てはまりますが、犬を含めた多くの哺乳類は1日に複数回眠る「多相性睡眠(たそうせいすいみん)」という特徴をもちます。
これは犬がもともと野生動物だった頃に発達した機能で、深い眠り(ノンレム睡眠)に入る時間を最小限に抑え、浅い眠り(レム睡眠)を何度も繰り返すことで外敵から身を守っていたとされています。
犬も睡眠中に夢を見る?

実際のところ、犬が睡眠中に夢を見るかどうかは、科学的にはまだ証明されていません。しかし、睡眠中の脳波の動きが人間と似ている報告があることや、寝ているときに足や尻尾をパタパタ動かす姿が度々見られることから、人と同様に、脳が活発に活動しているレム睡眠中に夢を見ているのではないかと言われています。
犬でも過去の記憶や経験が「夢」として再現されている可能性が高いようです。
年齢別の理想的な睡眠時間
人は年齢によって最適な睡眠時間は変化しますが、犬の場合はどうなのでしょうか。年齢別に犬の理想的な睡眠時間をみていきましょう。
子犬の場合:16~20時間

子犬は1日の大半を眠って過ごします。 これは成長期に必要な体力や、学習した情報の整理に睡眠が深く関わっているからです。
子犬の1日の平均的な睡眠時間は約16〜20時間ほどとされており、人の赤ちゃんと同じようにたくさんの休息を必要としています。
成犬の場合:9~14時間

子犬が成長していくにつれ、睡眠時間は次第に短くなり、成犬になると約9〜14時間程度に落ち着きます。
高齢犬の場合:12時間~

一般に高齢になると次第に睡眠の質が低下するため、昼間の睡眠時間が増えていきます。そのため1日に約12時間以上もの睡眠をとるようになるとされています。年齢を重ねると体力が落ち、ちょっとした運動や刺激にも疲れやすくなるため、こまめに眠って体を休めることが必要なのです。
犬種による睡眠の違い

犬の睡眠時間には、犬種や体格による違いも見られます。一般に、大型犬は体力の消耗が激しく、長めの睡眠を必要とする傾向があります。グレートピレニーズやラブラドールレトリーバーなどの犬種は、成犬であっても15時間以上の睡眠をとることがめずらしくありません。
一方、小型犬は大型犬に比べると睡眠時間が短く、活動時間も長めになることがあります。ただし大きさだけで一概には決められず、性格や生活環境でも個体差があるようです。
また、フレンチブルドッグやパグなどの短頭種は、生まれつき鼻から喉にかけての構造が細いためいびきをかきやすく、睡眠の質に影響を与える可能性があるため注意が必要です。
寝相からわかる愛犬の心と体のサイン

愛犬がスヤスヤと寝る姿は愛おしいもの。人と同じように犬によって寝相はさまざまです。こうした寝相や寝方から、愛犬の心や体の状態を読み取ることができます。
リラックスしたときの寝姿
犬の寝相には、心の状態がよく表れます。 安心しているときによく見られるのが、「横向き寝」や「へそ天(仰向け)」といった姿勢です。これらは体の急所を無防備にさらしている状態で、警戒せずに安心できていることを意味します。とくに飼い主のそばで伸び伸びと眠っている姿は、飼い主を信頼しているサインのため、優しく見守ってあげましょう。
注意するべき寝相も
一方で、警戒や不調を示す寝相も存在します。伏せたまま頭だけ起こしている場合や座ったまま目を閉じている場合は、痛みや呼吸の苦しさを感じて耐えている可能性があります。
また、胸や腹部を床につけたがらずに、丸め込んでいる場合もお腹の痛みを抱えている可能性があるため要注意です。睡眠時の姿勢がほかの犬と違うかもと感じたら、一度動物病院で相談してみましょう。
病気を疑う注意すべき眠りのサイン

愛犬が普段と違った眠り方をしている場合にも注意が必要です。ちょっとした睡眠の変化が体調や病気のサインとなることもあります。ここでは、病気と関連する寝方の特徴を紹介しますので、愛犬に当てはまるものがないか確認してみましょう。
眠りすぎている場合
愛犬が普段に比べて1日中寝てばかりいるのは、病気のサインかもしれません。甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう)などのホルモン疾患や、脳腫瘍などの神経疾患などが潜んでいると傾眠状態(意識障害のひとつ)となり、まるで眠っているかのように見える場合があります。
朝から夕方までほとんど動かず、食欲もないなどの変化があれば、早めに動物病院で診察を受けましょう。
寝られていない
反対に、十分に眠れていない場合も要注意です。夜中に何度も起きてウロウロしたり、日中ウトウトしてもすぐ目を覚ますような場合は、病気が原因で眠れていない可能性があります。
息がしづらく苦しい場合や体の激しい痛みがあると、なかなか寝付けずに睡眠不足に陥ります。そのほかシニア犬に見られる認知症状も、睡眠リズムの乱れや夜鳴きを引き起こします。睡眠不足が続く前に早めに異変に気づき、すぐに動物病院で検査を受けることが重要です。
寝相がいつもと異なる場合
寝ている姿がいつもと違うと感じたときも、何らかのサインかもしれません。普段以上にうなり声や激しい動きが続く場合や、寝ているのに「ハアハア」と呼吸が荒いなど、普段見かけない様子があれば病気の可能性があります。なるべく動画などで記録を残し、動物病院で相談しましょう。
快適な眠りのために飼い主ができること

愛犬の体調は、睡眠の質にも大きく左右されます。自宅でのちょっとした工夫で睡眠を整えることができるため、取り組みやすいものからぜひ始めてみましょう。
愛犬に合った寝床を選ぶ
犬は本来、狭くて囲まれた薄暗い場所に安心感を持ちやすいものです。体格に合わせたサイズのドーム型ベッドやクレートを寝床にしたり、ケージに屋根をつけるなど、周囲を囲ってあげるのもよいでしょう。
さらに体圧分散できるクッション性のあるものや、通気性の良い布地を選ぶと、長時間の睡眠でも体に負担をかけにくくなります。寝たきりの場合は、体の一点に負担がかかることで褥瘡(じょくそう:床ずれ)ができてしまうため、高反発性の介護用ベッドを選ぶのがおすすめです。
睡眠の室温と湿度を整えよう
愛犬の寝床の温度や湿度の管理も重要です。 理想的な室温は22℃前後、湿度は50〜60%程度が推奨されており、これを保つことで犬が深く安心して眠れる環境が整います。
特に寒暖差が激しい時期やエアコン使用時は、乾燥や冷えによる不調にも注意が必要です。実際に寝床の近くに温湿度計を設置すると管理がしやすくなります。冬場はベッド周辺に毛布を追加したり、夏は通気性の良いベッドや冷感マットを使うのも効果的です。
毎日の適度な運動や遊びを

日中に十分な散歩や遊びを通して体力を使うことで、ノンレム睡眠(深い眠り)の時間が増え、睡眠の質が高まると言われています。
体を動かすことでストレスも発散されやすくなり、精神的にも健康につながるため、普段から積極的に運動しましょう。小型犬は最低でも1回20〜30分、大型犬は60分程度の散歩を2回習慣にするのが適切です。犬種や年齢だけでなく、日々の体調に応じた運動量を意識してみましょう。
ベッドの衛生管理も忘れずに
ベッドが不衛生だと、かえって眠りの質が下がってしまいます。 犬は人よりも皮脂が多く抜け毛やフケも多く出るため、ベッドの繊維にダニや雑菌が繁殖しやすくなります。そのため衛生的な睡眠環境を維持するためには、週に1度の洗濯や天日干し、毛やホコリの除去を忘れずに行ってください。清潔な寝床は快適な睡眠だけでなく、皮膚病の予防や健康にもつながります。
飼い主と犬は一緒に寝るべき?

犬と一緒に寝るかどうかは、賛否が分かれるテーマです。一緒に寝ることで愛犬との絆が深まる反面、飼い主の睡眠が妨げられたり、埃やダニなどの衛生面での問題が生じやすくなります。
また、災害時やペットホテルなどに預けるとき、クレートに慣れていない犬は不安から眠れなくなる可能性もあります。基本は飼い主とは別々に眠る習慣を普段からつけておくほうが、万が一のときにも安心です。
お互いが確認できるように寝室の隣に寝床を置くなど、距離感を調整しながら、安心して寝られる環境を調整してみてください。
愛犬の睡眠を「見える化」してみよう

睡眠のリズムや質を把握するには、記録をとって可視化するのが効果的です。最近では手軽なメモだけでなく、スマートデバイスを活用した方法も広がってきています。愛犬の眠りをデータで「見える化」することで、日々の健康管理に役立ててみましょう。
日中と夜間の睡眠の記録をとる
日記アプリや手帳に「いつ寝て、どれくらい眠っていたか」「どんな寝相だったか」などを簡単にメモすることで、健康状態の傾向をつかみやすくなります。特に体調が悪いとき、獣医師に相談するうえで非常に有効な材料となります。
スマートデバイスの活用も
近年は、ペット用のスマートデバイスも進化しています。首輪型のデバイスや見守りカメラなどを活用すれば、愛犬の活動量や睡眠の質をデータで確認することができます。それにより、「最近寝る時間が短くなっている」「深夜に頻繁に動いている」といった変化を数値で見える化でき、病気の早期発見にもつながります。
愛犬の健康は良い眠りから
犬の睡眠は、健康を守るうえでとても大切なバロメーターです。年齢や犬種に応じた平均的な睡眠時間を理解して、生活リズムを整えてあげることが健康寿命にもつながります。「よく寝ているから安心」と思わず、眠りの質や行動の変化に目を向けてみましょう。きっと世界一かわいい、幸せな寝姿を見せてくれるはずです。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。