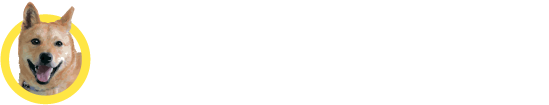犬にも花粉症はある?

花粉症とは、植物の花粉がアレルゲン(抗原)となり、体の免疫システムが過剰に反応することで発症するアレルギー疾患です。スギやブタクサ、イネなど、さまざまな植物がアレルギーの原因となります。犬にも花粉症はありますが、人でよく見られる鼻水やくしゃみなどの症状はあまり多くありません。
犬の花粉によるアレルギーの症状

花粉によるアレルギーは犬種に関わらず発症し、皮膚や耳、消化器、呼吸器などさまざまな部位に影響を及ぼします。そのため症状を早めに見つけて対策することが大切です。
皮膚や耳の症状

犬の花粉アレルギーで最も多いのが皮膚のかゆみや発疹、外耳炎です。特に目の周りや口、耳、脇や股の下、足先に症状が出やすく、掻いたり舐めたりする行動が増えます。また、耳の炎症があると強いかゆみと悪臭、耳垢が増加し、生活に支障が出ることも。花粉など環境中のアレルゲンが原因で起こる皮膚症状は、食べ物によるアレルギーと区別して、「アトピー性皮膚炎」と呼ばれる場合もあります。
【関連記事】
犬の皮膚病はうつる?皮膚トラブルの原因と治療法、予防につながるホームケアを紹介
犬の外耳炎の原因・症状・治療法は?気になるアレルギーとの関連性についても解説
下痢・嘔吐などの消化器症状
花粉が体内に入ることで、腸内の免疫バランスが崩れ、下痢や嘔吐が起こることがあります。特に、花粉の飛散量が多い時期に消化不良が続く場合、花粉アレルギーの可能性が考えられます。重症化すると血便や慢性的な下痢を伴い、脱水症状を引き起こす場合もあるため注意が必要です。

【関連記事】
もしも愛犬がおなかを下したら……下痢の原因や受診の目安、おうちでの過ごし方を解説
犬が嘔吐する原因は?自宅で様子見か病院を受診するべきか目安を解説
鼻水や咳などの呼吸器症状
犬の花粉アレルギーでは、呼吸器症状はそれほど多くありません。しかし、一部の犬では花粉の吸入による気道の刺激で咳が出たり、鼻水、喘息症状が見られることもあります。

特にフレンチ・ブルドッグやパグなどの短頭種は気道が狭く、軽い炎症でも呼吸がしづらくなるため注意が必要です。呼吸が荒くなったり、ゼーゼーと音を立てる、咳が止まらない場合は、早めの動物病院への受診が重要です。
花粉症に似たくしゃみ・鼻水の原因

犬のくしゃみや鼻水は、花粉によるアレルギー以外でもさまざまな原因によって引き起こされます。一時的な刺激によるものから、歯周病、感染症、腫瘍などの深刻な病気が関与する場合もあるため、原因をしっかりと見極めることが重要です。
歯周病・歯牙疾患
歯周病や歯の疾患が原因で、犬の鼻水やくしゃみが発生することがあります。特に上顎の第四前臼歯(奥歯の太い箇所)や犬歯の根本が感染し炎症が進行すると、鼻腔に貫通してしまうことがあります。進行すると痛みや腫れを伴い、食欲低下や口臭の悪化、顎の骨折など症状はより深刻になります。
【関連記事】犬の歯周病は放置すると危険!症状からリスク、対処法までを詳しく解説
鼻腔内感染症
犬の鼻腔内感染症は、細菌・ウイルス・真菌が原因で発症し、くしゃみや鼻水を引き起こします。特に、ケンネルコフ(犬伝染性気管気管支炎)などのウイルス感染症では、透明な鼻水が出ることが多いですが、細菌の二次感染により黄色や緑色の膿性鼻汁に変わることもあります。また真菌感染(アスペルギルス症など)では、鼻血を伴うことがあり、最悪命に関わる可能性もあります。
鼻腔内腫瘍
鼻腔内に腫瘍が発生すると、慢性的なくしゃみや鼻水から鼻づまり、ときには鼻血が生じることもあります。代表的な鼻腔内腫瘍には、腺癌(せんがん)や扁平上皮癌(へんぺいじょうひ)などがあり、高齢犬での発症が多いです。進行すると呼吸困難や顔の変形を引き起こすこともあり、命に関わることもあります。このような症状が見られた場合は、早期の検査と治療が重要です。
異物の詰まり
犬は散歩中に草むらに顔を突っ込むことが多く、植物の種や細い葉が鼻腔に入り込んで、くしゃみや鼻水が起きることがあります。異物が長期間残ると炎症が進み、膿性鼻汁や鼻血を伴うこともあるため、早めの対応が必要です。
花粉以外のアレルギーや免疫異常
花粉以外でも、環境中のハウスダスト、ダニ、カビなどは、鼻水や鼻詰まりの原因になります。また免疫異常が関与する自己免疫疾患では慢性的な炎症が続き、鼻づまりや鼻水、ひどい場合は喘息の症状や肺炎を引き起こすこともあります。その様な場合は抗ヒスタミン薬やステロイド、免疫抑制剤の投与が必要になることもあるため、症状が長引く場合は獣医師に相談しましょう。
アレルギーが疑われるときの検査

アレルギーが疑われる場合は、複数の検査を組み合わせて診断します。アトピーやアレルギーはさまざまな原因が複雑に関与しており、検査だけで確定診断することは不可能なため、症状や治療への反応を見ながら、総合的に判断することが重要です。
皮膚科検査
皮疹や脱毛など皮膚の症状に対しては、皮膚科検査を行います。皮膚掻爬検査(ひふそうはけんさ)やテープ検査、スタンプ検査などでは顕微鏡で皮膚の観察を行い、感染性皮膚炎や寄生虫感染などの有無を確認します。正確な診断のために、皮膚の一部を採取する皮膚生検により病理組織検査を行うこともあります。
アレルギー検査
花粉が関与するアレルギーの診断には血液検査(IgE検査)や皮内テストなどが有効です。血液検査では、特定の花粉やダニ、カビ、食物アレルゲンに対する抗体の有無を調べます。皮内テストは、皮膚にアレルゲンを少量注射し反応を見ることで、より正確な診断が可能です。ただし、アレルギー検査の結果は絶対的なものではないため、愛犬の症状や治療反応を見ながらの判断になります。
細菌培養検査
皮膚炎や鼻炎が続く場合は、細菌感染の可能性を考慮して細菌培養検査を行う場合があります。特に、皮膚の赤みがひどい場合や、膿が出る、鼻水が黄色や緑色の場合は、細菌感染の疑いが高いです。培養検査では感染源となる細菌を特定し、適切な抗生物質を選択することができます。
レントゲン検査
慢性的な鼻水、くしゃみなどが見られる場合、レントゲン検査で鼻腔や気道を確認する場合があります。レントゲン検査では、肺や気管支の異常、鼻腔内の炎症や腫瘍の有無をコントラストの違いで確認します。しかし、病変が小さい場合やほかの臓器と重なっている場合は、レントゲン検査だけでの確定診断は困難なため、より詳細な検査が必要です。
気管支内視鏡やCT検査
より詳細に鼻腔内や気道内部を調べる場合、内視鏡検査やCT検査を行います。これらの検査は高度な設備が必要なため、大学病院や専門病院で実施する機会が多いです。内視鏡検査は特殊な細い内視鏡を利用して、鼻の裏側や気道内部を確認します。CT検査では鼻腔や気管、肺などの断面像を撮影して、レントゲンではわかりにくい些細な異常を確認できるのが強みです。原因を特定し、より効果的な治療が可能になります。
花粉が関与するアレルギーの治療
花粉によるアレルギー治療は、免疫の過剰な反応や炎症を抑えたり、皮膚のバリア機能を強化する治療がメインで行われます。アレルギー疾患は完治が難しく、症状の程度に応じて時間をかけた管理が必要ですが、適切な治療で症状を落ち着かせ、普段通りの生活を送ることができます。
内服薬や注射薬での治療
アレルギーの治療では、主に炎症とかゆみを抑える薬を使用します。かゆみを抑える薬はどれも作用の仕方が若干異なるため、症状に合わせて使い分けることが重要です。ステロイドや、かゆみが伝わるシグナルを抑えるアポキルという薬を使用するほか、抗ヒスタミン薬や免疫抑制剤を併用する場合もあります。

同じくかゆみを抑える「サイトポイント」という注射薬は、子犬を含め幅広い年齢で使用できるうえ、効果が1カ月も持続するため、毎日の内服が難しい場合でも対処可能です。かかりつけ医と相談しながら、投与頻度や薬の種類を決めていきましょう。
局所的な場合は外用薬の使用も
限られた場所で症状が見られる場合は、外用薬が効果的です。ステロイド入りの軟膏や抗菌薬配合の外用薬は、炎症や感染を抑える役割があります。かゆみが強いときには、ローションやクリームを内服薬と併用するのも有効です。

食事療法による皮膚のケア
皮膚のバリア機能を強化するためには、栄養バランスのとれた食事が何よりも不可欠です。アトピー性皮膚炎の犬は、食物アレルギーを同時に併発している場合もあり、愛犬にとってアレルゲンを含まないフードを選ぶ必要があります。

動物病院で取り扱っている療法食は皮膚への栄養バランスが整っているだけでなく、アレルギーの原因となりやすい成分を排除しているものが多いです。食事を変更するだけで、皮膚の機能が向上して、痒みや脱毛などの症状が軽減する場合もあるため、相談した上で一度検討してみてはいかがでしょうか。
自宅でできる花粉対策

花粉シーズンには、普段の生活から花粉への接種を減らし、皮膚のバリア機能を高める対策が重要です。お散歩の際は服の着用でなるべく花粉が毛につかないように配慮したり、帰宅後は、体を拭き、ブラッシングをして花粉を落とすよう意識しましょう。
シャンプーは、肌に優しい成分で保湿力の高いものを選び、2週間に1回程度のシャンプーを行うと毛や皮膚に付着した花粉を除去できます。また、こまめな室内の清掃や空気清浄機を用いて、室内の花粉の飛散を防ぐことも欠かせません。
飼い主の衣服や靴に付着した花粉はなるべく玄関で脱ぎ、部屋の中には入れない工夫なども効果的です。このような対策は愛犬だけでなく、ご家族の花粉症対策にも非常に有効です。ぜひ取り組みやすいものから始めてみてください。
花粉の時期を快適に過ごすために
春は暖かくなりお散歩が楽しい季節ですが、花粉のアレルギーを持つ愛犬にはちょっとつらい時期でもあります。しかし、適切な治療や生活環境の工夫をすることで、症状を和らげ元気に春を楽しむことができます。ぜひ今回の記事を参考に、早めの対策を始めてみてください。少しずつできることを積み重ねて、愛犬と一緒に心地よい春を迎えましょう!
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。