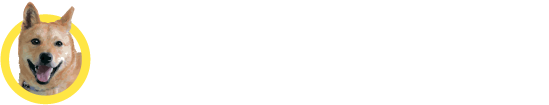「最近愛犬の口が臭い…」と感じたことはありませんか?実はその口臭、歯周病や内臓の病気のサインかもしれません。本記事では、犬の口臭の原因や注意すべきにおいの特徴から、自宅でできる予防方法までわかりやすく解説します。お口のケアをしっかり行い、病気知らずの健康的な歯を維持しましょう。
犬の口臭は実は病気のサインかも
犬の口臭はただのにおいではなく、重大な病気のサインであることが少なくありません。特に歯周病はその代表例で、3歳以上の犬の約8割が罹患しているともいわれています(*)。また、口臭の種類によっては、内臓機能の異常が原因のケースもあります。だからこそ、飼い主がいち早く異変を捉える意識が重要です。
*)参照:WSAVA 2017年ガイドライン
犬の口臭の主な原因

犬の口臭は、単に食べ物のにおいだけではなく、体調や環境など複数の要因によって発生します。
食べ物や生活習慣の影響
口臭の原因のひとつとして、飼育環境や習慣があげられます。古いフードや嗜好性の強い食材を頻繁に与えていると、口の中に残った成分が悪臭の原因になることがあります。
また、食糞(うんちを食べてしまうこと)の習慣も口臭悪化につながります。こうしたにおいは病気ではありませんが、後に体のトラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。
乾燥など口内環境の変化
口の中は通常唾液で潤っていますが、水分不足や開口呼吸が続くことで口の中が乾燥し、口臭の原因になります。放置すると歯周病や感染へと進行するリスクが高まるため、油断は禁物です。
ストレスや年齢などの生理的変化
ストレスを感じると交感神経が優位になり、唾液の分泌が減少します。唾液量が減ると口が乾燥して雑菌が繁殖し、においを発する原因に。また、加齢などで唾液の分泌量が減ることも問題です。愛犬の年齢や性格を考慮し、異常を感じ取ることが、病気の早期発見につながります。
口の中の炎症や疾患
犬の口臭の中でも特に危険なのが、歯周病や腫瘍など病気によるにおいです。歯垢(食べカス)が細菌の塊となり、やがて歯石に変化して歯茎に炎症を引き起こします。これを放置すると、出血や骨の破壊、組織の壊死といった深刻な症状へ進行します。
さらに、悪性腫瘍が口の中に発生した場合には、進行すると口のにおい以外にも食欲低下や出血、発熱など全身の異常に発展することもあります。
注意するべき口臭の種類

犬の口臭にはさまざまな種類があり、においの質によって体内で起きている異常の種類を推測できることがあります。ここでは6つのにおいのタイプと、関連する疾患の可能性について解説します。
魚のような生臭いにおい
魚を焼いた後のような「生臭さ」を感じる口臭は、口の中の乾燥が関係している可能性があります。犬は通常、唾液によって口の中の細菌を洗い流し、においの原因物質を抑えています。しかし、水分不足や開口呼吸の増加によって口の中が乾燥すると唾液の粘度が高くなり、においが凝縮されやすくなります。この結果、特有の「魚のようなにおい」が発生することがあります。
また、慢性的にこのにおいが続く場合に、鼻炎など呼吸器トラブルが隠れていることもあるため、注意が必要です。
ドブやうんちのようなにおい
「下水道」や「便」のような悪臭の場合、腸の疾患や食糞癖が関係している可能性があります。腸でトラブルが起こると、腸内のガスや内容物のにおいが口から発散され、強烈な便のにおいが生じやすくなります。食糞や便秘のほか、腸閉塞や腸捻転などの命に関わる緊急疾患などでも似た臭いが生じるため、違和感を感じたらすぐに動物病院を受診しましょう。
甘酸っぱいにおい
甘くて酸っぱいにおいがする場合、糖尿病が疑われるケースがあります。これは体内で脂肪が分解される過程で生じる「アセトン」という物質が原因です。進行すると多飲多尿や食欲の低下、意識障害など命に関わる場合もあるので、見逃さないよう注意が必要です。
アンモニア臭
「ツンとした刺激臭」のアンモニア臭がする場合、腎臓や肝臓の機能低下が疑われます。肝臓や腎臓は体内の老廃物を処理し、尿や胆汁中に排泄するという解毒作用を持っています。これら機能が衰えると処理しきれない老廃物が体中に蓄積し、においとして排出されるのです。
酸っぱいにおい
「ツンとした酸味のあるにおい」は、胃の不調や胃酸過多の原因が考えられます。犬の胃は、食べ物を消化するために強い酸を分泌しますが、過剰に分泌されると胃粘膜が荒れ、胃炎や逆流性食道炎といった症状が現れます。このとき胃酸が逆流して口の中に達すると、酸っぱいにおいを放つことがあります。
生ゴミのような腐敗臭
「腐った肉」や「生ゴミ」のようなにおいは、重度の口腔内疾患が原因であることが多いです。歯周病は、歯垢(食べカス)に含まれる細菌が歯茎に炎症を起こし、出血や膿を伴って進行する病気です。また、口の中に発生した悪性腫瘍も同様の腐敗臭を伴うことがあり、早期の対応が求められます。
口臭が発生しやすい病気

口臭の悪化は、体のどこかに異常が起きているサインです。原因となりやすい病気やメカニズムを知っておくことで、口臭から病気をいち早く見抜く手がかりになります。
歯周病
犬の口臭の原因で最も多いのが歯周病です。これは歯垢(食べカス)に含まれる細菌が歯肉に炎症を引き起こし、やがて歯槽骨(しそうこつ:歯を支える骨)を破壊してしまう病気です。歯周病は細菌感染症の一種で、炎症が血管を通じて腎臓や心臓など全身の臓器に広がるリスクもあるため、決して口だけの問題と考えないことが重要です。
【関連記事】犬の歯周病は放置すると危険!症状からリスク、対処法までを詳しく解説
口内炎
口の中の粘膜が赤く腫れたり、ただれたりする口内炎も、強い口臭の原因になります。ウイルス感染、免疫異常、ストレス、口のケガなどが主な原因です。慢性化すると治療が難しくなるため、早期発見と診断が重要です。
口腔内腫瘍
悪性腫瘍が口の中にできると、血や膿がにじみ出て腐敗臭のような強いにおいを放つことがあります。特に「悪性黒色腫(あくせいこくしょくしゅ)」「扁平上皮癌(へんぺいじょうひがん)」などの犬に多い腫瘍は、痛みや出血、よだれ、食欲不振を伴うことがあり、急速に進行するケースも少なくありません。異常なにおいが続く場合には、速やかに病院での検査を受けるべきです。
内臓疾患
口臭と内臓疾患の関連性は見過ごされがちですが、実は深い繋がりがあります。腎不全ではアンモニア臭、糖尿病ではアセトン臭が、胃腸疾患では酸っぱい胃酸のにおいが生じることもあります。これらは全身の問題で、命に関わるケースも多いため油断はできません。
動物病院へ行くべき口の症状
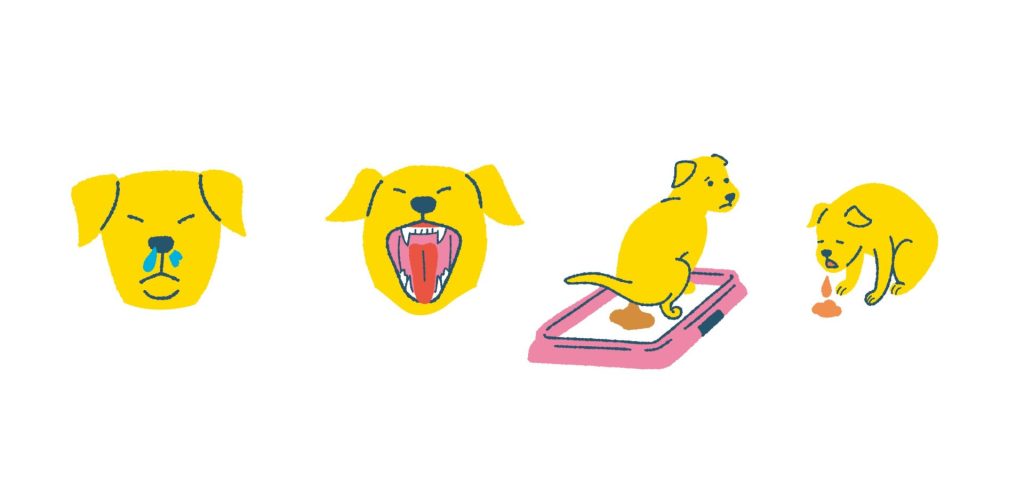
犬の口臭に気づいても、どのタイミングで病院を受診すべきか悩む方も多いでしょう。ここでは見逃してはいけない具体的な症状を紹介します。
強い異臭がある
においが以前よりも悪化していたり、明らかに強いと感じた場合、重篤な口腔疾患や内臓障害が進行しているサインかもしれません。病気が原因だった場合はにおいが自然に消えることはほとんどありません。違和感を覚えた時点で早めに動物病院で相談しましょう。
口からの出血やよだれ・クシャミ
口からの出血や、普段以上に多いよだれが見られた場合は、歯周病の重症化や腫瘍、口内炎などが疑われます。また、クシャミの増加も歯周病と深い関連があるため、口臭とともにクシャミが増えた場合は歯周病の悪化に注意しましょう。
ほかの症状を伴うとき
口臭に加えて、食欲や元気がなくなるなどほかの症状がある場合も注意が必要です。特に内臓疾患の場合は、口臭以外にも下痢や嘔吐、多飲多尿などさまざまな症状がみられます。気になる症状が見られたら、自己判断せず診察を受けるのが安心です。
今日からできる愛犬の口臭対策!

犬の口臭は、早期発見と早期対応によって多くが改善できます。病気ではない場合も習慣次第でにおいの軽減が可能です。ここでは、家庭で手軽に取り組める方法をご紹介します。
毎日のお口チェック
愛犬とのスキンシップの際、口元を軽く開いて歯茎の色や出血、においの変化をチェックするだけでも、異常の早期発見につながります。出血がないか、歯の色が黒くなったり欠けていないか、できものがないかも注意して観察しましょう。
こまめな歯磨きを
犬の口臭対策の基本はやはり日常的な歯磨きです。歯垢は2〜3日で歯石に変わるため、できれば毎日、最低でも週に数回のブラッシングが推奨されます。歯ブラシはペット専用のものを使用し、ブラシが苦手な子はシートタイプなど性格に合った種類を選んであげましょう。
デンタルケアグッズの活用
歯ブラシが苦手な犬は、デンタルグッズの活用が効果的です。たとえば、歯石除去効果のあるデンタルガム、飲み水に添加する口内洗浄液、消化酵素入りのサプリメントなど。市販品は成分や効果が異なるため、獣医師と相談のうえ、愛犬の状態に合った製品を選ぶことが大切です。こうしたグッズは、歯磨きとの併用でさらなる口臭予防効果が期待できます。
定期的に歯科健診へ
日々のデンタルケアを行っていても、自宅だけでは確認しきれない口の中のトラブルがあるのも事実です。特に犬は痛みや違和感をうまく伝えることができないため、病気を見落とすケースも少なくありません。そのため、半年に1回程度の歯科健診を受けることをおすすめします。
獣医師による口の中チェックやレントゲン検査によって、肉眼では確認できない異常や初期症状を早期発見することが可能です。さらに、歯石除去や歯肉の炎症ケアなど、必要に応じた専門的な処置を受けることで、将来の大きな病気の予防にもつながります。
愛犬の健康はお口のケアから
犬の口臭は単なる「におい」ではありません。ときに体内で進行する病気のサインになり、見逃せば命に関わる重大な疾患に発展することもあります。しかし、毎日のお口チェックや歯磨き、そして定期的な健診を行うことで、多くのトラブルを未然に防ぐことが可能です。口は体のさまざまな部分に影響する大切な部位。 今日から始められるケアを習慣にし、大切な家族である愛犬の健康を守っていきましょう。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。