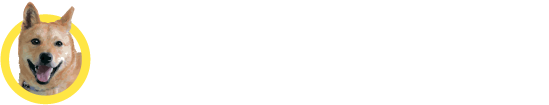「誰かの犬」

「小さいときはきっと可愛かったんだろうな」
保護犬を引き取ってしばらくすると、ぼくはついそんなことを口にしてしまう。ソファで丸くなっている愛犬、タロウの頭を撫でながら、あるいは散歩道で楽しそうに草の匂いを嗅ぎまわっている後ろ姿を見つめながら。
新しい家族を迎える喜びと同時に、どうしても気になってしまうのが、この子の過去だ。いったい、どんな場所で、どんな人たちと、どうやって生きてきたのだろう、と。
「保護犬」と呼ばれる前に、「誰かの犬」だった過去。
夜、静まり返ったリビングで、タロウがふいに身を震わせ、小さな唸り声をあげる瞬間がある。それは雷の音でも、外を通る車の音でもない。目には見えない、しかし確かに彼らの心に触れる何か。
「もしかして、昔に何かあったのかな」
その光景を見て、飼い主(ぼく)の想像力はとめどなく膨らんでいく。
宇宙からの侵略者

なにかに怯える様子を見たとき、ぼくは全力で「そのもの」と愛犬が出会わないよう、神経を張り巡らせる。タロウはどういうわけか、工事現場で使われるオレンジ色の安全ベストに異様なほど怯える。道端で作業員さんが着ているのを見つけると、文字通り一瞬で地面に張り付いて、目を合わせようとしない。まるで、ベストが宇宙からの侵略者であるかのように。
ぼくは勝手に「タロウのトラウマ・ベスト」と名づけ、散歩のルートからベスト着用率の高い場所を外すという、まるでスパイのエージェントのような警戒態勢を敷くのだった。誰も見ていないから、ついブツブツとタロウに状況説明をしてしまう。
「いいか、タロウ。今日はこの裏道を通る。敵(オレンジベスト)の影はない。でも油断するなよ」
この、特定のなにかに怯えるところを見て、想像を膨らませるという行為は、引き取った飼い主特有の切なくも微笑ましい儀式のようなものだ。
過去への郷愁

ある日、カフェのテラス席で一緒に休憩していると、少し離れた席に座った、穏やかな笑顔のおじいさんがいた。タロウはいつもはカフェでは大人しく伏せているのだが、その時ばかりは、クンクンと鼻を鳴らし、しっぽを控えめに振って、そのおじいさんをじっと見つめ続けたのだ。
「え、タロウ? どうしたの?」
ぼくは内心、ドキドキした。もしかして昔飼っていた人に似ているとか…あるいはその人そのものだったりして…いやいや、でもはたしてタロウにはいったいどんな過去があるのだろうか。
タロウはちらりとぼくに目を向け、再びそのおじいさんに視線を戻す。その瞳には、懐かしさ、戸惑い、そして少しの期待のようなものが入り混じっているように見えた。
ぼくは一瞬、胸が締めつけられるような気がした。
もしかしたら、タロウは、過去の日々と今の状態を比較しているのかもしれない。犬という動物も、郷愁のようなものを感じながら過去を思い出すこともあるのだろうか?
しかし、その緊張と感傷は一瞬で霧散した。
おじいさんが席を立ってタロウの横を通り過ぎる際、タロウは立ち上がり、思いっきりしっぽを振って「撫でて!」とばかりに頭を差し出したのだ。おじいさんは笑って、タロウをひと撫でしてくれた。
そして、おじいさんが去ったあと、タロウは満足そうに、カフェのお姉さんが持ってきたビスケットを、目を輝かせて食べ始めた。
そう、タロウは、過去の誰かを思い出していたのではない。
彼は単に、「この人はやさしそうだから、撫でてくれるかも。もしかしたら美味しいものをくれるかも」という、極めて「今」に特化した本能に従って行動しただけなのだ。
過去への郷愁なんて、たぶん1ミリもない。あったとしても、目の前のビスケット一個ぶんの価値もないのだ。
過去とは、ただの過ぎ去った世界

この出来事をきっかけに、ぼくの考えは大きく変わった。
ぼくたちは、つい、過去と現在を因果関係で結びつけようとしてしまう。それは、人間が持つ「物語」を求める性(さが)であり、愛する存在への「同情」という名のやさしさでもあるだろう。
けれど、彼ら犬たちにとってはどうか。
いや、むしろタロウにとって過去とは、ただの過ぎ去った世界なのではないか。
タロウが怯えるオレンジ色のベストだって、過去の悲しい記憶からきているのかもしれない。けれども、それ以上に彼は今、リビングに差し込む日差しや、新しいおもちゃ、そしてぼくの顔色なんかもあわせて、全身全霊で集中している。
ごはんの時間には、まるでこの世界でいちばんの幸せ者であることを見せつけるようなダンスを踊る。散歩の準備を始めれば、しっぽが取れるのではないかというほどのフルスイングで喜びを表現する。
そこには、過去の悲しみや、未来への不安など、微塵もない。あるのは、今この瞬間の、喜びと生命力だけだ。ぼくがちょっと寝坊してごはんがすこし遅れた日には全身で抗議の念を送りつけてくる。過去に腹を空かせていた日がどうだったかなんて、彼はたぶん、きれいさっぱり忘れている。
まっすぐに生をまっとうしようとすること

ぼくらは「過去の清算」や「トラウマの克服」といった、まるでドラマのようなストーリーを彼らに期待しすぎてしまう。でも、それは実は彼らの問題でもなく、彼らの物語でもない。
犬たちは、過去を教訓や思い出として脳内で整理する、という複雑な認知活動はしない。彼らにとって、過去の出来事からくる感情の残り香は、現在の行動に影響を与えるかもしれないが、その感情そのものに「過去」というレッテルを貼って保存はしない。
人間のそばにいる動物で、今を生きる、ということがこれほど似合うのは犬だよなあ、と心底思う。
こんなにもまっすぐに生をまっとうしようとすることに、憧れてしまうほど。
ぼくは過去の失敗を悔やみ、仕事の不安に怯える。「タロウのトラウマ・ベスト」を避けようと躍起になっているぼくこそが、過去と未来に縛られている人間だ。しかし、タロウはベストから逃げおおせた瞬間、さっと頭を切り替え、目の前の散歩道を全力で楽しむのだ。
その瞬間、「おいおい、さっきまで死ぬほど怯えてたのはどこの誰だよ」と、思わずタロウの顔を覗き込み、くすっと笑ってしまう。彼はまったく気にしていない。
日差しのもとへ連れて行く

保護犬を引き取るということは、その子の過去を丸ごと引き受けること、だと言われる。それは間違いない。
しかし、その過去を掘り起こして詮索することなどない。ぼくらがすべきことはただひとつ。
過去に何かがあったとして、それが暗い影を落とすのなら、日差しのもとに連れて行くのが飼い主のつとめだということだ。
その影が、オレンジ色のベストの形をしていようと、大きな物音のかたちをしていようと関係ない。
「大丈夫だよ。ここは安全だよ。ぼくがいるからね」
タロウを抱きしめながらそう語りかける。
この子が心の底から楽しい、うれしい、と感じる瞬間を、ひとつでも多く提供し続けること。
タロウにとって「今」とは、ぼくの膝の上、美味しいビスケットの味、公園の芝生の匂い、そして何より、「毎日、この人(ぼく)と一緒にいられる」という確かな安心感だ。
過去の暗い部屋の扉は、もう、タロウ自身が自らの意志で閉めている。ぼくら飼い主は、その扉の鍵を探す必要はない。ぼくらがすべきなのは、リビングの窓を大きく開け、燦々と光を迎え入れることだ。そして、その光の中で、タロウが最高の笑顔を見せてくれたら、それで十分。
一緒に生きる、というのはそういうことなのだろう。
保護犬の過去は、ミステリー小説のように興味をそそる。けれども、その最終章はいつも、「今」という、温かい現実で上書きされていく。そして、その現実こそが、何よりも尊い物語なのだ。
文と写真:秋月信彦
某ペット雑誌の編集長。犬たちのことを考えれば考えるほど、わりと正しく生きられそう…なんて思う、
ペットメディアにかかわってだいぶ経つ犬メロおじさんです。 ようするに犬にメロメロで、
どんな子もかわいいよねーという話をたくさんしたいだけなのかもしれない。
▽ ワンコを幸せにするために「ワンだふるサポーター」でご支援お願いします。▽