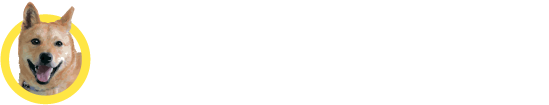「仕事から帰ると、犬が家の中をめちゃくちゃにしている」
「留守番をさせると、トイレ以外の場所に下痢をしている」
「ちょっと姿が見えなくなっただけで大騒ぎするから、気が休まらない」
これらは、犬の分離不安症にお悩みの飼い主からよく聞かれる言葉です。犬は飼い主への愛情がとても深く、飼い主と離れることに強い不安を感じると、体や行動にSOSのサインが現れます。症状がひどいときには、薬の服用やトレーニングでの適切な対処が必要になります。
この記事では、分離不安症の症状や原因、診断、家庭でできるトレーニングを獣医師がわかりやすくお伝えします。愛犬の分離不安症に悩む方の心が少し軽くなるヒントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
犬の分離不安症は不安障害のひとつ

犬の分離不安症は、血液検査やレントゲンなどの一般的な検査では異常が見つからないことがほとんどです。そのため、身体的な病気というよりも、ストレスが引き金となる「不安障害」のひとつと考えられています。
分離不安症の発症には、経験や環境が影響する
分離不安症の発症には、以下のようなトラウマや過酷な経験、生活環境が大きく影響します。一方、犬種や年齢、しつけの影響はそれほどないと言われています。
- 野良犬生活を経て、保護された
- 劣悪な環境で飼育されていた
- 飼い主が何度も変わり、人と信頼関係を築けなかった
- 飼い主との急な別れを経験した
- 急に長時間の留守番を任されるようになった
犬の性格もある程度関係する
たとえば、以下のような性格の犬は、分離不安症になりやすい傾向があります。
- 飼い主への依存心が強い
- 怖がりで神経質
- 刺激に過敏に反応しやすい
ただし、普段は楽観的な性格の犬であっても、不安定な状況が続けば分離不安症を発症することもあります。
子犬期の社会化不足が原因のことも

犬の社会化とは、人や犬、環境に慣れさせて、不安なことや初めてのことにもストレスなく適応できる力を育てることです。生後2〜3ヵ月齢の好奇心旺盛な時期に、人や犬、音、物などさまざまな刺激に少しずつ慣れさせることが大切です。
社会化が不十分な犬は、知らない人や音に極度に怯えたり、攻撃的になったりすることがあり、不安な状況にうまく対処できません。その結果、“安心”を与えてくれる飼い主への依存が高まり、分離不安症を引き起こすことがあります。
分離不安症の主な症状

分離不安症の代表的な症状は以下のとおりです。
問題行動
- 無駄吠え
- ケージやクッションなどをかじったり壊したりする
- 後追い
- 脱走を試みる
- トイレの失敗
- 前足やしっぽを強く舐め続けたり、噛んだりする自傷行為
- 飼い主の帰宅時に過剰に興奮する
体の不調
- 嘔吐や下痢
- 元気や食欲がなくなる
重症のケースでは、飼い主が出かけるのを察知しただけで落ち着かなくなったり、自宅にいても姿が見えなくなるだけで症状が現れたりすることもあります。
環境が変わってすぐの症状は一時的なことが多い
新しい飼い主の元に来てすぐの頃や、家族構成の変化など、環境が大きく変わった直後に分離不安の症状が出ることもあります。
このようなケースでは、犬の不安な気持ちをしっかり受け止めて、新たな信頼関係を構築することに努めましょう。時間が経ち、新しい環境に慣れると症状が落ち着くことが多いです。
動物病院での診断と治療

分離不安症の診察の流れと治療方法を解説します。
問題行動の動画を用意する
分離不安症の診断には、以下のような情報がとても重要です。また、実際に問題行動をしているときの動画があると診断の助けになります。
- いつから・どのような症状があるか
- 症状が出るタイミング(飼い主の外出前、外出中、帰宅時、在宅時など)
- 頻度や継続時間
- 犬の経歴や性格
- 飼育環境
気になる行動には、体の不調や病気が原因である場合も
一見すると分離不安症に見える行動でも、実際には身体の不調や加齢に伴う病気が原因であることがあります。
- 自傷行為→皮膚炎や痛み、不快感
- 排泄の失敗→泌尿器系や消化器系のトラブル
- 吠え続ける→認知症の可能性
いつもと様子が違うと感じたときは、しつけやトレーニングの前に一度動物病院で相談してみましょう。
治療はトレーニングが主で、薬は補助的
治療が必要と判断されるのは、症状が頻回で程度が激しく、飼い主や犬自身の心身に負担がかかっているケースです。
治療の基本はトレーニングです。重度の分離不安症では、抗うつ薬や抗不安薬が使用されることもありますが、薬はあくまでも補助的に使用して、犬がトレーニングを通じ自立して過ごせるようになることが大事です。
おうちでできる分離不安症のトレーニング

分離不安症の改善には、家庭でのトレーニングがとても重要です。軽度のケースでは、トレーニングだけで改善することも多くあります。
トレーニング①:不安のきっかけを和らげる
たとえば「バッグを持つ」「鍵の音がする」「靴を履く」など日常の動作が、犬にとって不安な気持ちの引き金になることがあります。
- バッグや鍵を持ってもすぐに置く
- 靴を履いてもすぐに脱ぐ
など、日常動作=外出とは限らないことを覚えさせましょう。
トレーニング②:短時間からの留守番練習
最初は10秒間だけ隣の部屋に行って戻る、という程度で構いません。戻ってきたら大げさに褒めたりせず、あくまで普段通りに対応します。
慣れてきたら、30秒、5分、10分・・・と留守番の時間を延ばしていきましょう。ポイントは「犬が吠える前に切り上げる」こと。成功体験を積ませるのがコツです。
留守番の間に楽しめるものを用意する

知育玩具などを活用し、留守番を退屈な時間から1人遊びを楽しむ時間に変えていきます。飼い主が在宅中にも同じおもちゃで遊び、留守番=特別にならないようにしましょう。
出かける前・帰宅時は淡々と
外出前や帰宅時に過度なスキンシップや声掛けは控えましょう。帰宅時に犬が興奮している場合は、落ち着くまで距離を取って待ちます。こうすることで、留守番は特別なイベントではないと犬が感じられるようになります。
飼い主自身の心のケアも大切

分離不安症の犬と暮らす飼い主のなかには「犬のためにがんばりたい」という気持ちと「自分が辛い」という気持ちの間で揺れている方が多くいらっしゃいます。
ここでは、飼い主の方のストレスを和らげるためのヒントを紹介します。
罪悪感とどう向き合うか

犬に深い愛情があるからこそ罪悪感を感じてしまうものです。
しかし「愛情=ずっと一緒にいること」ではありません。犬がひとりで過ごせる力を身につけることも大事なしつけのひとつといえます。
後追いに疲れたときは
トイレや洗濯など、ちょっとした家事のタイミングであえて犬に声を掛けないようにしてみましょう。
いちいち声を掛けることで、犬は飼い主の不在に敏感になり、後追いを強めてしまうこともあります。少しずつ、一緒にいなくても大丈夫と教えてあげましょう。
自分の時間を大切に

飼い主自身の心に余裕がなくなってしまうと犬に注ぐ愛情も少なくなってしまいます。信頼できるトレーナーや動物病院に犬を預けて、1人の時間をとるようにしましょう。
まとめ
この記事では、犬の分離不安症について、発症の原因や症状、動物病院での診断と治療方法、家庭でできるトレーニングを解説しました。
分離不安症は、犬が飼い主と離れることに強い不安を感じ、問題行動や体の不調を起こす不安障害の一種です。発症は、過去の経験や環境が大きく関わっており、育て方やしつけの失敗ではありません。重症例では薬を飲むこともありますが、トレーニングを行うことが治療の基本です。
犬が「ひとりでいても大丈夫」と自信を持てるように教えていくことが分離不安症改善のポイントです。焦らず少しずつ進んでいきましょう。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。