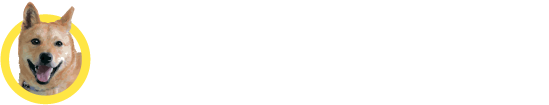愛犬が足先を舐めている……よく見たら擦り傷が!そのような経験をしたことはありませんか?散歩中のちょっとしたケガや床との摩擦など、犬の擦り傷は日常的に起こりやすいものです。この記事では、犬の擦り傷に気づいたときの正しい応急処置や、皮膚トラブルとの見極め方、舐め癖の対策や予防方法について詳しく解説します。万が一の愛犬のケガもすぐに直してあげましょう。
愛犬の擦り傷とは

擦り傷は、皮膚の表面がこすれて傷ついた状態のことをいいます。散歩中の転倒や室内での摩擦、ほかの動物との接触など、日常のちょっとした出来事が原因で生じやすいケガのひとつです。
軽い傷なら様子をみていい?
簡単な擦り傷でも、安易に放置するのはよくありません。放置したことで、より重症化してしまうケースもあるため、自宅でもしっかりと手当をすることが重要です。
さらに、傷ができた原因がケガではなく皮膚病や感染症だった場合は、様子を見るだけでは根本的な治療にならず、長引いたり悪化してしまいます。時には命に関わるケースもあるため、症状が悪化する前に獣医師に相談するとよいでしょう。
傷を見つけたらまずすべき応急処置

犬の擦り傷を見つけたとき、飼い主が冷静に応急処置を行うことが、重症化を防ぐうえで大切なポイントです。
清潔な流水でやさしく洗い流す
擦り傷の処置で最初に必要なのが、患部の洗浄です。 傷口についた汚れや細菌を取り除くことで、感染の予防につながります。ぬるま湯で、傷口をやさしく洗い流しましょう。シャワーの水圧が強すぎると皮膚への刺激になるため、強い場合はペットボトルなどを使って少しずつ流すとよいでしょう。
出血がほとんどない小さな擦り傷の場合は、洗浄のみで十分なケースも多く、無理に消毒液や石けんを使う必要はありません。逆に、石けんなどの強い刺激を受けると皮膚を傷め、治癒が遅れるおそれがあります。洗い流したあとは、患部を軽く押さえて水分を拭き取ってあげましょう。
毛が絡まないようにする
患部に周囲の被毛がこびりついている場合は、感染や刺激の原因になってしまいます。そのため傷に毛が絡まないようにかき分けてよけたり、場合によっては傷に干渉させないためやさしく切り取る必要があります。
毛が傷口に触れると、感染しやすいだけでなく、痛みの原因になることもあります。可能であれば、動物病院で処置してもらうとより安全です。
出血していたら、清潔な布で圧迫止血
出血がある場合は、清潔なガーゼや布で軽く圧迫し、止血を行いましょう。擦り傷の場合、通常は軽い出血で済みますが、血管が多い箇所だと出血量が多くなることもあります。
強く押さえすぎず、通常5分程度圧迫すれば出血が止まります。ただし、出血がなかなか止まらない場合や広い範囲に傷がある場合は、すぐに動物病院を受診してください。出血の程度に応じて外用薬や内服薬を用いて止血を行います。
症状が重度ならすぐに動物病院へ
患部が腫れている、膿(うみ)が出ている、あるいは重度の傷や強い痛みがある場合は、早急に動物病院での診察が必要です。擦り傷の悪化によって炎症が広がると、通常の自宅ケアでは対応できなくなることがあります。
特に、肉球や関節の周辺など、動かすことが多い部位の擦り傷は悪化しやすいため要注意です。傷口の色やにおいなどの変化も、細菌感染の兆候のひとつです。少しでも異変を感じたら、迷わず獣医師に相談しましょう。
応急処置時に避けたいNG行動

応急処置は重要ですが、誤った方法は患部に刺激を与えたり細菌の繁殖を促してしまうおそれがあります。ここでは、やってしまいがちなNG行動とそのリスクについて解説します。
人間用の薬は使わない
市販の外用薬やステロイド、抗生剤軟膏などは、犬にとって強すぎたり成分が適さない場合があります。犬の皮膚は人間よりも薄くデリケートで、成分が過剰に吸収されると、副作用が出るおそれもあるため注意が必要です。
また、犬が薬を舐めてしまうことで中毒や胃腸障害などを引き起こすリスクもあるので、自己判断での使用は絶対に避けましょう。使う前に、必ず獣医師に相談のうえ適切な処置を行ってください。
アルコール消毒は刺激が強く逆効果
犬の皮膚にアルコールを使用すると、強い刺激によって痛みや炎症を引き起こす可能性があります。また、アルコールは皮膚の細胞も傷つけてしまうため、再生や治癒に必要な組織の修復を妨げることもあります。傷が軽度の場合、動物病院で処方された消毒薬がある場合を除き、基本的には流水での洗浄のみで十分です。
ガーゼで覆うと治りが遅くなる場合も

人でよく使う絆創膏(ばんそうこう)やガーゼ、ドレッシング材(創傷被覆材)などは、傷の状態によっては好ましくない場合があります。創傷被覆材は、傷の状態で小まめに使い分ける必要があり、誤った使い方をしてしまうと、傷の治りが遅くなってしまうためです。
細菌が感染している場合にドレッシング材などを使用すると、細菌が閉じ込められ感染が広がってしまうため危険です。また、ガーゼは出血や滲出液(しんしゅつえき)の量が多いときは有効ですが、体からの大切な滲出液を吸収しすぎたり、かさぶたと癒着してしまい新たな皮膚細胞を傷つけてしまう可能性もあります。
そのため大きな傷の場合は、動物病院で治療を行うことを強くおすすめします。傷の舐め防止などでどうしてもカバーする必要がある場合は、エリザベスカラーを用いたり、動物用の通気性がある保護パッドや包帯を使用して、こまめに交換して衛生的に保つことが重要です。
かさぶたは無理に剥がすと逆効果に?
かさぶたは、傷口を守る自然なふたのようなものです。 無理に剥がすと、下で形成されつつある新しい皮膚(表皮細胞)が傷つき、治癒が遅れたり再び出血することがあります。また、犬が舐めて自分でかさぶたを取ってしまうと、細菌感染や皮膚炎につながることもあるため、無理に刺激せずに自然に剥がれるのを待ちましょう。
犬が足を舐める理由

犬が足をしきりに舐めている場合、擦り傷だけでなくさまざまな原因が考えられます。舐める行為は癖ではなく、痛みやかゆみ、不快感や不安などからくるサインかもしれません。ここでは、代表的な原因を4つに分けて紹介します。
ケガによるもの
犬は、擦り傷や打撲、刺さり傷など、物理的なケガが原因で舐める行為をすることがあります。 傷口を舐めることで痛みを紛らわせようとするのは犬の自然な行動ですが、舐め続けることで症状が悪化する危険性もあります。ぶつかったり転倒するなどのアクシデントが起こった場合は、目立たなくても傷が出来ていないかチェックしてあげましょう。
皮膚病によるもの
アレルギー性皮膚炎や膿皮症、マラセチア性皮膚炎などの皮膚病が生じた場合も、体を舐める原因になります。皮膚病はかゆみや赤みを伴う症状が多く、犬は違和感を感じて体を舐める場合が多いです。
特にアレルギーが関与した皮膚炎は長期間の治療が必要になることもあります。繰り返し同じ場所を舐めている、皮膚が赤く腫れている、脱毛などの症状がある場合は、皮膚病の可能性も視野に入れて動物病院を受診しましょう。
【関連記事】犬の皮膚病はうつる?皮膚トラブルの原因と治療法、予防につながるホームケアを紹介【獣医師監修】
寄生虫などの感染
ノミ・ダニ・疥癬(かいせん)など寄生虫の存在も、強いかゆみや不快感を引き起こします。寄生虫による感染症の場合は、一般的にお腹や背中など舐める部位が複数でてきます。ほかのペットや飼い主にも影響が出る可能性があるため、早めの駆虫を行いましょう。

【関連記事】犬のフィラリア症は予防薬で確実に防げる!症状や正しい薬の使い方を解説【獣医師監修】
心理的な要因
留守番の時間が長い、家族構成の変化、運動不足などのストレスが原因で過剰なグルーミングや舐める症状が現れる場合もあります。足先や尻尾、腕やお腹など、舐めやすい箇所で生じやすいです。
心因性の行動は無意識に繰り返す癖のようなもので、根本的に解決するためには行動療法や生活改善が必要です。心因性皮膚炎はほかの皮膚炎がないかを調べ除外して判断するため、必ず動物病院で相談しましょう。
傷口を舐めさせないための家庭ケア

犬の擦り傷が悪化する主な原因のひとつが、舐めることによる刺激です。自分で傷を舐めてしまうと、細菌感染や炎症の拡大を引き起こす場合があります。ここでは、家庭で簡単にできる方法をご紹介します。
エリザベスカラーで舐めを防止
エリザベスカラーは、犬が患部を舐めるのを物理的に防ぐための保護具です。動物病院でも手術後や傷口保護のために広く使われており、シンプルで効果的な方法といえます。
エリザベスカラーにはプラスチック製・布製・ソフトタイプなどの種類がありますが、犬種や傷の部位に合わせて選ぶことで、ストレスを軽減しながら効果的に舐め癖を抑えることが可能です。使用する場合は、鼻先がエリザベスカラーからでないように、サイズを確認しましょう。
洋服や靴下でカバー
傷口が足先や身体の表面にある場合は、洋服や靴下を利用してカバーするのも効果的です。 特に足や指の間にできた擦り傷は、舐めやすく地面とこすれたり、砂利などが付着しやすい部位のため注意が必要になります。
犬用の靴下やソックスを使用する場合は、滑り止めや通気性があるものを選びましょう。ただし、傷口が直接布に付いてしまったり、通気性が悪くなるデメリットもあるため、使用する場合は獣医師に相談して使用するのがおすすめです。
包帯・保護フィルムを正しく活用
包帯や動物用の被覆材も、傷口を物理的にカバーする役割があります。ただし、間違った使い方をすると通気性が失われ、患部が蒸れて細菌が繁殖する原因にもなるため注意が必要です。動物病院では傷の深さや部位に応じた適切な使い方を教えてくれるので、不安がある場合は相談してみましょう。
病院に行くべきかの判断基準

「このくらいなら大丈夫」と自己判断する前に、病院を受診すべきかどうかの判断基準を事前に知っておくことが大切です。
傷の深さ・広がり・出血量が重度
擦り傷といっても、深さや広がりによって重症度は大きく異なります。出血が止まらない場合や、広範囲にわたる場合は、皮膚の下の組織までダメージを受けている可能性があります。
特に、筋肉層や脂肪組織が露出しているような深い傷は、手術による治療が必要なケースもあるため、すぐに動物病院を受診してください。
傷が膿んでいる・悪臭がある
膿や悪臭がある場合は、傷がすでに細菌に感染し、炎症を起こしている可能性が高いです。こうした状態は、放置すると周囲の皮膚組織にまで炎症が広がったり、血管を通して全身に感染するリスクもあるので、必ず動物病院を受診しましょう。
日常生活に支障が出ている
歩き方がおかしい、食欲が落ちている、眠れないなど、日常生活に変化が見られる場合は体に強い不快感や痛みがあるサインです。擦り傷が原因であっても、痛みや炎症が広がってしまうと、犬の生活に大きな影響を及ぼします。外から見える症状以上に体内で問題が起きている可能性もあるため、早めの受診が重要です。
ケガ以外の症状がある
傷口のほかに、嘔吐、下痢、発熱、ふらつきなどの全身症状が見られる場合は、傷以外に別の病気が関係していることも考えられます。細菌感染が全身に広がっていたり、免疫疾患が隠れている場合は非常に危険です。複数の症状が重なった場合は、迷わず動物病院へ行きましょう。
日常でできる擦り傷の予防方法

犬の擦り傷は、日常生活の中でのちょっとした工夫で予防が可能です。完全に防ぐことは難しくても、飼い主が皮膚の状態に注意を払い、適切なケアを続けることで、傷や感染のリスクを大きく下げることができます。ここでは、日々の生活に取り入れやすい4つの方法をご紹介します。
指先チェックを毎日のルーティンに
指の間や肉球は、地面と接触するため擦り傷が起こりやすい部位のひとつです。散歩や遊びのあとには、足裏や指の間の皮膚を清潔なタオルなどで拭き取りながら観察する習慣をつけましょう。砂や細い棘などの小さな異物が挟まっている可能性があります。日々のチェックで早期に異常を発見して、悪化を防ぐことが重要です。
舐め癖を防ぐにはストレスケアも重要
舐め癖はケガや病気だけでなく、ストレスや不安といった心理的要因も同時に背景にあることもめずらしくありません。舐め癖が定着する前に、散歩や遊びの時間を確保し、飼い主とのふれあいで安心感を与えることが大切です。
心因性皮膚炎は環境改善だけでなく、ストレス軽減作用のある内服薬やサプリメントなどの活用で症状が改善する場合もあります。
乾燥する季節はクリームで保湿を
冬場は、犬の皮膚も乾燥しやすくなります。乾燥した皮膚はバリア機能が低下し、軽い刺激でも傷がつきやすくなるため、特に肉球や足先には保湿ケアが有効です。ペット専用の保湿クリームや肉球用バームを使い、散歩の前後や就寝前に軽く塗ってあげると、擦り傷の予防になります。
定期的に専門家に見てもらおう
自宅でのケアに加えて、動物病院やトリミングサロンなど、専門家による定期的なチェックも効果的です。飼い主が気づきにくい部分も細かく見てもらえるため、早期発見につながります。さらに正しいシャンプーや爪切りの方法、皮膚の保護グッズの使い方など、日頃のケア方法を相談してみるのもおすすめです。
舐めるのは体からのサイン。見逃さずやさしくケアを
愛犬が体をしきりに舐めているときは“体からのサイン”かもしれません。舐める原因はさまざまですが、どれも放っておくと悪化するリスクがあります。「気になるな」と思ったら、まずは傷の有無や様子をチェックしてみましょう。 必要であれば、ためらわずに動物病院に相談することが最善です。毎日のケアと観察を心がけ、楽しみながら愛犬の健康をサポートしてあげてくださいね。
【執筆・監修】
原田 瑠菜
獣医師、ライター。大学卒業後、畜産系組合に入職し乳牛の診療に携わる。その後は動物病院で犬や猫を中心とした診療業務に従事。現在は動物病院で働く傍ら、ライターとしてペット系記事を中心に執筆や監修をおこなっている。