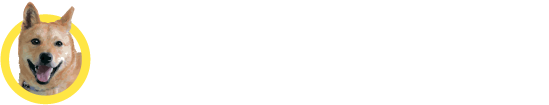「犬が散歩中スキップのような歩き方をする」
「膝を伸ばすような仕草をする」
これらの行動は、膝蓋骨脱臼のサインかもしれません。膝蓋骨脱臼は、特に小型犬に多く見られる病気で、重症化すると関節の変形や痛みで歩くのが困難になり、手術が必要になります。この記事では、膝蓋骨脱臼とはどんな病気なのか、基本知識から症状のグレード分類、検査方法、手術の適応まで詳しく解説します。犬の歩行が気になっている飼い主さんは、ぜひ参考にしてください。
膝蓋骨脱臼(パテラ)とは

膝蓋骨(しつがいこつ)は膝の前面にあり、いわゆる「膝のお皿」と呼ばれている骨です。大腿四頭筋(だいたいしとうきん)の筋力を効率よく膝下にある脛骨(けいこつ)に伝え、膝をスムーズに曲げ延ばしをするための滑車の働きをしています。
膝蓋骨は、大腿四頭筋とその末端から伸びる膝蓋腱(しつがいけん)に適度に引っ張られることで、大腿骨の末端にある溝の中に収まっています。
膝蓋骨脱臼は、何らかの原因で膝蓋骨がこの溝から外れてしまう病気です。脱臼の方向や程度、頻度によって症状が異なり、膝蓋骨の英名“patella”から「パテラ」という通称で呼ばれたりもします。
膝蓋骨脱臼(パテラ)の種類
膝蓋骨脱臼には、膝蓋骨がずれる向きによって、内方脱臼と外方脱臼があります。
内方脱臼
膝蓋骨が体の内側にずれる状態です。小型犬ではこちらのほうが圧倒的に大多数を占めます。
外方脱臼
膝蓋骨が体の外側にずれる状態です。大型犬では比較的、外方脱臼が多くみられます。
犬種問わず発生するが、小型犬がほとんど
膝蓋骨脱臼は、トイプードル、チワワ、ポメラニアンなど、小型犬が圧倒的に多いです。現在の日本では小型犬の方が飼育数が多いということを加味しても、大型犬での発生は少なく、症例のほとんどは小型犬です。
膝蓋骨脱臼(パテラ)の原因とグレード分類

膝蓋骨脱臼は、遺伝的な要因と、外傷やジャンプしたときの衝撃が原因となります。
膝蓋骨脱臼(パテラ)のグレード分類
膝蓋骨脱臼の重症度は、脱臼の状態や膝蓋骨の戻り方によってグレード1〜4に分類されます。数字が大きくなるほど重症です。グレード分類は、治療方針や予後の判断にとても重要な診断になります。
| 脱臼の状態 | 膝蓋骨の戻り方 | |
| グレード1 | 通常は正常位置にあるが、指で押すと脱臼する | 自然に元の位置に戻る |
| グレード2 | 自然に脱臼することがある | 手で戻す必要があるが、比較的容易に戻せる |
| グレード3 | 脱臼したままの状態が多い | 手で戻せるが、すぐにまた外れる |
| グレード4 | 常に脱臼しており、膝蓋骨自体や周りの骨の変形も伴う | 手で戻すことができない |
放置するとほかの関節や靭帯の病気を引き起こすことも
膝蓋骨脱臼は放置すると重症化するだけでなく、関節の変形や靭帯を痛めたり、靭帯断裂を起こしたりするリスクも高まります。問題の足をかばううちに、ほかの足を痛めてしまう可能性もあるので、早めの対処が大事です。
小型犬にグレード1、2が多いといわれる理由
小型犬に比較的軽度の膝蓋骨脱臼が多いのは、以下の2つの理由が関係しています。
- 遺伝的な素因
- 骨と筋肉の発育のアンバランスさ
遺伝的な素因
小型犬には遺伝的に、膝関節の構造が浅く、大腿骨や脛骨がやや湾曲しているため、脱臼しやすいといった骨格的な特徴があります。
また、膝蓋骨脱臼は遺伝しやすく、親犬に膝蓋骨脱臼があると子犬も受け継ぐ可能性があります。そのため、 繁殖時にグレードの高い親犬を避けたほうがよいでしょう。
骨と筋肉の発育時のアンバランスさ
小型犬は、急速に体が大きく成長する一方で、筋肉量が少ないため、骨のサポートする筋肉の力が不十分なケースがあります。成長期に運動をさせすぎたり、滑りやすい床で過ごしたせいで発育中の筋肉や骨に変な力が加わってしまうといった環境要因も、膝蓋骨脱臼につながる、発育のバランスを崩しやすい要因になります。
膝蓋骨脱臼(パテラ)の症状

膝蓋骨脱臼でみられる症状は、以下のとおりです。
- スキップのような歩き方になる(スキップ歩様は膝蓋骨脱臼で特有の症状)
- ケンケンする
- 足を後ろに伸ばす動きをする
- 散歩や運動を嫌がる
- 足を地面に着いたり、飼い主に触れられたりするのを嫌がる
無理に脱臼(パテラ)を戻そうとするのは禁物
脱臼している膝蓋骨を飼い主が元に整復しようとするのは絶対にやめましょう。
膝関節にはたくさんの靭帯や軟骨が集まる部分です。無理な力をかけるとそれらを傷つける可能性があります。また、すでに関節が変形していたり、靭帯断裂などを伴っていたりした場合は、無理やり膝蓋骨を動かすことで逆に状態を悪化させてしまう危険があります。
一時的に膝蓋骨の位置が戻っても、グレードが進んでいれば脱臼を繰り返すため、獣医師の判断と適切な治療が必要です。
膝蓋骨脱臼(パテラ)の検査方法

動物病院では、身体検査(視診・触診・歩行観察)と画像検査(レントゲン)を中心に検査します。状況によっては骨の立体的構造をより正確に評価するためのCT検査や関節鏡検査、エコー検査などを行うこともあります。
身体検査(視診・触診・歩行観察)

立ち姿や歩き方を観察します。脱臼があるときは、触診で膝蓋骨を手で左右に動かしてどの方向にどの程度動くか、正常の位置に戻るかを調べ、グレード分類を判断します。
画像検査(レントゲン)

骨の位置関係や関節周りの状態を評価します。グレード3〜4では、骨の変形や関節の摩耗がみられることもあります。
膝蓋骨脱臼の治療法
グレード分類ごとの基本的な治療方針をまとめました。
| 治療方針 | 手術の適用 | |
| グレード1 | 保存療法 | 手術は不要。経過観察を行う。 |
| グレード2 | 保存療法、もしくは外科手術 | 頻繁な脱臼や、痛みなどで生活に支障があれば手術を検討する。 |
| グレード3 | 原則は外科手術を推奨 | 歩行異常や常時脱臼があるケースでは手術が望ましい。 |
| グレード4 | 骨格矯正を含む外科手術が必要 | 外科手術が基本。足全体を含めた術前評価が重要。 |
保存療法
主にグレード1〜2の軽症に適応されます。
- 運動制限(滑る床やジャンプを避ける)
- 体重管理(膝への負担軽減)
- 筋力強化のためのリハビリ(太ももの筋肉をつけて膝を安定させる)
- サプリメント(グルコサミン・コンドロイチンなど関節保護)
- 鎮痛薬や消炎剤(炎症・痛みがある場合)
外科手術
グレード2の後半〜4が対象です。特に歩行障害や痛み、骨変形がある場合は早期手術が推奨されます。
手術には、大腿骨の溝を削る、腱の付着部を外科的に移動するなどいくつかの方法があります。骨の変形を伴う重症例では、骨を切って角度を調整する難しい手術を行うこともあります。手術の手法は、足の状態や犬の体重、年齢などで選択します。

膝蓋骨脱臼の手術費用
実施する術式にもよりますが、15万円〜40万円程度と考えましょう。
術後の過ごし方
一般的には、手術後2〜5日の入院が必要です。
退院後はしばらく運動を制限し、ケージやサークルの中で過ごさせます。定期的に受診し、獣医師の許可が出れば短時間から散歩ができるようになります。グレード3〜4や骨切りを行ったケースでは、マッサージ、可動域訓練、水中トレッドミルなど術後のリハビリも有効です。

痛み止めや抗生物質の投薬や、傷口を舐めないためのエリザベスカラーの装着も忘れずに行いましょう。元の生活に戻るには、6〜8週間かかると考えましょう。
術後の再発リスク
犬の膝蓋骨脱臼に対して手術を行った場合の再発リスクは、術式や犬の状態により異なりますが、適切な手術と術後管理ができていれば再脱臼の確率はかなり低くなります。
飼い主ができる予防と日常ケア

親兄弟が膝蓋骨脱臼を起こしやすい家系の犬や、脱臼歴のある犬では、普段から膝に負担をかけないようにしましょう。
室内の環境対策
ジャンプの衝撃で脱臼することもあります。段差はスロープを付けたり、滑りやすい床はマットを敷いたりして対策をしましょう。
肥満予防
適切に体重管理をして、関節への負担を減らしましょう。
適度な筋力トレーニング
運動や散歩のしすぎもよくありません。適度な運動を心がけましょう。
まとめ
この記事では、犬の膝蓋骨脱臼について、原因や症状のグレード分類、治療の方法を解説しました。膝蓋骨脱臼は、軽度であれば保存療法を行いながら経過観察をしますが、重症になると外科手術が必要です。グレード判定に基づいた治療方法の選択、術後の安静とリハビリが再発予防と回復に重要です。
また、飼育環境の整備や体重管理といったおうちでのケアも大切です。
股関節脱臼は、症状が軽いうちに気づいてあげることが、愛犬の健康を守る第一歩です。気になることがあったら獣医師に相談しましょう。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。